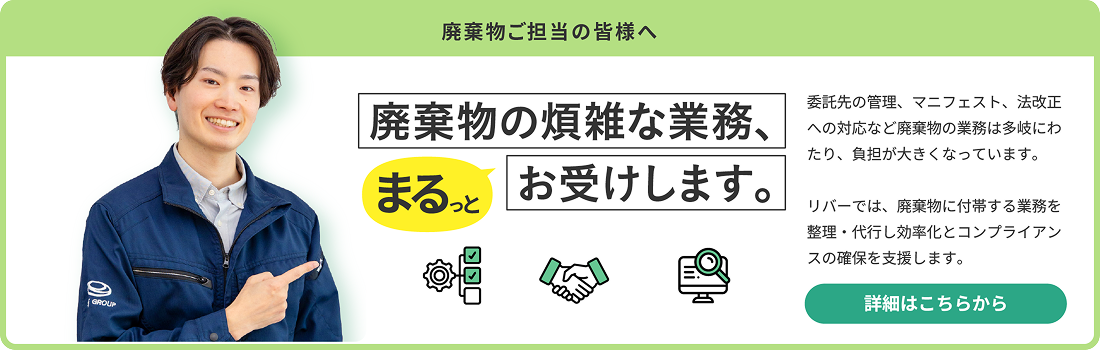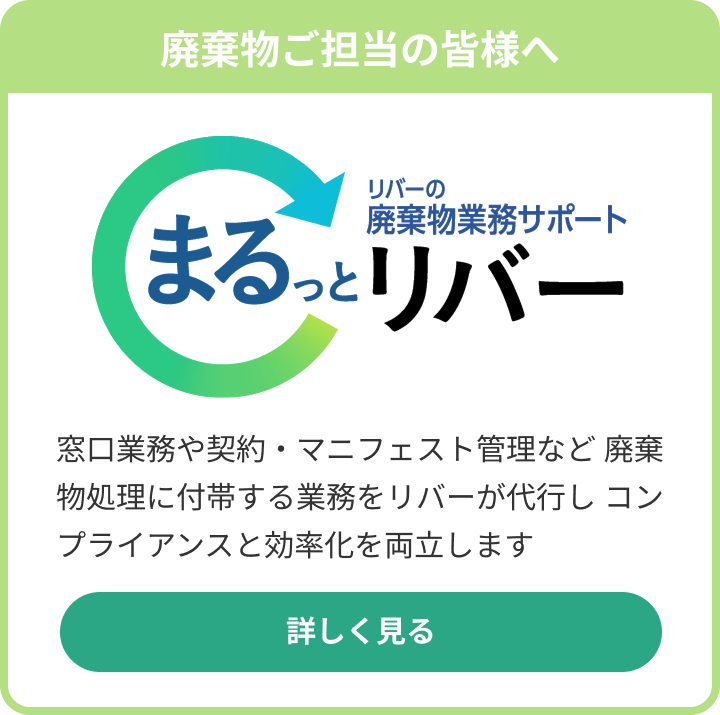産業廃棄物の処理を委託する際には必ず発行しなければならないマニフェスト。
運用の流れや書き方についてわかりやすく解説します。
「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」とは、廃棄物が適正に処理されているか確認するために用いる書類です。
日本国内では、高度成長期からバブル期(1950年代~90年代初頭)にかけて、モノの製造・消費が増大するとともに、廃棄物の量も急激に増えました。これにともない、不法投棄など不適正な処理も横行し、社会問題に。
そこで、1990年、産業廃棄物の流れを確認して、適正な処理を行うことを目的とする「産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度」が任意運用としてスタート。1993年に義務化されました。
ここでは、この「マニフェスト」がどのようなもので、どのように利用すれば廃棄物を適正に管理できるのかを、順を追って説明していきます。
1.マニフェストとは
産業廃棄物が契約内容通りに適正処理されたか確認するために排出事業者が交付する伝票です
マニフェストの交付が義務化された当初は、特別管理産業廃棄物を対象とした紙マニフェストの運用のみでしたが、1998年12月に全ての産業廃棄物に対象範囲が拡大され、同時に電子マニフェストが制度化されました。
紙マニフェストも電子マニフェストも排出事業者が交付するもので、基本的な運用方法に違いはありません(詳しくは5.紙マニフェストと電子マニフェストの比較を参照ください)。

2.マニフェスト運用の流れ
最終処分までの各工程でマニフェストを発行します
紙マニフェストは複写式で、A票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票の7枚綴りとなっています。このそれぞれに役割があり、また、排出事業者、収集運搬業者、処分業者のそれぞれで記載しなければならない事項が決められています。
また、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に交付するマニフェストを「1次マニフェスト」、処分業者が処分後の残さ物を最終処分業者などに処理委託する際に交付するマニフェストを「2次マニフェスト」といいます。1次マニフェストと2次マニフェストの運用方法も、基本的に同じです。
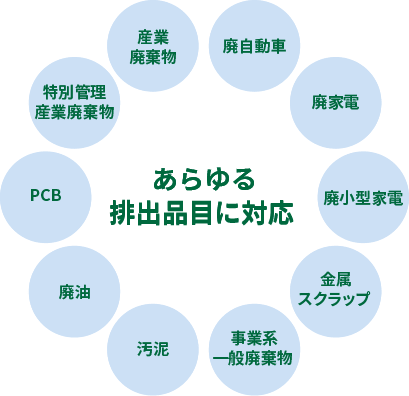
発行したマニフェストは、5年分保管しなければなりません
これらのマニフェストは、交付した排出事業者と、それを受け取った処理業者の双方で、5年間にわたり保管することが義務付けられています。
それぞれ以下の伝票を保管することになります。
| 保管するマニフェスト伝票(伝票の役割) | ||
|---|---|---|
| 排出事業者 | A票(排出時の自社控え) | 排出時に必要事項を記入し収集運搬業者の受領サインの後、A票のみを切り取ります |
| B2票(運搬終了の確認) | 収集運搬業者が運搬を完了したとき、お手元に届きます | |
| D票(処分終了の確認) | 中間処理業者が処分を完了したとき、お手元に届きます | |
| E票(最終処分終了の確認) | 最終処分が完了したとき、お手元に届きます | |
| 収集運搬業者 | B1票(運搬終了の自社控え) | B1票:運搬終了時に終了年月日を記載しB1票とB2票を切り取ります(B2票は排出事業者へ送付) |
| C2票(処分終了の確認) | C2票:中間処理業者が処分を完了したとき、手元に届きます | |
| 中間処理業者 | C1票(処分終了の自社控え) | C1票:処分終了時に終了年月日を記載しC1票、C2票、D票を切り取ります(C2票は収集運搬業者、D票は排出事業者へ送付) |
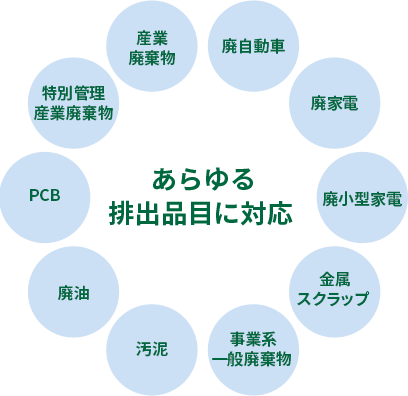
3. マニフェストの書き方
(記載項目)
A票に必要な情報をすべて記載します
紙マニフェストは複写式になっているため、直接記載が必要なのはA票のみです。ここには、以下の項目を含め、必要な情報全てを記載します。
また電子マニフェストでも、一つの入力画面から必要な情報全てを記入できるようになっています。
主な記載内容
- 引き渡す産業廃棄物の種類
- 引き渡す産業廃棄物の量
- 運搬を委託する業者
- 運搬先
- 処分を委託する業者
など
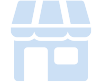
出典:公益社団法人全国産業資源循環連合会
| ①「交付年月日」 | マニフェストを交付した日付を記入 |
|---|---|
| ②「交付担当者」 | マニフェストの交付を担当した者を記入 |
| ③「排出事業者」 | 排出事業者の氏名又は名称、住所、電話番号を記入 |
| ④「排出事業場」 | 排出場の名称、所在地、電話番号を記入 |
| ⑤「産業廃棄物」 | 排出する産業廃棄物の種類にチェック |
| ⑥「数量」 | 排出する産業廃棄物の数量を記入 (単位は自由 (kg、㎥、車など)) |
| ⑦「荷姿」 | バラ積み、フレコンバッグ入りなど荷姿を記入 |
| ⑧「産業廃棄物の名称」 | 廃棄物の概要が分かるように記入 (廃タイヤ、業務用冷蔵庫など) |
| ⑨「有害物質等」 | 有害物質が含まれている場合記入 |
| ⑩「処分方法」 |
「破砕」「切断」「圧縮」など 当該産業廃棄物の処分方法を記入 |
| ⑪「中間処理産業廃棄物」 | 中間処理業者が残さ物を処理委託する際に記入 |
| ⑫「最終処分の場所」 | 最終処分する予定の場所を記入 |
| ⑬「運搬受託者」 | 運搬を委託する収集運搬業者の名称などを記入 |
| ⑭「運搬先の事業場」 | 契約している処分業者の事業場を記入 |
| ⑮「処分受託者」 | 契約している処分業者の名称などを記入 |
| ⑯「積替え又は保管」 | 積替保管を行う場合のみ記入 |
4. マニフェスト運用上の注意点
マニフェストには返却期限があります
排出事業者が交付し、収集運搬業者や処分業者の手に渡ったマニフェストは、運搬・処分が終わったのち、控えを残して排出事業者の手元に返すよう定められています。それぞれのマニフェストが戻ってくるまでの期日は以下の通りです。
90日以内
180日以内

もし、期日までに戻ってこなかったら?
期日までにマニフェストが返却されない場合は、収集運搬業者、処分業者に状況を確認する必要があります。
その後は状況に応じて必要な措置を講じるとともに、都道府県に「措置内容報告書」を提出しなければなりません。
定められた義務に違反した場合には罰則があります
マニフェストに関する規定に排出事業者が従わなかった場合は、廃棄物処理法違反とみなされ、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
例えば、次のようなケースが該当します。
廃棄物を委託したとき
虚偽の内容を記載したとき
保管していないとき
など

罰則
廃棄物処理法違反で、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
5.紙マニフェストと
電子マニフェストの比較
紙マニフェストと電子マニフェストの運用方法は基本的に同じですが、媒体の性質上、それぞれ以下のようなメリット・デメリットがあります。一部の廃棄物を除き、どちらを利用してもかまいません※。
(公社)全国産業資源循環連合会などが用紙を販売
![]() メリット
メリット
- すぐに作成できる。
- 排出回数が少なければ手間がかからない。
![]() デメリット
デメリット
- 記載間違いや記載漏れが起こりやすい。
- 紛失のリスクがある。
- 5年分のマニフェスト保管が必要。
- 毎年、報告書の提出が義務。
(公財)日本産業廃棄物処理振興センターがサービスを運営(JWNET)
![]() メリット
メリット
- マニフェストがシステム上で適正に管理できる。
- いつでも閲覧できるので、リアルタイムでの状況把握が容易。
- 事務処理が効率化できる 。
![]() デメリット
デメリット
- 導入費用がかかる。
- 排出事業者から収集運搬業者、処分業者までのすべての関係者がシステムを利用する必要がある。
※2020年4月から、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50トン以上の事業場で特別管理産業廃棄物(PCB 廃棄物を除く)の処理を委託する場合、電子マニフェストの使用が義務付けられました。
お手元に残して業務に役立てていただけるよう、この記事の内容を「マニフェストハンドブック」として資料にまとめていますのでご活用ください。
当社は、マニフェストの管理サポートなど廃棄物に関わる皆様の業務を大幅に削減するサポートを行っています。お気軽にご相談ください。