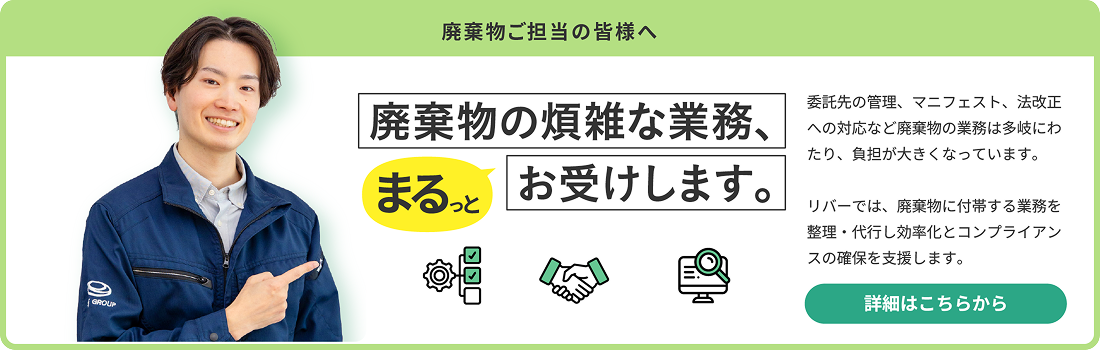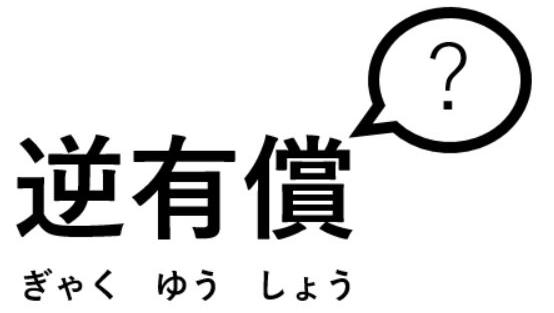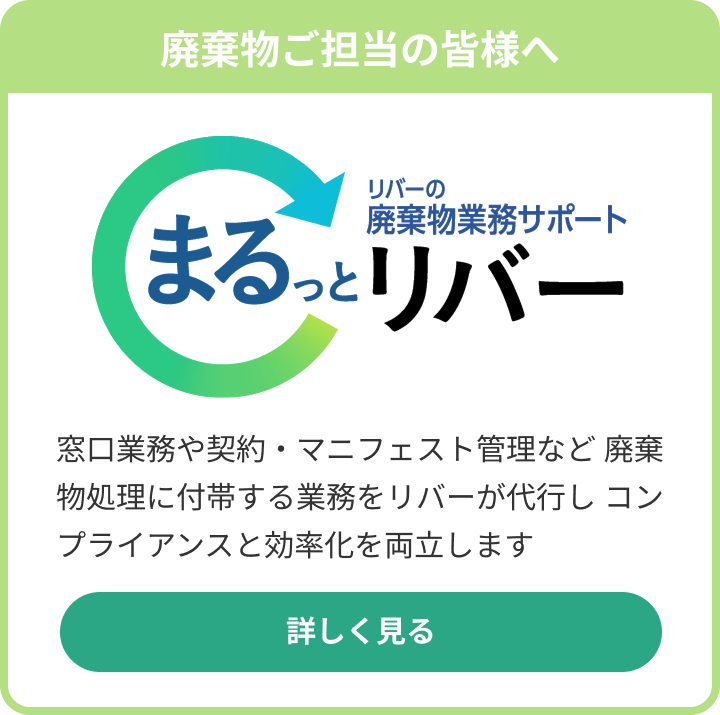産業廃棄物とは、事業活動から出た廃棄物のうち、法令で定める20品目(種類)の廃棄物のことをいいます。
事業者には法令に定められた適正な処理が求められます。
私たちは日々の生活や経済活動の中でさまざまなごみ(廃棄物)を排出しています。近年ではごみの減量やリサイクルへの機運が高まっていますが、
一方で、公害問題やごみの不法投棄・不正転売事件などは、今なお社会問題となっています。
このような問題から、廃棄物に対する規制も厳格化。特に廃棄物(産業廃棄物)を排出する事業者に対して、厳しく責任を問うようになりました。
ここでは、産業廃棄物の処理を正しく理解するためのポイントを簡単に解説していきます。
1.廃棄物の分類
そもそも廃棄物とは、自分で利用したり他人に有償で売却することができないために不要となったもののことです。大きく「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分けられ、このうち「産業廃棄物」は、事業活動に伴って排出されたもののうち、廃棄物処理法で定められた20品目(種類)を指します。これにあたらないものはすべて「一般廃棄物」となり、会社などから出るものは「事業系一般廃棄物」と呼ばれます。
なお、ここでの事業活動には、製造業や建設業の業務だけでなく、オフィスや商店での商業活動、学校などでの公共的事業も含まれることに注意が必要です。「産業」というと日々の暮らしからは縁遠いように思えますが、いたって身近なものなのです。
廃棄物の分類

※不要物でもガス状の物などは廃棄物として扱いません。
2.産業廃棄物の種類、具体的には?
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)では、産業廃棄物を以下の20品目と定めています。
| 産業廃棄物の種類 | 具体例 | ||
|---|---|---|---|
| あらゆる事業活動に伴うもの (業種限定なし) |
1 | 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、その他の焼却残さ |
| 2 | 汚泥 | 排水処理後及び各種製造業生産工程で排水された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、洗車場汚泥、建設汚泥、浄水汚泥等各種汚泥状のもの | |
| 3 | 廃油 | 鉱物性油、動植物性油脂、廃潤滑油、絶縁油、廃切削油、廃溶剤類、タールピッチ類等すべての廃油 | |
| 4 | 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、廃定着液などの酸性の廃液 | |
| 5 | 廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん廃液、廃現像液 などのアルカリ性の廃液 | |
| 6 | 廃プラスチック類 | ビニールくず、発泡スチロールくず、合成ゴムくず、廃タイヤ、合成繊維くず、合成樹脂くずなど、固形状・液状の全ての合成高分子系化合物 | |
| 7 | ゴムくず | 天然ゴムくず | |
| 8 | 金属くず | 研磨くず、切削くず、空缶、金属スクラップ | |
| 9 | ガラスくず、コンクリート及び陶磁器くず | ガラスくず、レンガくず、陶磁器くず、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、廃石膏ボード等 | |
| 10 | 鉱さい | 高炉・電気炉等の溶解炉かす、ボタ、スラグ、ノロ、廃鋳物砂、不良鉱石、不良石炭かす等 | |
| 11 | がれき類 | 工作物の新築・改築等で発生したコンクリート破片、アスファルトくず、その他これらに類する不要物 | |
| 12 | ばいじん | ばい煙発生施設等で発生するばいじんで集じん施設で集められたもの | |
| 特定の事業活動に伴うもの (業種限定あり) |
13 | 紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたものに限る)、パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業のうち新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの、製本業、印刷物加工業、出版業のうち印刷出版を行うものから生ずる紙くず |
| 14 | 木くず | 建設業に係るもの(工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたものに限る)、木材・木製品製造業(家具製造業)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業から生ずる木くず。貨物の流通のために使用した木製パレット(排出事業者の業種を問わず) | |
| 15 | 繊維くず | 建設業に係るもの(工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から生ずる繊維くず | |
| 16 | 動植物性残さ | 食料品・医薬品・香料製造業で原料として使用した動植物の固形状の不要物 | |
| 17 | 動物系固形不要物 | と畜場の獣畜・食鳥に係る固形状の不要物 | |
| 18 | 動物のふん尿 | 畜産農業の動物のふん尿 | |
| 19 | 動物の死体 | 畜産農業の動物の死体 | |
| 20 | 政令第13号廃棄物 | 上記1から19の産業廃棄物を処理したもので、1から19に該当しないもの(コンクリート固型化物等) | |
※特別管理産業廃棄物: 産業廃棄物のうち危険性・有害性の高い揮発油類などの廃油、廃酸(ph2.0以下の酸性廃液)、廃アルカリ(ph12.5以上のアルカリ性廃液)、感染症産業廃棄物、特定有害産業廃棄物(PCB、廃石綿、水銀など有害金属等を含む産業廃棄物)
これだけだと、いまひとつイメージがつかない……という方もいるかもしれません。身近な廃棄物のなかから、判断に迷いやすい例をいくつか挙げてみましょう。
例えば、工場の庭に生えている木を剪定したとき。切り落とされた木の枝は、産業廃棄物と一般廃棄物のどちらになるでしょうか。
答えは一般廃棄物(事業系一般廃棄物)です。「産業廃棄物の『14.木くず』に当たるのでは?」と思われがちですが、定められた20品目のうち「13.紙くず」から「19.動物の死体」までの7種類は、特定の業種・事業で排出されたものだけを産業廃棄物として扱います。
逆に一般廃棄物と勘違いしやすいのがCDやDVD。企業が販促のためにつくったものを破棄したなど、事業に伴って排出された場合は、産業廃棄物の「6.廃プラスチック類」に分類されます。
判断がつきにくい品物の例

木製パレット
貨物輸送用だけが産業廃棄物

工場内で剪定した枝
(事業系)一般廃棄物

引越しごみ
オフィスから排出された場合、種類により産業廃棄物

オフィスのコピー用紙や木製家具
(事業系)一般廃棄物

飲食店の残飯
(事業系)一般廃棄物

販促用のDVD
企業が保管していたものを捨てた場合、産業廃棄物
3.産業廃棄物の適正処理とは? 処理の流れと遵守事項
(1)「排出事業者責任」の考え方
日本国内の法律では、産業廃棄物を排出した事業者には「排出事業者責任」が発生します。
廃棄物処理法によれば、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければなりません(第3条1項)。また、事業者はその産業廃棄物を自ら処理しなければならないと定めています(第11条1項)。
しかし、実際には排出事業者が自ら産業廃棄物を処理するのは現実的ではありません。専用の処理施設が必要になることはもちろん、コストや手間もかかるためです。そのため、産業廃棄物を収集運搬、処分できる外部の廃棄物処理業者に処理を委託するのが一般的です。
とはいえ、処理を委託しても「排出事業者責任」がなくなるわけではありません。排出事業者は、自分たちが出した産業廃棄物が、最後まで適正に処理されたかを確認する必要があります。万一、委託先の業者などが違反行為をすれば、排出事業者にもその責任が及ぶ可能性があるため、注意が必要です。
(2)委託のルール
排出事業者が収集運搬業者や処分業者などの外部業者に産業廃棄物の処理を委託する場合にも、守るべきルールがあります。
1つ目は、都道府県等から産業廃棄物処理業の許可を受けた処理業者に処理を委託すること。
2つ目は、処理業者と事前に書面による契約を締結すること。収集運搬業者、処分業者のそれぞれと委託契約書を取り交わす必要があります。
また、この委託契約書には、法令で記載しなければならない項目が定められています(法定記載事項)。
3つ目は、契約内容どおりに産業廃棄物が処理されたかを確認すること。この確認のために、排出事業者は、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付しなければなりません。
(3)処理の流れ
- 排出
-

- 保管
-

- 収集運搬
-

- 中間処理
-

- 最終処分またはリサイクル
4.委託の際のポイント
産業廃棄物の処理や運搬を委託するときは、その業者が産業廃棄物処理業の許可を受けていることはもちろん、処理能力や設備の状況なども確かめる必要があります。以下のようなポイントに沿って確認していきましょう。
(1)許可内容などの確認
産業廃棄物の収集運搬、処分を委託する処理業者は、それぞれ「産業廃棄物収集運搬業許可」「産業廃棄物処分業許可」を有している必要があります。
これらの有無は、業者が有している許可証で確認できます。
チェックのポイントは、「許可自治体」と「許可品目」です。
許可自治体
収集運搬業者は、産業廃棄物の排出場所と運搬先の両方の都道府県等から収集運搬業許可を得ている必要があります。
また、処分業者については、産業廃棄物を処理する施設がある都道府県等の処分業許可が必要です。
許可品目
委託予定の産業廃棄物について、廃棄物処理法の20品目のどれに対応するかを確認し、対応する品目に関して、その業者が許可を有しているかをチェックします。プラスチック製のものの処理を委託したいのであれば「廃プラスチック類」、研磨くずや金属スクラップなど金属製のものの処理を委託したいのであれば「金属くず」が許可品目に含まれることを確かめましょう。
許可内容のチェックポイント
| 委託先 | 許可の種類 | チェック項目 | チェックのポイント |
|---|---|---|---|
| 収集運搬業者 | 産業廃棄物収集運搬業許可 | 許可自治体 | 以下の両方から許可を得ている
|
| 許可品目 | 委託予定の産業廃棄物と対応する品目について、収集・運搬の許可を得ている。品目が複数ある場合は、そのすべてについて確認する | ||
| 処分業者 | 産業廃棄物処分業許可 | 許可自治体 |
|
| 許可品目 | 委託予定の産業廃棄物と対応する品目について、処分の許可を得ている。品目が複数ある場合は、そのすべてについて確認する |
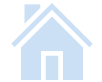
(2)現地での確認
処分業者の処理場を実際に訪問して確認することも重要です。その業者が産業廃棄物を適切に処理できるかどうかは、主に以下の視点で確認すると良いでしょう。
現地確認でのチェックポイント
| 処理施設の状況 |
|
|---|---|
| 処理場での処理の流れ | 受け入れから処理完了までの一連の工程が適正である |
| 中間処理後の流れ | リサイクルや最終処分に至るまでの一連の工程が適正である |
| 書類の管理状況 | 委託契約書やマニフェストが適正に管理されている |
処理に関する設備やプロセスとあわせて、委託契約書などの書類を管理する体制がどうなっているかも確かめておくと、より確実です。
このほかにも求める点や条件があれば確かめておきましょう。「あまり細かいことを聞くのも」と気が引ける方もいるかもしれませんが、排出事業者責任を有する企業として、「安心して業務を委託できる」と確信できる業者を選ぶことが何より大切です。
関連リンク