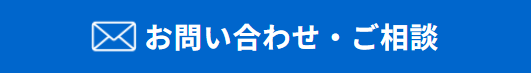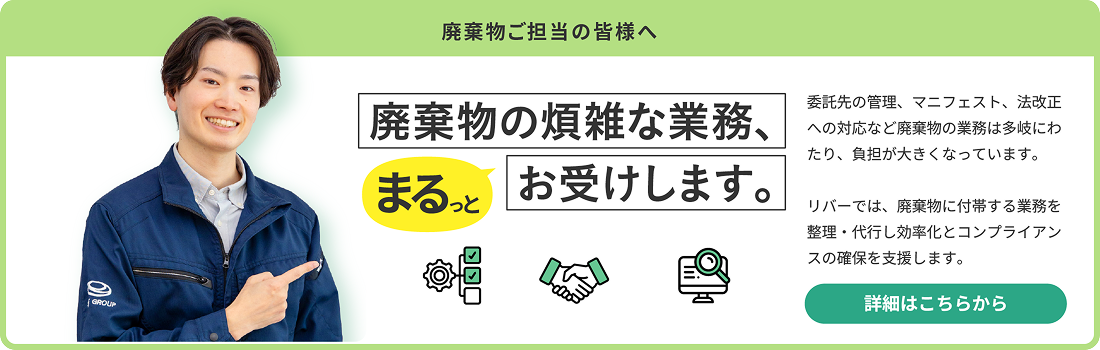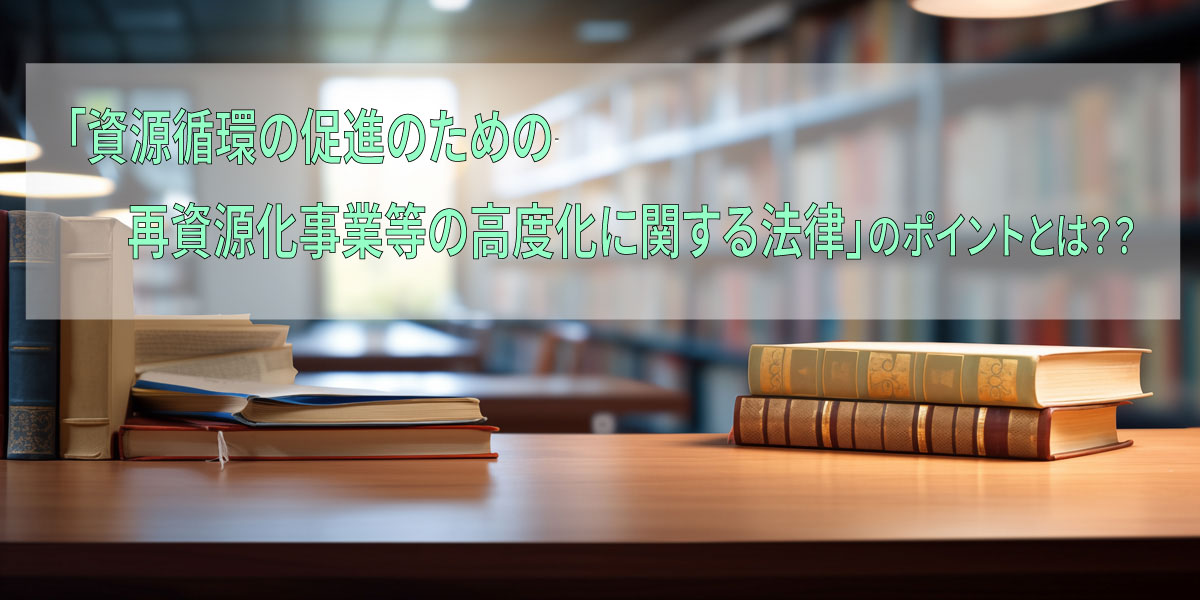よく聞く「逆有償」って何?
2018年02月28日
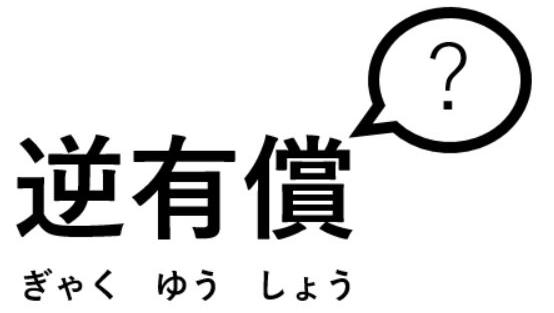
目次
逆有償とは
中古品や古本をリサイクルショップや古本屋に持ちこむ場合、少額ででも買ってもらえるだろうと期待しますよね。
買取をうたっていますし、一般にモノの取引は“売買”が基本なのですから、それが自然な感覚でしょう。
オフィスや工場でも、不要になる機械類や什器を買い取ってもらったり、新品購入時に無料で下取りしてもらうこともあります。
そこには「ゴミ」であるという感覚はほとんどなく、まだ使えるものだという認識もあるかもしれません。
このような不用品売買の文脈で逆有償という言葉が使われると、
●逆有償とは:買ってもらうどころか、あべこべにお金を払わないといけない=処理費を払うこと
というニュアンスになります。
通常のお金の流れと“逆”であるということで、逆有償なのです。
スクラップ業界でもこのような感覚で、逆有償とは「スクラップを売りに来たつもりのお客さんから、処理費を頂かなければならない」ある意味、異常事態を指します。
一方の廃棄物は売れない前提のモノです。
家庭ごみは「無料」かゴミ袋を買って回収してもらいますし、産業廃棄物も処理費を払うのが基本です。
したがって、処理費を払うことをわざわざ逆有償ということはほとんどありません。
ところが、廃棄物処理の文脈でも逆有償という言葉があえて使われることがあります。その場合、
●逆有償とは:それ自体は有償で売却できるのに、運賃の方が高いため、トータルでは費用を払わなければならないこと
という取引を指すことが多いのです。
モノを出す人が費用負担するという意味では同じなのですが、そのモノ自体は売れるのです。
「逆有償」という表現は「せっかく有価物として買ってもらえるのに、結局マイナスに逆戻りしてしまった…」という気持ちが生んだものなのでしょう。
つまり、「逆有償」という言葉は、語られる文脈によって、全く別の意味を持っているのです。
以前は、スクラップ業界と産業廃棄物業界の関係者が言葉を交わすことはほとんどなく、大きな混乱は生じなかったのですが、最近は交流が深まっています。
しかも今年からは、有償売却できる雑品スクラップを廃棄物処理法が規制するようになります。
今後はどちらの業界もこの言葉を使わないようにした方が良いかもしれません。
スクラップ業界は逆有償を「処理費or廃棄物」、産業廃棄物業界は「手元マイナス」という言葉を使うのはどうでしょうか。
「手元マイナス」は、環境省も委員会などで使用しているほぼ公式な表現です。規制改革通知では以下のように説明しています。
規制改革通知 環廃産発第 050325002 号 平成17年3月25日
http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/tuuti.pdf
●手元マイナスとは:産業廃棄物の占有者(排出事業者等)がその産業廃棄物を、再生利用又は電気、熱若しくはガスのエネルギー源として利用するために有償で譲り受ける者へ引渡す場合においては、引渡し側が輸送費を負担し、当該輸送費が売却代金を上回る場合等当該産業廃棄物の引渡しに係る事業全体において引渡し側に経済的損失が生じている場合
この場合について、「有償で譲り受ける=買ってくれる」者に引き渡した以降は廃棄物ではないという説明が続きます。
しかし、運搬時については言及がありません。そのため、旧通知で「運搬時は廃棄物である」と説明していたこともあり、安全側に立って運搬時は産業廃棄物として扱っていることが多いようです。
ただし、旧通知を新しくしたのは、東日本大震災後に副産物をエネルギー源としての使用を推進するために、遠方に運搬するために運賃が高くなってしまう場合でも、有価物として扱えるように規制緩和をする目的でもありました。
リサイクルに資するのであれば、専門家や関係者と協議するなどして運搬時も有価物として運用できないか検討してみるのもよいでしょう。
(リバーグループ/メジャーヴィーナス・ジャパン株式会社 シニアコンサルタント・行政書士 堀口昌澄)
リサイクルのご相談、お問い合せ
リバーグループでは様々な廃棄物、有価物の回収から処分まで一貫して対応しています。買取や費用のことなどお気軽にご相談ください。
TEL:03-6365-1201(代)
(受付時間:平日10:00~18:00)
また当社は、廃棄物の処理・リサイクルに加え、廃棄物の業務負担を削減するサービスを行っています。ぜひご覧ください。