世界文化遺産、韮山反射炉に興味ありますよね?私はもちろんありますよ、もちろん。
2017年11月27日

資源リサイクル・産業廃棄物処理業のスズトクの若手営業担当のコラムです!! 入社以来スズトク一筋の社員の、生の声をお届けします。
目次
鉄くず小僧です!
世界文化遺産に登録された『韮山反射炉』
日本では、大気環境を保全するため、昭和43年に「大気汚染防止法」が制定されました。この法律は、大気汚染に関して、国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することなどを目的としています。そういった時代背景の中で、「ばい煙」を排出してしまう為、現在は稼働しておりませんが、平成27年(2015年)7月に、世界文化遺産に登録された『韮山反射炉』という築造物が、静岡県伊豆の国市にあります。
この『反射炉』は、日本の産業分野を推し進めていく中で、非常に重要な物でありました。天保11年(1840年)のアヘン戦争を契機に、日本では列強諸国に対抗する為の軍事力の強化が大きな課題となりました。
嘉永6年(1853年)ペリー艦隊の来航を受け、幕府もついに海防体制の抜本的な強化に乗り出し、「西洋砲術の導入」、「鉄製大砲の生産」、「海軍の創設」、「西洋式の訓練の導入」などを、以前から幕府に進言してきた、江川英龍(えがわひでたつ)を責任者として、反射炉の築造を決定いたしました。
そんな、鉄製大砲の生産を行っていたという歴史から、私、鉄くず小僧が、Feの臭いにつられて、現場に行って参りました!
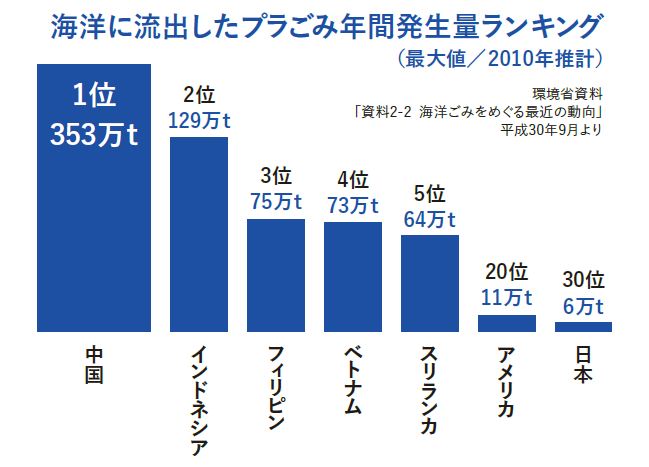
反射炉の歴史と普及
反射炉は、17世紀から18世紀にかけてヨーロッパで発達。金属を溶かして大砲などを鋳造する為の溶解炉で、内部の天井がドーム状になった炉体部と煉瓦積みの高い煙突からなり、石炭などを燃料として発生させた熱や炎を炉内の天井で反射し、一点に集中させることにより、銑鉄(鉄鉱石から直接製造した鉄で、不純物を多く含む)を溶かすことが可能な千数百度の高温を実現させています。このような熱や炎を反射する仕組みから、反射炉と呼ばれてきました。
反射炉は、嘉永6年(1853年)12月に下田港に近い賀茂郡本郷村(現下田市)にて、基礎工事が始められました。この場所が選ばれたのは、資材や原料鉄の搬入と、生産した大砲の搬出・回送の便を考えてのことだった様です。しかし、翌安政元年(1855年)3月末、下田に入港していたペリー艦隊の水兵が、反射炉建設地内に進入するという事件が起こりました。この時既に日米和親条約が締結され、下田は開港場となっていたため、今後も同様の事態が起こることが予想されました。
そこで、急遽反射炉建設地を移転することになったのです。移転先は、韮山代官所にも近い田方郡中村(現伊豆の国市)と決定されました。 その後、建造は比較的順調に進みましたが、安政2年(1856年)1月、江川英龍(えがわひでたつ)は反射炉の竣工を見ることなく病死してしまいます。後を継いだ江川英敏(えがわひでとし)は、英龍の代から交流があり、また蘭学の導入に積極的で反射炉の建造も行っていた佐賀藩に応援を求め、技師の派遣を要請しました。
佐賀藩は、杉谷雍助(すぎたにようすけ)ら11名を韮山に派遣し、英敏の要請に応えています。その結果、安政4年(1858年)11月、すべての炉が稼働可能な状態となり、反射炉は着工から3年半の歳月をかけて、ようやく完成したのでした。なお、反射炉の周りには砲身の内部をくり抜くための錐台(すいだい)や付属品の細工小屋など、大小の施設が付属されていました。反射炉は、それらの施設も含めて、大砲の製造工場だったといえます。完成した反射炉では、元治元年(1864年)に使用が中止されるまでに数多くの鉄製砲が鋳造されました。

(鋳造された大砲のレプリカ)

(反射炉使用の耐火レンガ)
現在も残る韮山反射炉ですが、明治41年、昭和32年、昭和60年~平成元年の3回の補修工事を経て今に至ります。敷地内の小山を登ると、目の前には富士山が有り、静かに反射炉の歴史を見つめておりました。皆さんも、静岡方面に行った際には、是非立ち寄ってみてはいかがでしょうか。









