海洋プラ問題の最終的な落としどころは?|海洋プラスチック問題への対応策を3つの切り口から考える
2019年07月30日
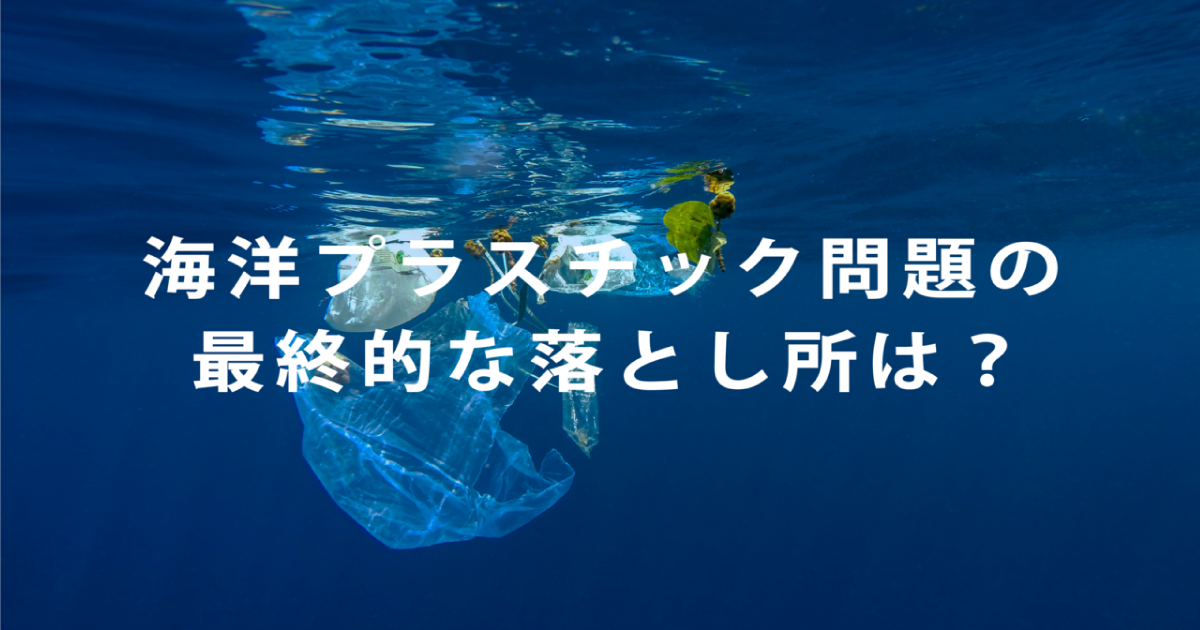
この記事のポイント
・2019年7月8日に環境ブランド調査2019の結果が発表され、容器の軽量化、植物由来原料の使用、回収・リサイクルなどの取り組みをしている企業が評価された。
・海洋プラスチック問題への対応策は、回収・リサイクル、素材の変更、使用しない(事業モデルを変える)の3つ。
・海洋プラ問題への効果が高い取り組みは、事業への影響が大きい。
目次
各企業が出来るところから対策を打っていますが…
2019年7月8日に環境ブランド調査2019の結果が発表されましたが、サントリーが3年連続で1位でした。容器の軽量化や植物由来原料の使用などが評価されたようですが、プラスチックストローの全廃宣言をしたスターバックスも前年の27位から7位に順位を上げました。
環境ブランド調査2019の結果はこちら>>
最近、報道で目にすることが増えた海洋プラスチック問題 への対応策としては、
- 回収・リサイクルの仕組みを作る
- 素材を変更する
- 使用しない(事業モデルを変える)
が考えられますが、効果の高さは3→2→1の順でしょう。3は言わば3Rの最優先のリデュース又はリユースであり、通常は売り上げの低下を招くためでしょうか、日本国内ではどの分野でもあまり進展しておらず、環境省の委員会などでも課題となっています。
サントリーのこれまでの取組も1、2が主でしたが、スターバックスは以前よりマイタンブラーを取り入れるなど3に取組んできました。この違いは、3は商品やサービスの提供方法の変更であるため、ユーザーに直結しているスターバックスのほうが取り組みやすいという理由も考えられます。
多くの企業では3の効果が高いことは分かっていても、それに踏み切る段階にはないために1と2のような、事業形態への影響が少ない=やりやすい取り組みをしています。サントリーは6月に大阪市と連携し、「キャップとラベルを分別、洗浄された質の高いペットボトルを買取る」という新しい取り組みを発表しましたが、これも1の高度化です。先進的とはいえ、最近見受けられるイベントや公共機関などでのウォータースタンドの設置、ペットボトル飲料の配布の取りやめ等の動きへの「守りの対策」という印象がぬぐえません。
他にも、製品そのものの2や3ができないために、出来るところから対策を取っている例もあります。例えば、合成繊維の衣類を洗濯するとマイクロプラスチックが発生しますが、ユニクロなどは1の使用済み衣類の回収や、2のプラスチック袋を有料紙袋にするなどの対策を取っています。
また、キッチンスポンジからは使用中にマイクロプラスチックが流出していると思われますが、3Mがキッチンスポンジの回収をするのも1の取組みです。当然ですが今回の廃プラ問題は、化学品メーカーとしては大変なリスクです。
以前から行われている、食品用プラスチックトレーの回収も1ですが、今後は生分解プラスチックへの変更どころか、容器をガラスや金属に戻してリユースしたり、昔ながらの量り売り+紙袋包装が好ましいという流れにならないとも限りません。例えばP&Gやユニリーバは、シャンプー等の容器を金属などの非プラスチックの素材に変更し、回収・リユースする3に該当する仕組みを2020年に展開する予定です。これは既に海外では実績がある、テラサイクルという前出の3Mのスポンジ回収も支える会社と組むそうです。
テラサイクルのWebサイトはこちら>>
各企業が、出来るところから対策を打っています。良いことだとは思いますが、1を完璧にすることはできません。最終的には“製品そのもの”の2か3が必要になるのではないでしょうか。覚悟を決めて、そのつもりで計画を立てる必要があるかもしれません。
(リバーグループ/メジャーヴィーナス・ジャパン株式会社 シニアコンサルタント・行政書士 堀口昌澄)







