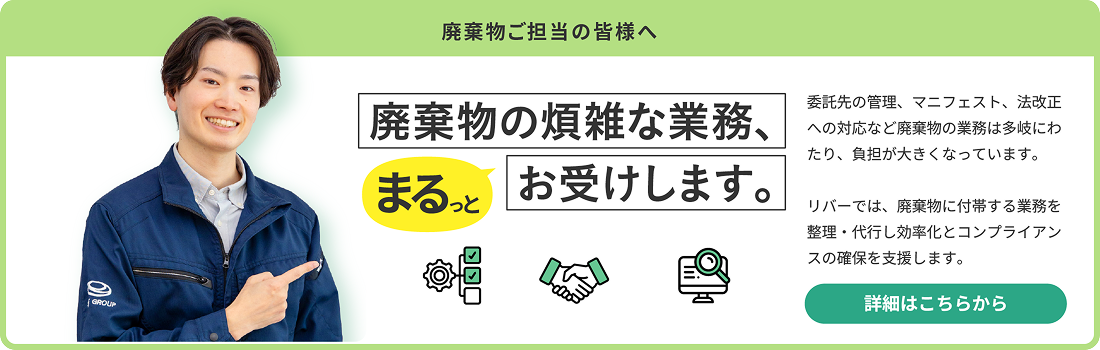静脈産業とは?経済発展に不可欠な理由と高度循環型社会への展望
2025年07月08日

近年、循環型社会の実現に向けて欠かせない産業として「静脈産業」が注目を集めています。SDGsの推進や地球温暖化対策といった環境問題への配慮が世界的に重要視されるなか、静脈産業は資源を循環させるビジネスモデルとして期待を集めているためです。
この記事では、静脈産業がどのような背景で注目されるようになったのか、その成り立ちから現在抱える課題、静脈産業の全体像を詳しく解説します。
目次
静脈産業とは廃棄物の回収・再生・処理などを行う産業
静脈産業とは、製品の製造や使用に伴って生じた廃棄物を回収し、再資源化・再利用・適正処理を通じて資源を循環させる産業のことです。
これに対して動脈産業は、資源をもとに製品を設計・製造し、流通・販売までを担う産業を指します。
「動脈」「静脈」という呼び方は、二つの産業の関係を人体の血液循環に例えたものです。動脈は製品の社会への供給を、静脈は不要となったものの回収と循環を担うイメージです。
静脈産業は循環型社会を支える基盤として、資源の有効利用や環境負荷の低減に寄与しており、今後ますます重要性が高まるとみられています。
静脈産業が”初めに“注目された背景
近年、静脈産業の役割が広く注目されるようになった背景には、廃棄物を取り巻く社会的な課題が深刻化していることが挙げられます。国や自治体、企業が「排出後」の対応を重視する傾向が高まった流れのなかで、資源を有効に循環させる静脈産業が重要な産業分野として位置づけられるようになりました。
大量生産・大量消費の時代
戦後の高度経済成長期の日本は、モノを大量に作り、使い、捨てる「大量生産・大量消費」の時代でした。製造業を中心とした動脈産業の発展と、それに伴う消費活動の活発化によって、廃棄物の排出量が急増しました。さらに、工業化の進展により深刻な環境汚染が広がり、公害問題も次第に顕在化していきました。
水俣病やイタイイタイ病などの公害病は、こうした汚染によって引き起こされ、多くの人々に甚大な健康被害をもたらしました。このような事態を受けて、工場から排出される有害物質の適正な処理を義務づける法律が制定されるなど、公害対策が段階的に進められ、1980年代までに産業に起因する公害への対策は着実な進展を見せました。
一方で、ごみ問題は大きな社会問題となっていきます。バブル景気を背景に廃棄物はその量・種類ともに増加の一途をたどり、埋立に必要な最終処分場の不足が深刻化したのです。
戦後最大級の大量不法投棄事件
静脈産業への注目を決定づけたのが、香川県豊島(てしま)で発生した「産業廃棄物の不法投棄事件」です。この事件では、汚染された土壌を含む廃棄物の量は90万トン以上と判明。その撤去には14年もの歳月を要しました。
全国的にも深刻な環境問題として報道され、社会に大きな衝撃を与えたこの事件は、廃棄物処理の在り方に対する関心を高め、1990年代には、廃棄物の減量、リサイクル、再資源化を目的とする法整備と施策が進められました。規制強化とともに静脈産業の整備と育成を後押しする契機となりました。
豊島事件については、以下の記事で詳しく紹介しています。あわせてお読みください。
豊島事件が残した課題|真の循環型社会に向けて(3-1) | ecoo online | 廃棄物処理のことならリバー
豊島事件が残した課題|真の循環型社会に向けて(3-2) | ecoo online | 廃棄物処理のことならリバー
豊島事件が残した課題|真の循環型社会に向けて(3-3) | ecoo online | 廃棄物処理のことならリバー
静脈産業の現状と課題
静脈産業は、循環型社会の実現に不可欠な分野として発展を続けています。2000年には「循環型社会形成推進基本法」が制定され、その後も国の政策のもと、関連法の整備と取り組みが着実に進められてきました。
環境省は毎年「令和6年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」の中で、日本国内における1年間の資源の採取、消費、廃棄の総量を重量ベースで示した「物質フロー」を公表しています。令和6年度版の白書によると、2021年度の天然資源等投入量は約11億9,000万トンで、2000年度と比べて約38%減少しました。一方、同年の循環利用量(再使用と再生利用の合計)は約2億3,500万トンで、2000年度から約10%増加しています。
最終処分量は約1,234万トンと、同じく2000年度と比べて約78%減少し、2025年度の目標である1,300万トンを前倒しで達成しました。
経済成長や人口増加が進むなかで、資源の使い捨てを前提とした経済モデルには限界があると指摘されています。経済産業省が示した「循環経済ビジョン2020」は、今後は資源の投入・消費を抑えながら、国内に蓄積されたストックを活用し、サービス化によって付加価値を高める循環経済への転換が重要であるとしています。
この先、より高度な循環型社会の構築を推し進めていくためには、静脈産業はその中核を担う存在として、さらに多様な産業との連携と持続的な成長を果たしていくことが求められているのです。
世界規模での環境問題が深刻化
現在、地球規模での環境問題が深刻さを増しています。2050年には世界人口が97億人に達すると予測されており、それに伴い新興国を中心とした資源需要の急増が見込まれています。
仮に何も対策が取られなければ、廃棄物の排出量や不適切な処理も今後さらに増えるとされており、地球温暖化や海洋プラスチックごみの問題といった複合的な環境負荷もさらに拡大することが懸念されます。こうした状況を受け、国際社会では経済活動の前提を見直し、資源の効率的な利用や再利用を重視する制度改革が進められており、静脈産業は単なる廃棄物処理の枠を超え資源循環を支える社会インフラとしての重要性を高めています。廃棄物を適切に回収・再資源化する仕組みを構築することは、持続可能な社会を支えるうえで不可欠なテーマであるといえます。
静脈産業が抱える課題
循環型社会の実現には、静脈産業と動脈産業の連携による、資源循環を前提とした新たな産業構造の構築が欠かせません。
しかし現状では、静脈産業におけるリサイクル技術や処理工程の体系化・標準化が不十分であり、業務効率や情報共有体制の整備も遅れています。さらに、両産業の連携を支える基盤となるデジタル化も、静脈産業側では導入が進んでおらず、連携の土台が整っていないのが実情です。
これらの課題の背景には、地方行政による許認可制度に起因する産業構造上の特性があります。財務資本や人材、設備が限られた小規模事業者が地域に点在し、多くは新たな仕組みに対応する余力を持っていません。一方で、ノウハウや経営力を備えた海外の大規模企業が日本市場への参入を進めており、今後は競争の激化が予想されます。
こうした状況のなか、国内の静脈産業が持続的に成長し、循環型社会の中核を担い続けるには、産業構造の抜本的な見直しと実効性のある対策が急がれます。
静脈産業と動脈産業の連携強化による「高度循環型社会」へ
静脈産業は、単に廃棄物を処理する業種ではなく、再生資源を安定的に供給する「資源循環の要」としてその存在感を増しています。今後は動脈産業との連携を強化し、資源の投入から製品の設計・流通・使用・回収・再資源化に至るまでの一連の流れを円滑にする仕組みづくりが重要となります。
例えば、動脈産業がリサイクルしやすい製品設計を行うことで、静脈産業における処理や再利用の効率が向上し全体の循環プロセスがスムーズになります。こうした連携を通じて、高品質な再生資源の安定供給と環境負荷の低減が期待でき、社会全体として資源の循環を最適化する「高度循環型社会」の実現に近づくことができるでしょう。
静脈産業で社会貢献を目指すリバー
静脈産業は、廃棄物の回収・再生・処理を担う産業として、循環型社会の実現に不可欠な存在です。戦後の大量生産・大量消費時代を経て、豊島の不法投棄事件などを契機に社会的関心が高まり、現在では環境負荷削減と資源の有効活用を両立する重要な産業分野として位置づけられています。
今後は動脈産業との連携をさらに深め、高品質な再生資源の安定供給を通じて、持続可能な社会の実現に貢献することが期待されます。
事業活動で排出される産業廃棄物の処理にお困りであれば、リバーへご相談ください。再利用できない廃棄物もまとめて処分できるため、ワンストップで対応いたします。