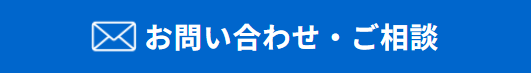なぜアルミ缶はリサイクルの優等生といわれるのか?
2025年07月23日

アルミ缶リサイクルは、持続可能な社会の実現に向けた重要な取り組みとして注目されています。品質劣化が少なく、繰り返し利用可能なアルミニウムは、省エネルギーやCO2削減の観点からも高い評価を受けています。
本記事では、アルミ缶リサイクルの基本プロセス、国内外の現状、注目される理由、多様な用途展開、さらには課題や今後の展望について詳しく解説し、なぜリサイクルの「優等生」として期待されるのかを探ります。
目次
アルミ缶リサイクルの基礎知識
コンビニの回収ボックスやスーパーのリサイクルコーナーなど、アルミ缶リサイクルは、いまや日常の風景です。
実はこのアルミ缶、リサイクルの世界では「優等生」として知られています。なぜなら、繰り返し使用しても品質がほとんど劣化せず、資源として持続的に循環利用できる素材とされているためです。 しかも、新たにアルミをつくる場合に比べて、リサイクルはエネルギー消費もCO2排出も大幅に抑えられます。
アルミ缶リサイクルは、持続可能な社会の実現に向けた重要な取り組みとして、今あらためて注目されています。
ここでは、アルミ缶リサイクルの基本的な流れや国内外の現状、さらにはなぜ優等生といわれているのかを解説します。
アルミ缶はリサイクルで何に生まれ変わる?
回収されたアルミ缶は、リサイクル工程を経てさまざまな新しい製品へと生まれ変わります。最も代表的なものは飲料用アルミ缶としての再利用ですが、そのほかにも自動車のエンジン部品やホイール、建物の窓枠や外壁材、電子機器のパーツ、家庭用調理器具など、多岐にわたる分野で活用されます。
また、鉄を作る際の脱酸材としても重要な役割を果たしており、産業用途にも幅広く貢献しています。
国内外のアルミ缶消費量とリサイクル率の推移
日本のアルミ缶消費量は過去10年間、微減傾向で推移しており、アルミ缶リサイクル協会の調査によれば、2024年度の国内消費量は約209億缶です。
また、日本のアルミ缶リサイクル率は極めて高く、2024年度には99.8%という世界トップクラスの数値を記録しました。これは、70%程度といわれる世界平均のリサイクル率を大きく上回るものであり、日本の回収・リサイクルシステムが高度な水準にあることを示しています。
一方、世界全体のアルミ缶市場規模も拡大傾向にあり、2025年には約535億米ドル、2030年には約668億米ドルに達すると予測されています。今後も年平均4.5%程度の成長が見込まれており、飲料や食品の包装需要の増加、環境意識の高まりが市場を後押ししています。
日本は世界でも有数のアルミ缶リサイクル先進国であり、今後もアルミ缶リサイクルの重要性と市場規模はさらに拡大していくと予測されています。
参照:日本アルミ協会「リサイクル率」
日本アルミ協会「世界各国のアルミ缶リサイクル率」
アルミ缶リサイクルが注目される理由
アルミ缶リサイクルが注目される大きな理由のひとつは、環境負荷の大幅な低減と省エネルギー効果にあります。
アルミ缶をリサイクルして再生地金(溶かしたアルミニウムをかたまりにしたもの)を製造する際に必要なエネルギーは、新たにボーキサイトという天然資源から地金を製造する場合のわずか3%で済み、97%ものエネルギーを節約することが可能です。
その結果、CO2排出量も新地金製造時の1/30に抑えられ、地球温暖化対策にも大きく貢献します。また、アルミ缶は品質劣化が少なく、何度でも缶から缶へと水平リサイクル(CAN to CAN)が可能です。そのためアルミ缶は、環境負荷を抑えつつ資源を効率的に循環させるうえで、極めて優れた素材といえます。
さらに、スチール缶やペットボトルと比較しても、リサイクル率が高いことが知られています。この三者を比較可能な2023年度の日本国内の数値で見ると、スチール缶が93.5%、ペットボトルが85.0%に対して、アルミ缶97.5%に達しています。
このような高効率なリサイクルは、廃棄物削減や資源の有効活用にもつながります。脱炭素社会の実現やサーキュラーエコノミーへの移行が重要な課題となっている今、エネルギー消費やCO2排出量を大幅に抑えられるアルミ缶リサイクルは、持続可能な社会づくりに不可欠な取り組みとして、今後ますます重要性を増すと考えられます。
日本のリサイクル率については、以下の記事も参考にしてください。
「日本のリサイクル率はどれくらい?素材や品目ごとの現状を解説」
出典:日本アルミ協会「リサイクル率」
出典:日本アルミ協会「リサイクルについて」
アルミ缶リサイクルのプロセスと多様な用途
ここでは、アルミ缶の回収から再生までの具体的なプロセス、再生されたアルミニウムが、どのような製品や分野で活用されているかを紹介します。
回収から再生までの流れと技術進化
アルミ缶リサイクルのプロセスは、使用済み缶の回収・選別・圧縮から始まり、異物や塗装を除去した後、高温で溶解して再生地金化する流れが基本です。近年はキルン加熱などの技術進化によって塗料や異物の除去効率が向上し、より高品質なリサイクル地金の生産が可能になっています。
また、バーコードやICタグを活用したトレーサビリティの強化に加え、光学センサーやAIを活用した自動選別技術の導入によって、リサイクル工程全体の効率化が進んでいます。
CAN to CAN(缶から缶へ)リサイクルの現状と意義
CAN to CAN(缶から缶へ)リサイクルとは、使用済みアルミ缶を再び新しいアルミ缶として生まれ変わらせる水平リサイクルの仕組みです。
カスケードリサイクル(元の用途とは異なる、かつ通常は元の用途よりも価値が低い形で再利用すること)に比べ、CAN to CANは高品質な資源循環を維持できる点が大きな意義です。
アルミ缶リサイクル協会の調査によれば、2024年度の日本のCAN to CAN率は75.7%に達し、回収されたアルミ缶の多くが再び飲料缶として利用されています。品質劣化が少なく繰り返し再生できるアルミニウムの特性を最大限に活かしたリサイクルであり、資源循環型社会の実現やCO2排出量の削減、省エネルギーに大きく貢献しています。
さらに国内の包装容器製造企業が100%再生アルミ製飲料缶(蓋含む)の量産を目指すなど、100%リサイクル缶の普及に向けた取り組みがはじまっています。こうした取り組みは、新たな資源の採掘を減らし、CO2排出量を大幅に削減するうえで極めて重要な意義を持ちます。
出典:アルミ缶リサイクル協会
地域に根ざしたアルミ缶リサイクル活動
アルミ缶リサイクルは、地域や社会全体で支えられている活動です。自治体や学校、ボランティア団体などが協力して回収活動を行い、分別の徹底や啓発活動も積極的に展開されています。
優れた回収活動を行った団体や個人を対象に「アルミ缶回収協力者表彰」や「アルミ缶小・中学校回収協力者表彰」が実施されており、2024年度には全国の一般団体65団体、小・中学校42校が表彰されました。
さらに、国内の大手化学会社ではほとんどの従業員が参加するアルミ缶リサイクル活動を長年にわたって継続し、回収したアルミ缶の売却益を地域の学校や福祉団体に寄付してきています。このような表彰や啓発活動は、地域コミュニティの連携強化や環境意識の醸成に大きく貢献しています。
アルミ缶リサイクルの多用途展開
アルミ缶リサイクルは、使い終えた缶が再びアルミ缶やアルミ製品として使われるだけにとどまりません。鉄をつくる過程で使われる「脱酸材」としても再利用されています。脱酸材は、鉄をつくるときに溶けた鉄から酸素を取り除くために使われ、アルミ缶由来のアルミニウムが鉄鋼の現場でも欠かせない役割を担っています。
さらに、リサイクルされたアルミニウムは、自動車の部品、建物の資材、電子機器のパーツなどにも使われており、用途の広がりが進んでいます。このような多方面での活用が、資源の無駄を減らし、ごみの発生を抑える取り組みに結びついています。結果として、持続可能な社会づくりにも貢献しています。
今後の展望と「優等生」としてのアルミ缶リサイクル
アルミ缶は高いリサイクル率を維持していますが、その価値はそれだけでは終わりません。上述したとおり、アルミ缶リサイクルは、製造時のエネルギー消費やCO2排出量の大幅な削減、資源の国内循環による経済的な自立、さらには自動車部品や建築資材など幅広い分野への再利用を通じて、社会全体の持続可能性向上にも貢献しています。
今後は、国内での再利用の流れをさらに強めることや、リサイクルに関する技術を進化させる取り組みが求められます。あわせて、市民一人ひとりがリサイクルへの意識を高めることも重要です。
国内循環強化と技術革新の展望
アルミ缶リサイクルは、今後さらに発展が見込まれる分野です。国内で資源を循環させる仕組みを強化するうえでは、より効率的な回収体制や再生処理の仕組みを整えるための政策の動きに注目が集まっています。
環境への負担を減らすため、アルミ缶そのものを軽くしたり、薄くしたりする技術も進んでいます。これにより、原材料の使用量を抑えられるだけでなく、運搬時のCO2排出量の削減にもつながります。
・リデュース (Reduce):ごみ減量
・リユース (Reuse):再使用
・リサイクル (Recycle):再資源化
という3Rの考え方は、今後も循環型社会を支える基本的な方向性です。アルミ缶リサイクルは、この3Rを実現するうえで重要な役割を担っており、素材としての優れた特性と技術の進歩によって、今後の価値がさらに高まっていきます。
アルミ缶リサイクルの課題と今後の可能性
アルミ缶は非常に高いリサイクル率を維持していますが、今後さらに発展させるには、いくつかの課題に取り組む必要があります。
まず求められるのは、現在の高い回収率を安定的に保ち、さらに向上させる工夫です。とくに、屋外やイベント会場などで発生する回収漏れを減らす仕組みが求められます。また、これまで多く輸出されてきた再生アルミを、国内で効率よく使い回す流れへと切り替えることも大きな課題です。
こうした問題に対応するには、消費者が分別を意識して行動することが前提となります。そのうえで、企業はリサイクルしやすい製品の設計や技術開発に取り組み、自治体は無駄のない回収体制を整える必要があります。そして、これらすべての関係者が連携を深めることで、アルミ缶リサイクルの可能性をさらに広げていけます。
一人ひとりができるアクションと社会全体への期待
アルミ缶リサイクルをさらに広め、今後の成長につなげるには、私たち一人ひとりの具体的な行動が欠かせません。最初のステップは、使用後のアルミ缶をしっかりと分別し、回収に協力することです。
住んでいる地域のルールに従いながら、スーパーなどに設置された回収ボックスも積極的に利用しましょう。さらに、リサイクルされたアルミニウムを使った製品を選ぶことは、再生資源の需要を高めるうえで有効な手段です。これにより、リサイクルの流れがより活発になります。
このような意識の変化が、企業の取り組みを後押しし、社会全体にリサイクルの流れが広がっていきます。企業や自治体、そして私たち消費者が連携して行動すれば、資源が循環する持続可能な社会の実現に一歩近づきます。