豊島事件が残した課題|真の循環型社会に向けて(3-1)
2020年12月10日
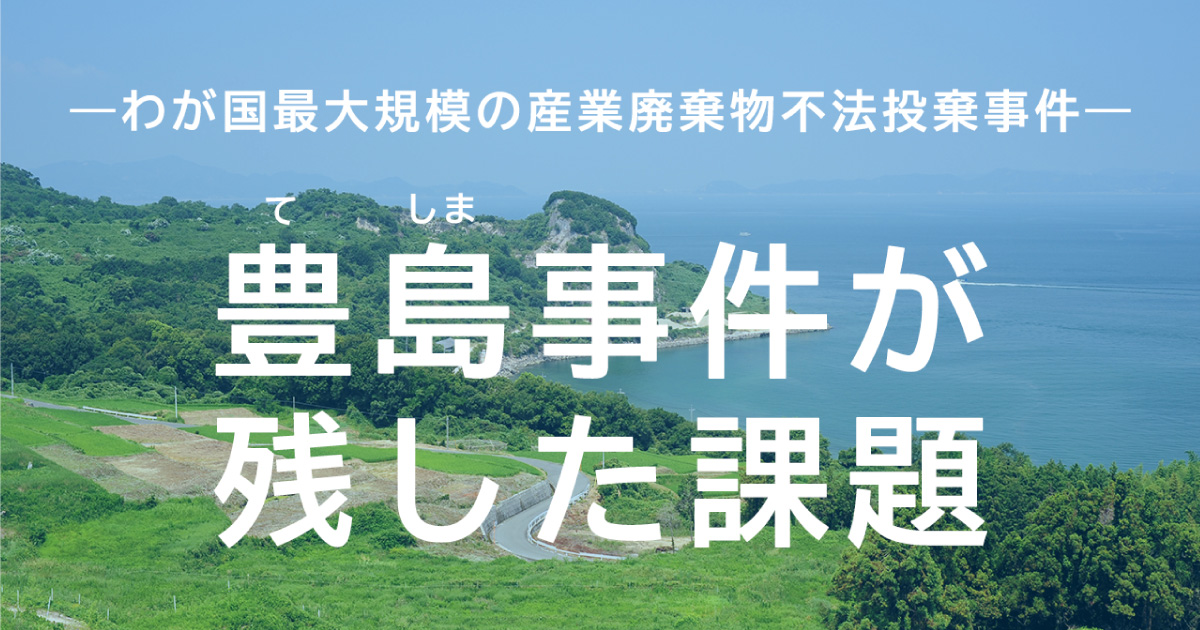
目次
風光明媚な瀬戸内海に浮かぶ香川県の豊島。清水が湧き出る棚田や、オリーブ畑やレモン畑ののどかな風景が広がるこの小さな島は、近年、豊島美術館や瀬戸内国際芸術祭により「アートの島」として世界の注目を集めるようになりました。
しかし、数十年前には悪臭漂う「ごみの島」と揶揄された時代がありました。わが国最大規模の産業廃棄物不法投棄事件と、それに敢然と立ち向かった住民たちの闘いが、その後の日本の環境政策に与えたインパクトは計り知れません。
現代のプラスチックごみ問題へと続く、私たち日本人と廃棄物との闘い。そのターニングポイントとなった「豊島問題」から、この特集はスタートします。
豊島事件と住民運動の軌跡
事件の発端は1975年、豊島の事業者「豊島総合観光開発株式会社」が、香川県に対し島の西端の水ヶ浦で、廃棄物を取り扱う処理業の申請を行ったことでした。これが、決着まで実に44年の歳月と800億円もの莫大な費用を要した、日本最大級の廃棄物不法投棄問題へと発展していくことになるのです。
日本の産業廃棄物処理の課題を浮き彫りにした「豊島事件」
その事業者は、以前にも暴力事件や、島の貴重な資源である砂を勝手に掘り起こして売りさばくなどの問題を起こしていた、いわくつきの人物でした。このままでは島の美しい自然環境が損なわれ、農漁業に悪影響を及ぼすのではないか──。豊島住民は、この事業者の廃棄物処理場建設に反対する署名活動を始め、県に認可拒否を陳情しました。ところが、当時の香川県知事は「反対運動は住民のエゴ、事業者いじめ」と断じ、事業者への申請許可を表明したのです。これを機に、豊島住民と県との軋轢は悪化の一途をたどります。
1977年、住民が廃棄物処理場の建設差し止め請求訴訟を提起すると、事業者は申請する事業内容を「無害物によるミミズの養殖」に変更。県がこれを許可し、住民もいったんは和解に応じます。しかし、ミミズの養殖は隠れみので、実際には廃棄物の処理後残渣物、有害物質を思わせるマークのついたドラム缶、ラガーロープ、燃えがら、廃油、汚泥、廃プラスチック、得体の知れない液体物などの廃棄物が続々と運び込まれていきました。
戦後の高度経済成長期の真っただ中にあった60~70年代は、大量生産・大量消費の時代。それに伴い、行き場のない大量の家庭ごみや産業廃棄物が、人目に付きにくいへき村や離島に不法投棄される事件が、日本各地で頻発していました。豊島では、悪徳業者への適切な行政指導が行われないまま、産業廃棄物の持ち込みが放置され続けました。島には廃棄物を野焼きする有害な黒煙が毎日のように立ち上り、ドロドロの液体が染み出す地面には猛烈な悪臭が立ちこめ、体調不良を訴える住民が続出。子供の喘息の発生率が全国平均の約10倍近くに増加しました。
転機が訪れたのは、1987年。隣県の兵庫県姫路海上保安署が、許可なく廃棄物を運搬する豊島観光の船を見つけ、廃棄物処理法違反の疑いで検挙。1990年には兵庫県警が同法違反の容疑で事業者の処分場の強制捜査に踏み切り、翌1991年1月、豊島観光の経営者らが逮捕・起訴されます。これにより、12年間に及んだ廃棄物の搬入、野焼き、埋め立てがようやく止まりました。
しかし、「ごみの島」の風評というさらなる試練が住民を襲います。島の農漁業は致命的な打撃を受け、残存する大量の廃棄物の処理と、そこに含まれる有害物質による土壌や地下水の汚染も住民の生活に重くのしかかりました。やがて住民側が香川県に対して、廃棄物の撤去と賠償を求める公害調停へと発展。豊島事件は新たな局面を迎えます。
1993年の申し立てから実に36回を重ねた調停は、不法投棄を看過した責任を認めようとしない県を相手に難航を極めましたが、中坊公平氏ら弁護団の尽力と、「美しい豊島を取り戻したい」という住民の強い意志と幾多の抗議行動が実を結び、2000年、ついに調停が成立しました。島内の廃棄物の量、実に91万トン以上。これらが完全撤去されたのは2019年。ほんの1年前のことです。

香川県豊島の産廃問題の現場。1995年の撮影。既に豊島観光は兵庫県警に摘発されたが、産廃の撤去はまだ本格的には始まっていない。出典:国土地理院ウェブサイト
監修/喜多川和典 公益財団法人 日本生産性本部 エコ・マネジメント・センター長 主席コンサルタント







