豊島事件が残した課題|真の循環型社会に向けて(3-3)
2020年12月10日
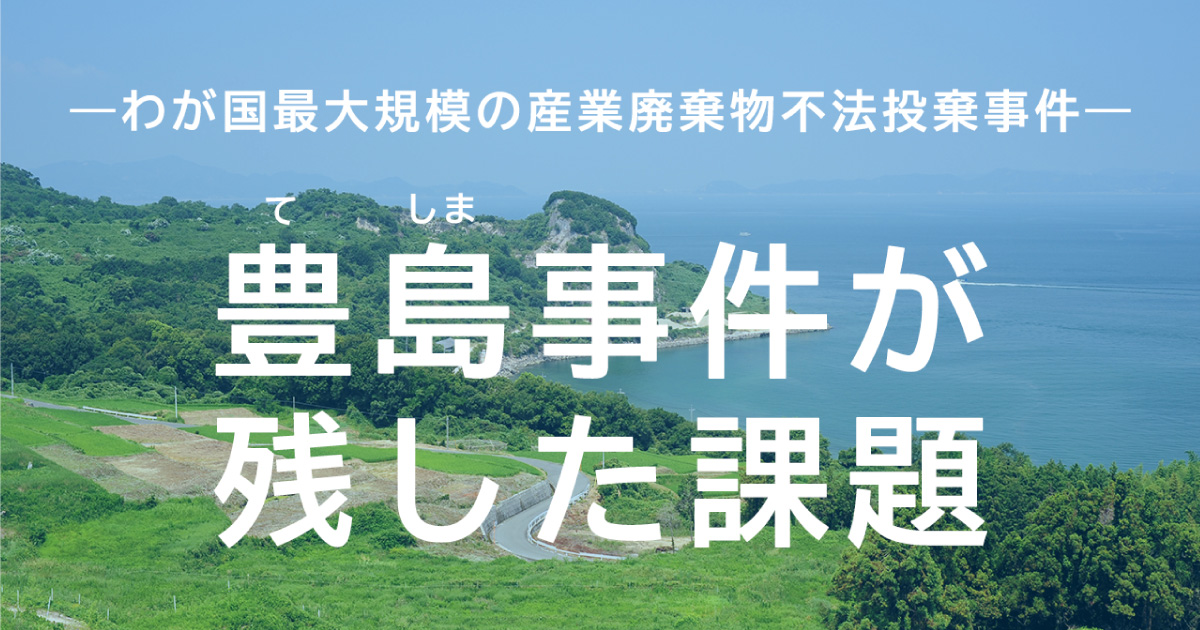
清水が湧き出る棚田や、オリーブ畑やレモン畑ののどかな風景が広がるこの小さな島は、近年、豊島美術館や瀬戸内国際芸術祭により「アートの島」として世界の注目を集めるようになりました。
目次
風光明媚な瀬戸内海に浮かぶ香川県の豊島。清水が湧き出る棚田や、オリーブ畑やレモン畑ののどかな風景が広がるこの小さな島は、近年、豊島美術館や瀬戸内国際芸術祭により「アートの島」として世界の注目を集めるようになりました。
しかし、数十年前には悪臭漂う「ごみの島」と揶揄された時代がありました。わが国最大規模の産業廃棄物不法投棄事件と、それに敢然と立ち向かった住民たちの闘いが、その後の日本の環境政策に与えたインパクトは計り知れません。
現代のプラスチックごみ問題へと続く、私たち日本人と廃棄物との闘い。そのターニングポイントとなった「豊島問題」から、この特集はスタートします。
この記事を初めから読む方はこちら。
官民一体のリサイクル対策で循環経済の市場を切り拓く
「雑品スクラップ」と「廃プラスチック」という課題に、日本社会はどのように取り組むべきでしょうか。
豊島事件等を経て、循環型社会形成推進基本法が生まれ、産業界や消費者にもリサイクルの責任が共有される社会への変化が加速しました。自動車や食品、小型家電、建設など、品目ごとにリサイクル法が誕生し、リサイクル率は飛躍的に向上しました。しかし今も、雑品スクラップや廃プラスチックは、目の前にあるあらゆる工業製品から発生しています。これに対しては、社会全体が関与する、より包括的なシステムが必要なのではないでしょうか。
世界に目を向ければ、EUでは2025年までに少なくとも1000万トンの再生プラスチックをEU域内で循環利用することを決議し、再生プラスチックのマーケットを醸成する取り組みが積極的に行われています。
日本では2020年5月に経済産業省が、あらゆる産業が循環性の高いビジネスモデルへの転換を目指す「循環経済ビジョン2020」を発表しました。その中では、サーキュラー・エコノミー(循環経済)という概念も示され、資源を節約し、地球環境への負荷を低減、気候変動対策に貢献しながら、ビジネス、そして、経済も成長させていこうという流れが生まれています。まだ端緒についたばかりですが、見方を変えれば、日本独自の循環型社会を発展させる機運が高まりつつあるといえます。
動脈産業は、資源循環しやすい商品設計や、自らが利用しやすい再生材のリサイクルシステムの開発を進めていくでしょう。静脈産業には、地域の垣根を越えた資源回収の仕組みづくりや、雑品スクラップ等の選別・再生技術の高度化、そして高品質な再生材を安定供給できる生産能力のスケール化が求められます。消費者はリサイクル回収への協力やグリーン購入などに対する意識の変革を。そして、国は雑品スクラップ等を含む、廃材のさらに円滑な資源循環を推進させるための制度の整備と運営を。官民一体の取り組みが待ったなしで求められています。
これからの資源の流れ「サーキュラー・エコノミー(循環経済)」

これからの資源の流れ サーキュラー・エコノミー(循環経済)
サーキュラー・エコノミー(循環経済)とは、従来の廃棄物処理の流れの中で活用されることなく「廃棄」されていた製品や原材料などを新たな「資源」と捉え、廃棄物を出すことなく資源を循環させる経済の仕組みのことを指します。「循環経済ビジョン2020」では、生産から廃棄までの直線的な仕組みがさまざまなレベルで循環していくよう、設計やビジネスモデルの段階から抜本的に社会経済のあり方を見直すことが示され「環境負荷を低減する手段」として注目されています。
サーキュラー・エコノミーへの歩みを加速する鍵を握るのは、動脈産業・消費社会・静脈産業、そして、それを支える行政・自治体との有機的な連携です。リバーグループは、国連サミットで採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」の達成に向けて、日本における資源循環プレーヤーとして、全てを資源にできる技を磨き、あらゆる資源が再資源化される高度循環型社会の実現を目指します。
監修/喜多川和典 公益財団法人 日本生産性本部 エコ・マネジメント・センター長 主席コンサルタント







