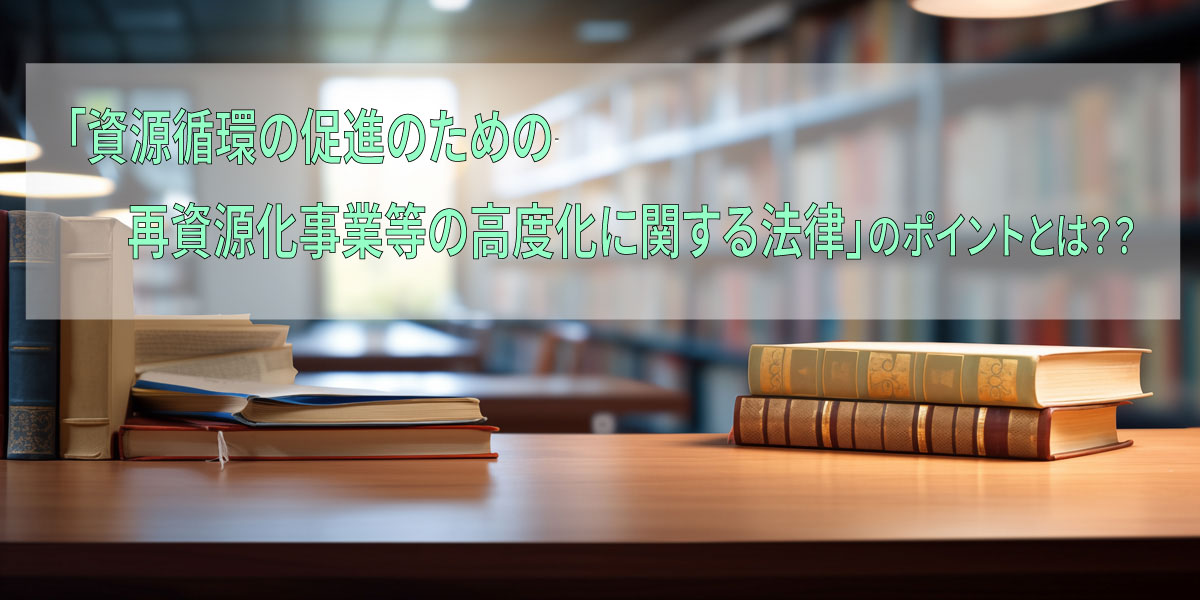生分解性プラスチックは廃プラでいいの?
2018年11月29日

海洋プラの問題でにわかに注目を集めている生分解性プラスチックですが、従来のプラスチックではありえない「肥料化」「堆肥化」「発酵」という処分方法も考えられます。そのため、廃プラスチック類ではなく他の品目、例えば、動植物性残さや紙くず、木くずの方が良いのではないか、新設してもよいのではないか、という意見もあるかもしれません。今後どうなるかはともかく、現状どのような解釈になるのかを整理しておきましょう。
目次
廃プラスチック類の定義
廃プラスチック類の定義は、法第2条では産業廃棄物の種類の一つとして「廃プラスチック類」が挙げられているだけで、それ以上の説明はありません。旧厚生省通知【昭和46年10月25日 環整第45号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」】では、
廃プラスチック類・・・合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等合成高分子系化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類を含むものであること。
と定義されています。
判断基準は「合成高分子系化合物」かどうかですが、生分解性であっても、合成された高分子の化合物には違いありませんから、廃プラスチック類と言わざるを得ません。なお、液状のものも廃プラになる、というのは意外ですが、実際には液状の合成樹脂は廃油として扱われています。
現在、肥料化は許可されていない?!
さて、現状では廃プラスチック類の処分方法として、上記のような「肥料化」等の方法は許可されていないはずです。廃プラスチック類の処分方法が法律で限定されているわけではありませんので、今後「生分解性プラスチックに限る」といった条件付きと思いますが「肥料化」等の許可が出される可能性はあります。その場合でも、普通の廃プラの混入を認めるわけには行きませんので、生分解性プラスチックの製造工程から排出される場合などの、かなり例外的なケースに限られるでしょう。
自社処理の場合は許可は不要
では、自社処理としてコンポスターに投入したり、構内の緑地や畑にすきこむとしたらどうでしょうか。「肥料化」「堆肥化」「発酵」等の処分方法であれば、産業廃棄物処理施設の設置許可は不要ですので、この点は心配ありません。さらに、自社処理をする場合は処理業の許可は不要ですので、特に規制はありません。緑地や畑にすきこむと、不法投棄とみなされるのではないかという懸念を持たれるかもしれませんが、処分方法が法律で限定されていないため、土中で確実に分解され、生活環境に問題を生じさせない処分であれば、問題ありません。
生分解性プラスチックにもさまざまな種類があるため、条件によって分解されやすさ、速度が違いますので注意しなければなりません。現時点では普及率も低いため、生分解だからと言って専用の処分施設を積極導入するのではなく、従来型の廃プラの処分方法でよいと思います。しかし、普及が進んでくると埋立処分に悪影響があるかもしれません。廃プラは分解しない前提で安定型産業廃棄物として埋立られますので、生分解性プラスチックが大量に混入し、安定型最終処分場で分解・消滅されてしまうと困ります。通常の廃プラとの混入が避けられない場合は、管理型最終処分かサーマルリサイクルが推奨されることになるかもしれません。
(リバーグループ/メジャーヴィーナス・ジャパン株式会社 シニアコンサルタント・行政書士 堀口昌澄)