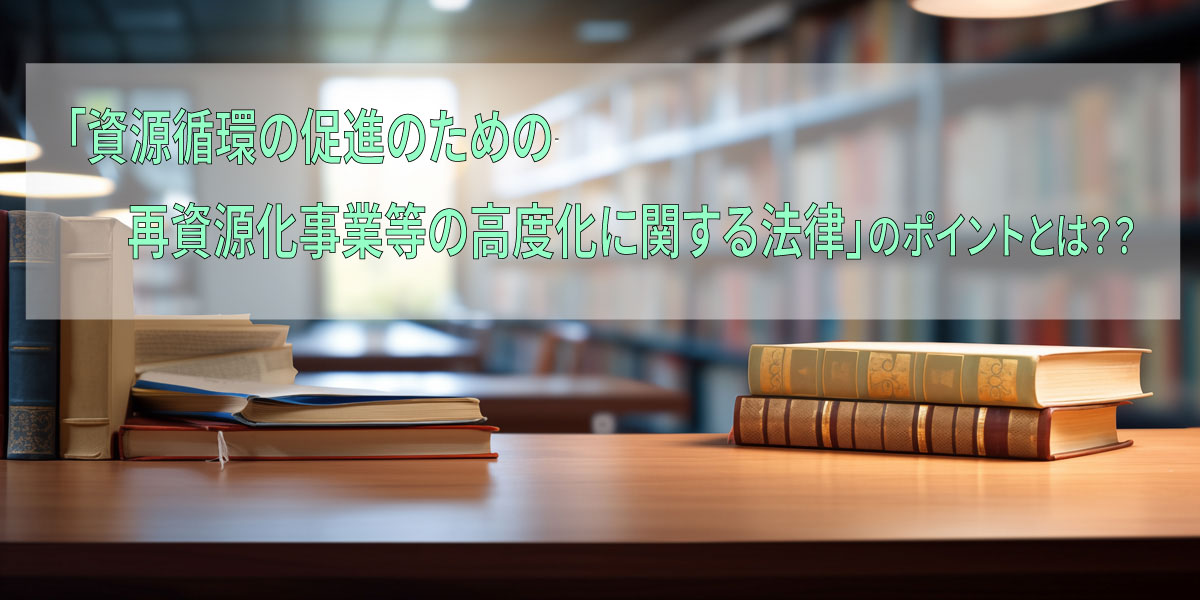契約書と許可証の「所在地」が違う?
2019年02月27日
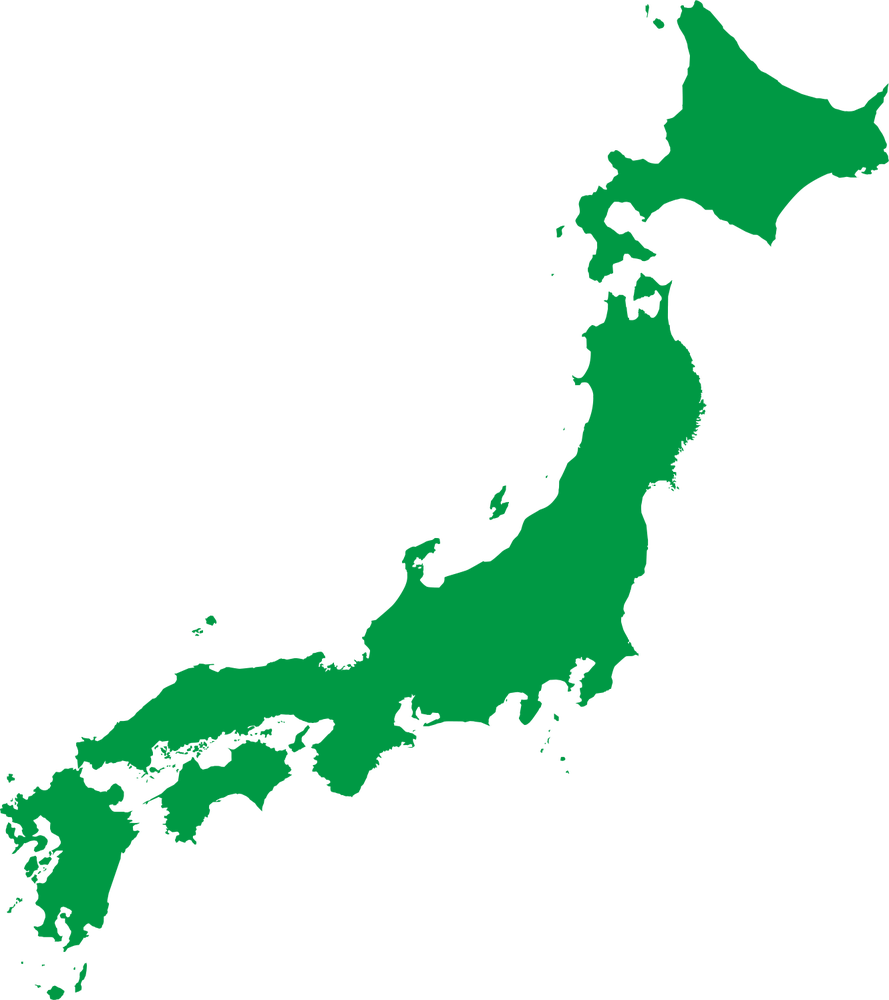
目次
許可証の内容と契約内容は整合していなければならない
処理委託契約書に記載されている「処分の場所の所在地」と、許可証に記載してある「施設の住所」が違うということで、問題となることがあります。施行令第6条の2によると、産業廃棄物の処理委託にあっては「業として行うことができる者であって~中略~その事業の範囲に含まれるものに委託すること」ということです。したがって原則、許可証の内容と契約内容は整合していなければなりません。
ではここで、関係する条文を確認してみましょう。
「産業廃棄物処分業許可証の記載事項」様式第9号
・事業の用に供するすべての施設(施設ごとに種類、設置場所、設置年月日、処理能力、許可年月日及び許可番号(産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合に限る。)を記載すること。)
「委託契約書の記載事項」 施行令第6条の2第1項第4号ハ
・産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
要約すると、許可証については「事業の用に供するすべての施設の設置場所」が記載され、契約書については「処分の場所の所在地」を記載しなければなりません。つまり「施設の設置場所」と「処分の場所」を記載するのですが、これらが概念として同一なのかどうかがポイントです。
契約書の「処分の場所の所在地」の記載
許可証には、その都道府県内の複数の場所に施設があれば、それぞれの場所が記載されます。例えばA県の甲市に破砕機αとβ、乙市に焼却施設θ、丙市に埋立施設δがある場合、A県の許可証にはこれらのα~δの4つの「施設の設置場所」が記載されます。では、契約内容が破砕処分であって、破砕機αとβのどちらも使える契約にする場合は契約書の「処分の場所の所在地」にはどう記載すべきでしょうか。
そもそも「施設の設置場所」は許可証により明らかですが、「処分の場所」という言葉は定義されていません。イメージとしては「処分の場所」の内部に施設が設置されていると考えるのが自然だと思います。したがって、例えば処分をする場所が支店として登記されている場合は、その所在地を記載すればよいでしょう。登記していなくても、紙マニフェストをはじめ書類のやり取りをすることを考えると、郵便物の宛先、入荷の受付をしている事務所の住所などを記載するのが合理的です。
極論すると、許可証・契約書・マニフェストは、それぞれ仕組みとしては独立しています。委託基準を軸として、許可内容及び引き渡しの実態(マニフェスト)との間に齟齬があると違反になりかねませんが、類似の項目の表現が少し違っていても、そのことだけをもって違反には直結しません。同一でなければならないのであれば、契約書の記載事項の「許可の事業の範囲」のように条文に明記されているはずですので、杓子定規に「一字一句に至るまで同一でなければならない」と考える必要はないと思います。
(リバーグループ/メジャーヴィーナス・ジャパン株式会社 シニアコンサルタント・行政書士 堀口昌澄)