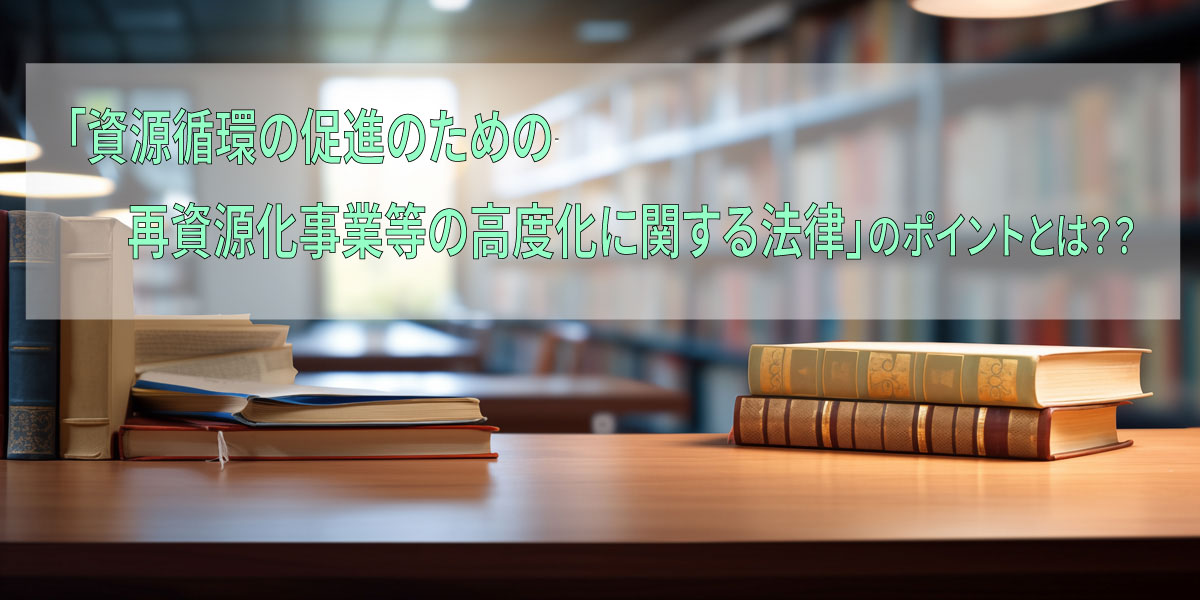話題の紙ストロー、喫茶店から捨てると一般廃棄物になる?
2019年04月01日

目次
最近、プラスチックストローの代わりに紙のストローが話題ですね。「紙のストローって、大丈夫なの?」と思われた方は決して少なくないはずです。しかし一口に紙と言っても、様々なものがあります。
コピー用紙のようなシンプルなものから、雑誌や写真印刷用の表面に塗料を塗布して、美しい印刷性能を追求した紙もあります。防水性を持たせるためにプラスチックやアルミなどがコーティングされていることもあります。建材として使われる壁紙や化粧板に貼る化粧紙などもプラスチックが張り合わされています。
さらに、海洋プラスチック問題が取りざたされる中、代替品として紙製の資材が提案されることがあります。プラスチックの代替ですので、純粋な紙では機能的に不十分なこともあるため、紙に塗料を塗布したり、プラスチックを張り付けたりしていることがあります。それでは海洋プラスチック問題の解決にはならないとして、生分解する素材を用いて加工するなど、新しい技術が開発されています。
ここではこれらの紙を「加工紙」と呼ぶこととします。
該当する業種以外から出された紙くずは一般廃棄物…だが一体となった廃棄物は?
さて、廃プラスチック類は排出される業種にかかわらず産業廃棄物になります。一方、紙くずは「建設業、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業」から排出されると産業廃棄物になります。それ以外の業種、例えば喫茶店やファーストフード店から排出されると一般廃棄物となります。
プラスチックと紙が複合している加工紙は、上記業種から排出されると「産業廃棄物である廃プラスチック類と紙くずが一体となった廃棄物」となります。
それ以外の業種から排出されると「産業廃棄物の廃プラスチック類と、一般廃棄物の紙くずが一体となった廃棄物」となります。
同様のことは、
- 合成繊維と天然繊維の混紡品
- プラスチック/金属と木の複合した製品
- プラスチック容器に食品が入った物
でも考えられます。
総体産廃、総体一廃。問題になるのは、〇〇%の割合
産業廃棄物と一般廃棄物が一体になっている場合、産業廃棄物と一般廃棄物の両方の許可を持つ業者に委託しなければならず、処理委託可能な業者を探すことが難しいことがほとんどです。
そのためもあって、一般廃棄物部分は無視しても支障がない量しか含んでいない場合は、「総体産廃」又は「総体一廃」として全体を産業廃棄物又は一般廃棄物として扱っていることが多いのが実態です。
その他、多くの都道府県で、公式、非公式な形で「〇〇%が産業廃棄物であれば産業廃棄物とみなしてよい」という解釈、指導をしています。
ここで問題になるのは、〇〇%の割合です。個別の組み合わせについての通知や、都道府県ごとの個別解釈はあっても、一般に適用できる根拠はありません。それではどうしたらよいのでしょうか。
一つには、都道府県に相談するという方法があります。ただし、グレーゾーンであればあるほど、都道府県によって、それどころか担当者によっても解釈が違ってきます。これでは、アリバイ作りにはなっても、解釈の信頼性が低いですし、場当たり的な対応でしかなく、会社としての管理、ルール化が困難です。何といっても都道府県によって解釈が違うことは少なくなく、越境委託する場合に困ります。
最終的には基本に立ち戻って、廃棄物処理法の目的である「生活環境の保全」を踏まえて、企業コンプライアンスが求める法令、社会規範、社会通念、社会的要請に応えられる解釈をするしかありません。
言い換えると、”第三者に説明して納得してもらえるか”がポイントでしょうか。
その木や紙は、無視してよいレベルしか混ざっていないか。処理施設、処理技術として問題はないか。逆に、見た目や触感に反して紙がほとんどで、プラスチック部分は微量ではないか。その解釈は、廃棄物処理法の目的である「適正処理」にかなっているか。行政、警察、マスコミに説明して、誰も問題視しないか。正解はありませんが、判断基準としては最終的にここに来るしかないのだと思います。
(リバーグループ/メジャーヴィーナス・ジャパン株式会社 シニアコンサルタント・行政書士 堀口昌澄)