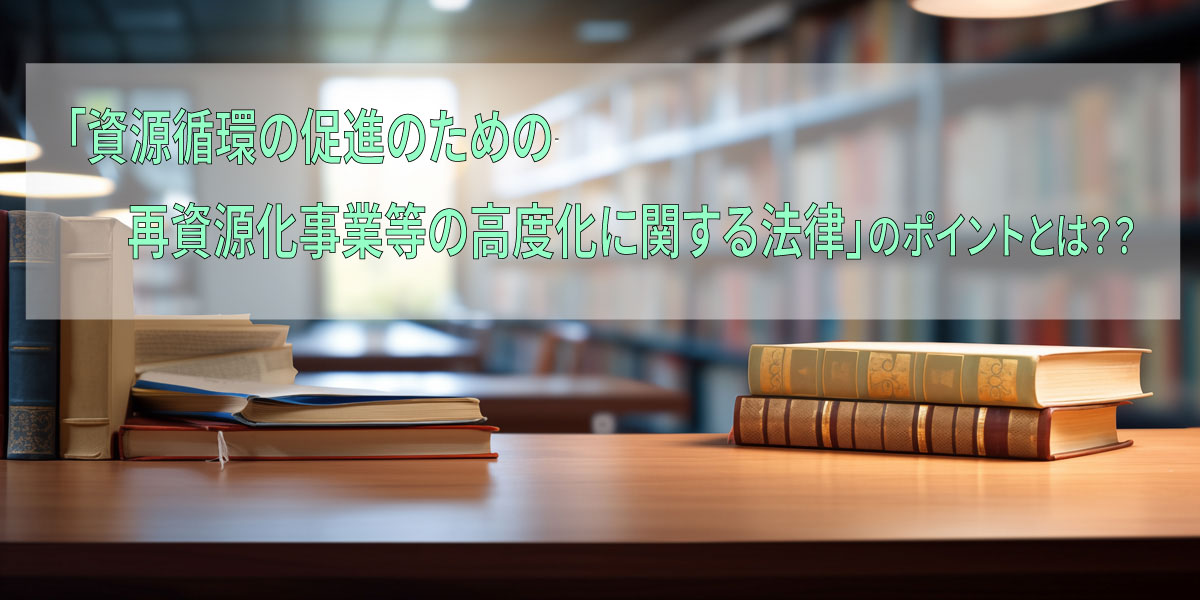大気汚染防止法(アスベスト関係)改正の注意点|2021年4月1日
2021年01月12日

この記事のポイント
・建築物の解体工事ピークに向けて2021年4月1日より、大気汚染防止法が改正される。
・これまではアスベスト建材の調査方法が決まっておらず、事後のチェックも難しかった。
・今後は、すべての工事について調査、報告し、書類の保管が義務付けられる。
目次
大気汚染防止法は、文字通り大気の汚染を防止する法律ですので、気体はもちろんのこと、大気中を浮遊する粉じんも規制対象としています。有害な粉塵の筆頭に挙げられるアスベストも規制されており、発生の可能性が高い建築解体時のアスベスト建材からの飛散は以前より規制されてきました。
国土交通省によると建築物の解体工事は2028年ごろまで年々増加する見込みで、それに向けて2021年4月1日より、大気汚染防止法が改正され、規制が強化されます。
ここではアスベスト規制の大枠と注意すべきポイントをまとめます。ご一読いただき、関係がありそうだと思われたら、環境省のウェブサイトで詳細をご確認ください。
事前調査の強化
元請業者は解体工事を始める前に、石綿含有建材があるかどうかを調査し、その結果を発注者に説明する義務があります。しかし、調査方法や調査者の資格要件がなく、結果の保存義務もないため、石綿含有建材の見落としが発生していた可能性が指摘されていました。
そこで、調査方法を定め、さらに「石綿含有建材調査者」が調査をすることになりました。この「石綿含有建材調査者」は、国の外郭団体が運営していた任意資格を法定化するもので、既に2000名弱の資格者はいます。しかし、これでは足りないため、2023年10月までは資格者による調査を猶予し、それまでに30~40万人程度育成する予定だそうです。
調査結果は都道府県へ電子報告し、発注者へ説明、記録の保存も義務化されますので、これまでよりしっかりとした事前調査が行われることでしょう。なお、これに違反すると30万円以下の罰金の対象となります。
発注者による届出
事前調査の結果、レベル1,2(飛散性アスベスト)がある場合は、発注者が工事開始14日前までに都道府県に届出をしなければなりません。解体工事をする元請けではなく、コスト負担者である発注者が届け出をするところがポイントです。相応なコストがかかることを認識してもらい、不当な値下げを強要しないようにすることが目的でしょう。もし届出の内容に環境保全上の問題があると、計画変更命令が出されます。発注者は、届出を怠ると3か月以下の懲役30万円以下の罰金の対象に、計画変更命令に違反すると1年以下の懲役100万円以下の罰金の対象となります。
元請による作業
元請は作業基準に沿って石綿含有建材を除去し、作業記録を作成、発注者へ報告しなければなりません。レベル1,2は当然のこと、これまで規制がなく、本改正でも上記の届出の対象外であるレベル3(非飛散性)も、この作業基準等の対象となります。作業基準とは、湿潤化や養生、負圧化などの措置をすることを指し、適切に行わないと3か月以下の懲役、30万円以下の罰金の対象となります。
これまでは調査方法は決まっておらず、書類の保管義務がほとんどなかったため、完了後の工事に石綿含有建材が含まれていたのかどうか調べようもなく、事後的なチェックを入れることが難しかったようです。今後は、すべての工事について調査、報告し、書類の保管が義務付けられますので、石綿含有建材の有無にかかわらず罰則をかけることが可能となります。
今後は石綿含有建材の有無はこれまで以上に厳しく調査され、適切な処理が進むことでしょう。また、欧米の規制は今回の改正のさらに先を行っていると言われており、さらなる規制強化が行われる可能性があります。所有する建築物の資産除去債務にも関係する場合もありますので、必要に応じて詳細確認をしてください。
(リバーグループ/メジャーヴィーナス・ジャパン株式会社 シニアコンサルタント・行政書士 堀口昌澄)
アスベスト処分のお問い合わせ
リバー(株)では、アスベストの調査関連の調査から処理、報告までの一貫したサポートが可能です。
アスベストの処分でお困りの方は、リバー(株)にお問い合わせください。
リバーグループでは様々な廃棄物の運搬~処分まで、トータルサポートさせていただいております。
お急ぎの場合は、お電話でのご案内も可能です。
TEL:03-6365-1200(代)
(受付時間:平日10:00~18:00)