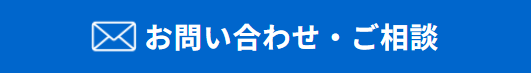家電リサイクル法とは? 正しい処分方法と抱える課題・今後の展望
2025年11月20日
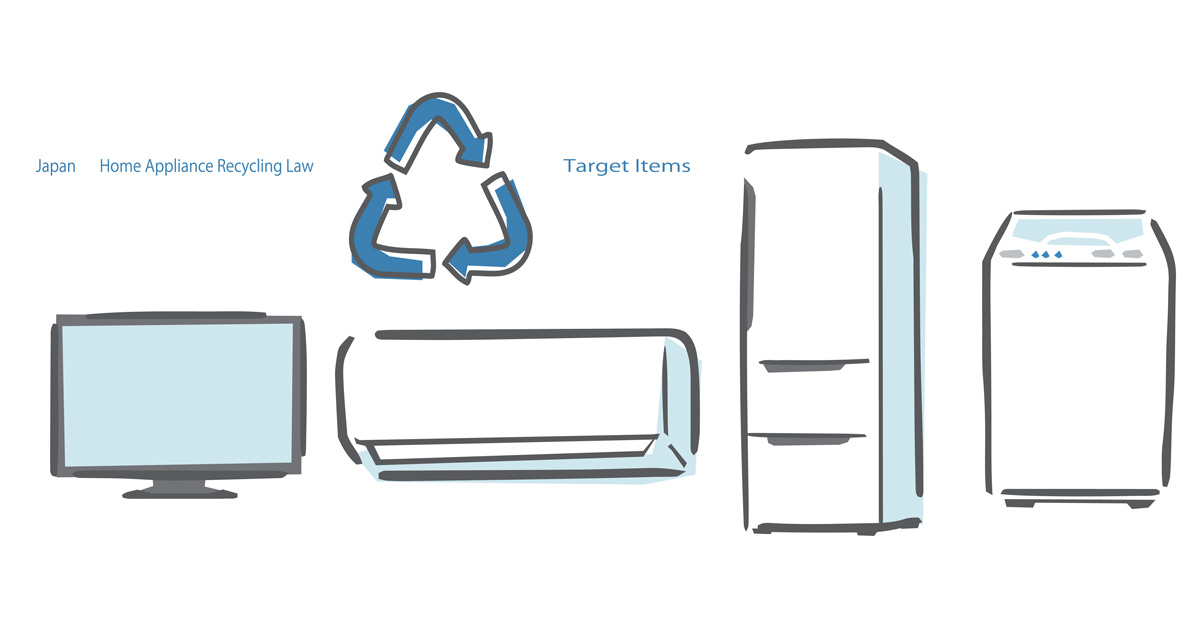
家電製品は私たちの生活に欠かせないものですが、使用後の処分方法を誤ると環境汚染や再利用できる資源を無駄にしてしまう恐れがあります。こうした課題に対応するため制定されたのが「家電リサイクル法」です。本記事では、同法の仕組みや対象製品、処分の流れを整理し、現状の課題や今後の展望までをわかりやすく解説します。
目次
家電リサイクル法の基礎知識
家電製品の適正な処分とリサイクルを推進するために制定された家電リサイクル法の目的・概要、対象品目、関係者の役割を解説します。
家電リサイクル法の目的と概要
家電リサイクル法(正式名称:特定家庭用機器再商品化法)は、廃棄物の減量と資源の有効利用を通じて、適正処理と循環型社会の実現を目指し、1998年6月に制定され、2001年4月から本格施行された法律です。
同法制定以前、一般家庭から排出される廃家電製品の多くは、破砕処理後に鉄など一部の資源が回収されていましたが、残りの多くはそのまま埋められていました。しかし廃家電には鉄、アルミ、ガラスなどの有用な資源が多く含まれており、最終処分場の残余容量がひっ迫する中で、廃棄物の減量化とリサイクル促進が喫緊の課題となっていました。
リサイクル対象となる家電4品目とは?
対象となるのは家庭用エアコン、テレビ(ブラウン管・液晶・有機EL・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目です。
これらの家電4品目が選ばれた理由は、大型で処理が困難であること、有用な資源が豊富に含まれていること、フロン類など環境に有害な物質を含む製品があることなどです。家庭用として製造・販売された上記4品目を事業所で使用し、廃棄する場合も対象となりますが、業務用として製造・販売されたものを家庭で使用していた場合は対象外となります。
また、製造業者等には、定められた再商品化基準(再商品化率)を達成する義務があります。具体的な基準は以下の通りです。
|
製品カテゴリ |
再商品化基準(再商品化率) |
|
エアコン |
80% |
|
ブラウン管式テレビ |
55% |
|
液晶・有機EL・プラズマ式テレビ |
74% |
|
冷蔵庫・冷凍庫 |
70% |
|
洗濯機・衣類乾燥機 |
82% |
出典:経済産業省「家電リサイクル法[担当者向けガイドブック2024]」https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/shiryousyu/guidebook2024.pdf
また、フロン類を使用している製品については、適切な回収処理が求められます。
家電リサイクル法における関係者の役割
家電リサイクル法では、消費者(排出者)、小売業者、製造業者等それぞれに明確な役割が定められています。
- 排出者(消費者)
不要となった家電4品目(エアコン、テレビ(ブラウン管式・液晶・プラズマ・有機EL)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)を廃棄するとき、収集運搬料金とリサイクル料金を負担した上で適切な方法で処分する責任があります。
引き渡しは、家電を購入した小売業者に依頼する方法と、指定引取場所へ自ら持ち込む方法のいずれかを選べます。
- 小売業者(家電製品を販売したお店)
排出者(消費者)から、過去に自ら販売した家電4品目または買い替え時に引き取りを求められた場合は、廃家電の引き取り義務があります。
引き取った廃家電は製造業者等が指定した引取場所に運び、適正に引き渡す責任を負います。
さらに、収集運搬料金・リサイクル料金の店頭掲示や説明、家電リサイクル券(管理票)の交付・管理・保存なども義務付けられています。
- 製造業者等(家電製品のメーカー・輸入業者など)
小売業者から引き取った家電製品のリサイクル(再商品化)を行う義務があり、法定のリサイクル率達成やフロン類の適切な回収・処理が求められています。
家電リサイクルの正しい処分方法と実務の流れ
家電4品目を適正に処分するためには、正しい手順と制度を理解することが重要です。ここでは、実際の処分方法や流れについて解説します。
家電リサイクル券とは? 取得方法と使い方
家電リサイクル券は、家電リサイクル券は、家電4品目を適正に処分する際に必要な書類であり、リサイクル料金を支払ったことを証明するものです。取得方法には、処分方法に応じて次の2種類があります。
①「料金販売店回収方式」の家電リサイクル券(通称「グリーン券」)
廃家電を小売業者に引き渡した場合に、小売業者から発行される家電リサイクル券です。この場合、排出者はリサイクル料金を小売業者に支払います。
②「料金郵便局振込方式」の家電リサイクル券(通称「郵便局券」)
排出者が廃家電を直接、指定引取場所に持ち込む場合などに使用する家電リサイクル券です。この場合、排出者は事前に郵便局でこの家電リサイクル券を購入し、リサイクル料金を支払います。その後、指定引取場所に家電と一緒に持ち込みます。
家電リサイクル券は、5枚複写式になっています。
販売店での回収と指定引取場所の利用方法
家電の処分方法は、買い替えの場合は新製品を購入する店舗に、処分のみの場合は処分したい家電を購入した店舗に引き取りを依頼するのが基本です。販売店での回収では、小売業者は廃棄物と家電リサイクル券への記載内容を照合し、「⑤現品貼付用」(家電リサイクル券の一部(5枚目))を廃棄物の本体右側面上部(エアコン、冷蔵庫、洗濯機、ブラウン管式テレビ)または本体背面左上部(液晶・プラズマ式テレビ)に貼付けて指定引取場所へ運搬します。
購入店が不明な場合などは、市区町村の案内する方法や指定引取場所への直接持ち込みが可能です。指定引取場所としては、例えばリバーグループの埼玉県加須市の加須事業所、千葉県千葉市の千葉事業所、千葉県市原市の市原事業所、栃木県大田原市の那須事業所があります。直接持ち込む場合は収集運搬料金がかかりませんが、事前に郵便局でリサイクル券を購入する必要があります。
リサイクル料金・収集運搬料金の目安と留意点
リサイクル料金は製造業者等ごとに設定されており、主にエアコン:990円または2,000円、テレビ(液晶・有機EL・プラズマ式 16V型以上):2,970~3,700円、冷蔵庫・冷凍庫(170L以下):3,740~5,200円、洗濯機・衣類乾燥機:2,530~3,300円程度が目安となっています(料金は2025年10月時点のものです)。
この料金に加えて、家電を販売店からリサイクル工場まで運搬するための収集運搬料金が発生します。この料金は、店頭掲示などで公表されていますが、販売店ごとに自由に設定できるため、事前に料金を確認しておくことが重要です。不当に高額な料金を設定している業者は、行政指導、行政処分および刑事告発の対象となります。消費者としても、正規のルートでの処分を選択し、適正な料金で安全な家電リサイクルを実現することが重要です。
家電リサイクル法の課題と社会的影響
家電リサイクル法は一定の成果を挙げているものの、実際の運用においてはさまざまな課題が浮き彫りになっています。ここでは、特に深刻な問題となっている不法投棄や、処分が困難なケース、そして今後の改善に向けた展望について解説します。
無許可回収業者による環境汚染と健康被害
無許可の廃棄物回収業者による不適正な処理は、深刻な環境問題を引き起こす懸念があります。これらの業者は廃棄物処理法に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可や市区町村の委託などを受けていないにもかかわらず、「無料回収」を謳って家電製品を回収しています。
無許可業者によって回収された家電は、フロン回収や有害物質の飛散・流出防止といった適切な措置が講じられないまま分解・破壊されることが多く、環境汚染や健康被害を引き起こす可能性があります。さらに、フロンガスやコンプレッサー内のオイルは引火性が高いため、破損や不適切な切断によって漏れ出すと発火する危険があり、不適正処理が火災につながるリスクも指摘されています。
家庭の廃棄物を回収するには市区町村の「一般廃棄物処理業許可」や委託が必要であり、これらの許可を持たない業者への処分依頼は避けるべきです。産業廃棄物処理業許可や古物商許可しか持たない業者は、家庭ごみを回収できません。
処分が困難なケースと高齢者・地域の課題
家電リサイクル法では小売業者の引取義務が限定されており、「小売業者の引取義務の対象とならない廃家電」(義務外品)の存在が大きな課題となっています。具体的には、過去に購入した店舗が廃業している場合や購入店が不明な場合が該当します。
このような義務外品は市区町村が処理することになりますが、多くの自治体では回収体制が十分ではありません。特に人口10万人以下の市町村や過疎地域では、職員数の制約もあり体制構築が困難な状況にあります。高齢者にとっては、重い家電を指定引取場所まで運搬することが物理的に困難であり、適正な処分ルートから外れる原因となっています。このような状況が、結果的に違法な回収業者の利用や不法投棄につながるリスクを高めています。
今後の課題と家電リサイクル制度の改善に向けて
家電リサイクル制度の改善に向けて、複数の重要な取り組みが検討されています。これまでには、ユニバーサルサービス化の必要性が議論されてきた経緯があり、現在のような小売業者の限定的な引取義務ではなく、より包括的な回収体制の構築が模索されています。
経済産業省が2022年6月に策定した「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」では、2030年度までに4品目合計の回収率70.9%(2019年度実績は64.1%)という新たな目標が設定され、「義務外品の回収体制構築や不法投棄の取り組みへの支援の継続・充実」が明記されました。技術面では家電リサイクル券のデジタル化も検討されており、制度関係者の利便性向上とトレーサビリティの精度向上を目指した改善が進められています。
消費者・事業者が知っておくべき注意点と取り組み方
家電リサイクル法の適正な運用には、消費者と事業者の双方が制度を正しく理解し、責任を持って行動することが不可欠です。ここでは、環境保全と資源循環の実現に向けた具体的な取り組み方について解説します。
正しいリサイクルのための消費者行動
消費者が家電4品目を処分する際は、無許可業者を避け、必ず正規のリサイクルルートを利用することが重要です。街中を大音量で巡回する車やチラシで『無料回収』を謳う業者の中には、自治体の許可を得ていない違法業者が含まれており、これらに引き渡された廃家電は不法投棄や不適正処理により環境汚染の原因となります。
正しくリサイクルするためには、以下の2点が重要です。
- 購入した店舗へ引取りを依頼する
- お住まいの自治体が案内する指定引取場所を利用する
いずれの場合も家電リサイクル券を使用することが必要です。こうした正規ルートの利用が、資源循環と環境保全につながります。
事業者の対応と法律遵守のポイント
小売業者には家電リサイクル法上の厳格な義務が課せられています。具体的には、自社が過去に販売した製品や買い替え時の同種製品について引取義務があり、引き取った廃家電は必ず製造業者等の指定引取場所に引き渡す義務があります。
この義務を怠ると経済産業大臣・環境大臣による勧告、措置命令の対象となり、法人および代表者に対して50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。違法な不用品回収業者やスクラップ業者への引き渡しは引渡義務違反となります。
適正な対応を取るためには、以下の体制整備を進める必要があります。
- 収集運搬料金の事前公表
- リサイクル券の適正な交付・管理
- 委託先業者の適切な選定と監督
- 適正な引取・引渡体制の構築
環境保全につながる家電リサイクルの意義
家電リサイクル制度により、令和5年(2023)度の再商品化率はエアコン93%、液晶・プラズマテレビ85%、冷蔵庫・冷凍庫80%、洗濯機・衣類乾燥機92%と高水準を維持しており、鉄や銅などの貴重な資源が効率的に回収・再利用されています。適正なリサイクルにより新たな資源採掘の必要性が減り、フロンガスや鉛などの有害物質の環境放出を防ぎ、温室効果ガスの排出削減にも寄与しています。
出典:「令和5年度における家電リサイクル法に基づくリサイクルの実施状況等について」|経済産業省、環境省
しかし、依然として年間約36,000台(2023年度)の不法投棄が発生しており、消費者・事業者双方の意識改革が求められています。正しいリサイクルルートに乗せることで再資源化が一層進展し、循環型社会の実現と環境負荷軽減に大きく貢献できるため、すべての関係者が制度の重要性を理解し、適切な行動を取ることが不可欠です。
リバーグループは、家電リサイクル法が施行された2001年以前から、大手家電メーカーとリサイクル技術に関する共同研究を行い、リサイクル法の成立にも貢献してきました。
法律の施行後も、ブラウン管から薄型テレビへの移行や、ドラム式洗濯機への移行など時代とともに進化する家電に対応しリサイクル技術を高めてきた実績から、現在も大手メーカーより処理を受託しています。
▼家電リサイクルの流れ