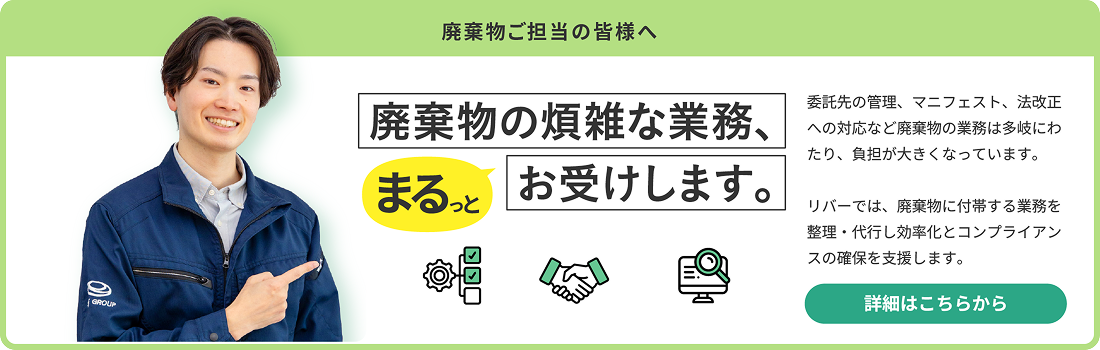なぜ今、サーキュラーエコノミーなのか? 循環型社会に向けた最新動向と実例
2025年09月22日

現代社会は、大量生産・大量消費・大量廃棄型の「リニアエコノミー」(直線型経済)が限界を迎え、地球規模の資源枯渇や環境問題が深刻化しています。こうした状況を受けて、世界的に注目されているのが、持続可能な未来を目指す「サーキュラーエコノミー」(循環型経済)です。いま私たちに求められているのは、資源を無駄にせず循環させる、新しい経済モデルへの転換です。
目次
サーキュラーエコノミーとは何か
地球の資源には限りがあり、従来の「作って、使って、捨てる」という一方通行の経済モデルは限界を迎えています。そこで今、注目されているのが「サーキュラーエコノミー」です。ここでは、その基本概念と、なぜ今、注目されているのかを解説します。
サーキュラーエコノミーの基本概念
サーキュラーエコノミー(CE:Circular Economy)は、従来のリニアエコノミーとは一線を画す、持続可能な経済システムです。リニアエコノミーが「採掘→製造→使用→廃棄」という一方通行で資源を使い捨てにするのに対し、サーキュラーエコノミーは、製品や資源をできる限り長く活用し、廃棄物の発生を最小限に抑えることを目指します。これは、リニアエコノミーの経済システムから脱却し、資源を循環させることで新たな価値を生み出す考え方といえます。
サーキュラーエコノミーは、これまで推進されてきた「3R」(Reduce:削減、Reuse:再利用、Recycle:再資源化)をさらに進化させた概念です。単に廃棄物を減らすだけでなく、製品設計の段階から資源効率性を考慮し、修理や再製造、アップサイクルといった多様なアプローチを通じて、資源が経済システムの中で何度も利用されるよう設計します。これにより、資源の枯渇や環境負荷の増大といった地球規模の課題に対応し、経済活動と環境保護を両立させることが可能になります。
なぜサーキュラーエコノミーが注目されているのか
サーキュラーエコノミーが注目されているのは、気候変動や海洋プラスチックごみなど環境問題の深刻化に加え、大量生産・大量消費・大量廃棄を前提とした従来のリニアエコノミーの限界が明らかになっているためです。さらに、国連のSDGsやEUの「循環型経済パッケージ」など、国際的な政策が打ち出され、持続可能な社会への転換がグローバルな潮流となっています。
こうした背景を受けて、製品やサービスの価値を長く保ち、廃棄物を最小限に抑えるサーキュラーエコノミーへの移行は喫緊の課題です。それは単なる環境規制ではなく、経済システムを根本から変革し、新たなビジネスチャンスや価値を創出する動きとして、企業や社会全体から注目を集めています。
サーキュラーエコノミーの仕組みと構成要素
サーキュラーエコノミーは、資源を使い捨てにせず循環させ、廃棄を最小化しながら新たな価値を生み出す仕組みです。実現するには、設計・消費・回収・再資源化をつなぐ多層的なサイクルと、それを支える技術革新が欠かせません。
サーキュラーエコノミーの構成要素と価値創造
サーキュラーエコノミーの実現には、従来の直線的な経済モデルから脱却し、資源を最大限に活用する仕組みが必要です。その中核をなしているのが、製品設計の工夫と素材の循環(デザイン・ストック思考)です。製品の環境負荷の多くは設計段階で決まるため、長寿命化や分解・リサイクルしやすい設計が重要となります。使用済みの製品を廃棄するのではなく、資源のストックとして捉え、循環させることで価値の維持を図ります。
また、従来の3Rをさらに発展させた取り組みも広がっています。例えば、廃材をまったく新しい製品へ生まれ変わらせる「アップサイクル」や、製品を所有せず必要なときだけ利用するサブスクリプション型の「サービス化」です。こうした仕組みを組み合わせることで、廃棄物を減らしながら資源を循環させ、新しい経済的な価値を生み出すことが可能になります。
サーキュラーエコノミーを支える技術とイノベーション
サーキュラーエコノミーの拡大には、デジタル技術の活用が欠かせません。しかし、現状ではその取り組みはまだ広く浸透しているとは言いがたい状況です。一方で、一部のリサイクル現場ではAIやロボティクスを活用し、廃棄物を素材ごとに自動で選別するなどの取り組みが始まっています。
こうした動きはリサイクルの現場にも広がりつつあります。リバー壬生事業所では、選別ラインに自動クレーンを導入し、シュレッダーダストの投入工程を担わせています。このクレーンは投入量を自動で検知し、あらかじめ設定された位置へと運び入れる仕組みで、工程の自動化と省力化を積極的に推進しています。
また、製品の素材情報や修理履歴を記録する「デジタルパスポート」は、部品ごとの再利用やリサイクルを容易にし、企業間での資源循環を促進する構想であり、現在、欧州を中心に実用化に向けた取り組みが進められています。加えてIoTやブロックチェーン技術を組み合わせれば、資源の流れを可視化し、信頼性の高い循環システムを構築できます。
これらのイノベーションは、資源循環を効率化するだけでなく、環境価値と経済価値を両立させる新しい産業モデルを形成する原動力となっています。
プラスチック問題と循環型社会への政策転換
深刻化するプラスチックごみ問題は、海洋環境や生態系への影響を及ぼしています。この課題に対応するため、日本を含む各国では循環型社会への政策転換が加速しています。
なお、プラスチックごみ問題の現状や循環型社会への移行については、ecoo online の記事「プラスチックごみ問題とは? 現状と循環型社会への道のり」でも詳しく解説されています。あわせてお読みになると、より理解が深まるでしょう。
海洋プラスチックごみ問題の現状と影響
海洋プラスチックごみ問題は世界的な課題です。現在、世界の海には膨大な量のプラスチックごみが存在し、毎年800万トンが新たに流入していると推定されています。特に問題視されるのが、紫外線や波で劣化した5mm以下の「マイクロプラスチック」の拡散です。
マイクロプラスチックは、有害物質を吸着・濃縮し、海洋生物が誤って摂取することで生態系全体に悪影響を及ぼします。食物連鎖を通じて人体の健康への懸念も高まっています。この深刻な状況に対し、国際的な問題意識が急速に高まり、G20や国連を中心に具体的な対策が進められています。2019年のG20大阪サミットでは、「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」が採択され、2050年までに海洋プラスチックごみによる新たな汚染をゼロにするという国際目標が掲げられました。国連でもSDGs目標14「海の豊かさを守ろう」として対応が求められています。
プラスチック資源循環促進法による今後のプラスチックリサイクルへの期待
日本では、2019年に策定された「プラスチック資源循環戦略」に基づき、3R+Renewable(再生可能資源の活用)を軸とした政策が推進されています。同戦略では、2030年までにワンウェイプラスチックの排出を累積25%抑制、容器包装の6割をリユース・リサイクル、2035年までに使用済プラスチックを100%リユース・リサイクルなどにより有効利用するといった、具体的な数値目標を掲げており、自治体や事業者の取り組みが強化されています。企業の先進的な事例としては、製品設計段階からのリサイクル性向上や、ケミカルリサイクルなどの技術開発が進められていますが、再生材の安定供給やリサイクルインフラの整備など、制度面・実務面での課題も多く残されています。
サーキュラーエコノミーへの移行をさらに加速させる手段としては、欧州を中心に導入およびその検討が進められているバージンプラスチック(新品のプラスチック)への課税もあります。本課税の導入により、再生材のコスト競争力を高め、再生材の需要を喚起する効果が期待されていますが、日本では現状、プラスチックへの課税の議論は活発化していません。
社会におけるサーキュラーエコノミーの実践事例
サーキュラーエコノミーの推進には、地域社会による具体的な実践が欠かせません。ここでは、市民レベルでの先進的な取り組み事例を紹介します。
学校・地域・NPOによる市民レベルの取り組み
サーキュラーエコノミーの推進には、市民一人ひとりの消費行動の変化が不可欠です。近年では「エシカル消費」や「サステナブル消費」といった考え方が広がり、環境や社会に配慮した商品選択や、マイボトル・マイバッグの利用、地域資源の循環活用などが日常的に実践されるようになっています。
こうした動きを支えるため、学校では環境教育やリサイクル活動、地域では資源の分別・再利用、NPOによるフードロス削減やエシカル商品の普及など、多様な取り組みが展開されています。例えば、以下のような例が挙げられます。
- 小学校と連携し、プラスチック鉢を筆の持ち手にアップサイクルしている企業
- 資源ごみの分別義務化などの施策により、「ごみ半減プラン」を実施していた京都市
- 規格外野菜の加工事業などで、フードロス削減問題に取り組んでいるNPO
特に、地域や学校、NPOが連携し、住民参加型の資源循環システムを構築することは、持続可能な社会の実現に向けて重要な役割を果たします。今後は、こうした草の根の活動を行政や企業が支援し、社会全体で循環型のライフスタイルを定着させていくことが期待されます。
まとめ:サーキュラーエコノミーの未来展望
サーキュラーエコノミーは、持続可能な社会の実現に向け、今や世界的な主流となりつつあります。欧州などが主導するこの流れに対し、日本でも官民一体の取り組みが加速していますが、資源循環を一層深化させるための具体的な技術開発や社会実装が今後の大きな課題です。
この変革を推進するのは、企業や行政だけではありません。私たちが日々行う消費行動や、環境に配慮した製品を選ぶといった一つひとつの選択が、社会全体を変える原動力となります。
サーキュラーエコノミーは、私たちの暮らしと地球の未来をより良くするための、新たな経済モデルとして大きな期待が寄せられています。
TREグループではサーキュラーエコノミーへシフトしていくため「WX(Waste Transformation)」という取り組みに挑戦しています。WXとは、進化する廃棄物処理技術の活用によって生み出される、様々な業種の企業や自治体、研究機関が動脈・静脈の枠を超えて“共創”の力で高度循環型社会だけでなく、脱炭素社会も実現させるための取り組みです。私たちは、WXをサーキュラーエコノミーへシフトしていくための象徴として社会全体に浸透させ、高度循環型社会への転換を加速させたいと考えています。
WXの詳細はこちらからご覧いただけます。
こうした取り組みを具体化するサービスのひとつが、リバーの「まるっとリバー」です。サーキュラーエコノミーを実現していくためには、廃棄物を効率的に管理し、資源として循環させる仕組みづくりが欠かせません。リバーが提供する「まるっとリバー」は、煩雑になりがちな廃棄物業務を一括でサポートし、企業のサーキュラーエコノミーへの取り組みを後押しします。
ぜひ、お問い合わせください。