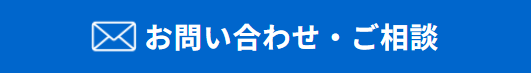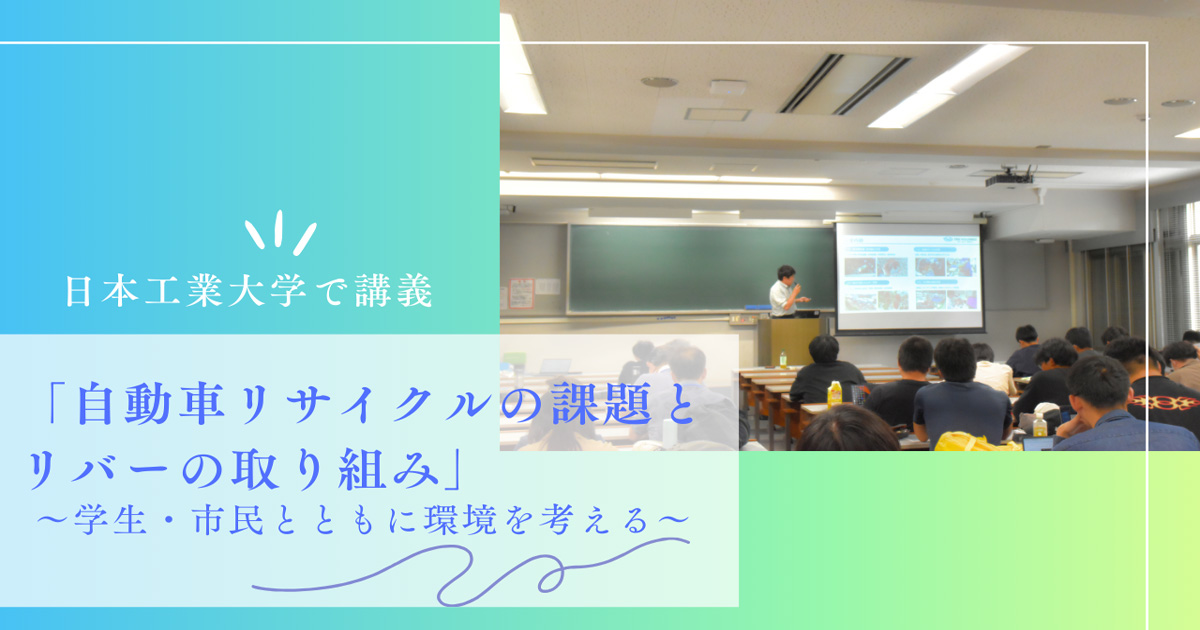バイクを手放す前に知っておきたい、リサイクルの仕組み
2025年09月08日

バイクはリペアやリユースが広く浸透しており、中古市場も発達しています。しかし、バイクも永遠に使えるわけではありません。では、いよいよ処分するとき、どうすればよいのでしょうか?
そこで注目したいのが、国内の主要4メーカーと輸入事業者が運営する「二輪車リサイクルシステム」です。この取り組みでは、バイクは全国各地の拠点へ集められ適正にリサイクル・処理されます。本記事では、この「二輪車リサイクルシステム」の仕組みや意義についてご紹介します。
目次
二輪車リサイクルシステムの全体像と対象
現在日本には、法的に定められたバイクの処理制度は存在しません。愛車が役目を終えた時、バイク専門の買取業者から不用品回収業者まで、処分の選択肢はいくつもありますが、中には有用な素材だけを取り出して、残りは適切に処理しない業者もおり、結果的に違法な廃棄につながってしまうこともあります。
「二輪車リサイクルシステム」は、再利用が難しいバイクを利用者が安心して廃棄できるよう、業界が自主的に整備した仕組みです。安全で確実に処理できるルートを提供し、適切なリサイクルを実現します。ここでは、本制度について詳しく見ていきます。
二輪車リサイクルシステムの概要と目的
二輪車リサイクルシステムは、製品のリサイクルに生産者が責任を持つという考えに基づいて設けられました。国内の主要メーカー(ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ)や輸入事業者が協力し、業界団体、販売店ネットワーク、全国のリサイクル・処理プラントの支援を得て運営されています。業界全体の自主的な取り組みとして整備され、2004年10月にスタートしました。
このシステムでは、廃棄二輪車を「廃棄二輪車取扱店」や「指定引取場所」で引き取り、これらを「処理・リサイクル施設」において適正にリサイクル・処理します。ユーザーが安心してバイクを廃棄できる仕組みを提供すると同時に不法投棄を抑制し、限りある資源の有効活用を推進することを目的として立ち上げられました。
2024年度の最新実績では、各メーカーとも高い再資源化率を維持しています。具体的な数値は以下のとおりです。
- 本田技研工業:引取台数402台、再資源化率(重量ベース)98.0%(注1)
- ヤマハ発動機:引取台数378台、再資源化率97.8%(注2)
- スズキ:引取台数244台、再資源化率97.8%(注3)
- カワサキモータース:引取台数10台、再資源化率97.8%(注4)
※再資源化率には、熱回収(サーマルリサイクル)が含まれます。
この結果は、この取り組みが循環型の社会づくりに確実に貢献していることを示しています。
(注1)Honda | 廃棄段階のリサイクル | 二輪車リサイクル自主取り組み | 進捗状況2024
https://www.honda.co.jp/motor-recycle/report2024.html
(注2)ヤマハ発動機 | 二輪車リサイクルシステム 2024年度の進捗状況
https://global.yamaha-motor.com/jp/sustainability/environment/mc-recycle/0023.html
(注3)スズキ| 2024年度 二輪車リサイクル自主取組みの進捗状況について | 二輪車リサイクル自主取組みの進捗状況について | 二輪車
https://www1.suzuki.co.jp/motor/recycle/progress/2025/
(注4)カワサキ|二輪車リサイクル自主取組みの進捗状況について
https://www.global-kawasaki-motors.com/environment/recyc_list.html
リサイクル対象となるバイクと条件
このシステムで引き取りの対象となる車両は、「二輪車リサイクルシステム」の参加事業者(以下、「参加事業者」)が国内で販売した二輪車(原動機付自転車、軽二輪、小型二輪)です。参加事業者(2025年8月時点)は、以下のとおりです。
■国内二輪車メーカー
本田技研工業株式会社、ヤマハ発動機株式会社、スズキ株式会社、カワサキモータース株式会社
■輸入事業者
ドゥカティ・ジャパン株式会社、ビー・エム・ダブリュー株式会社、ハーレーダビッドソンジャパン株式会社
残念ながら、すべての二輪車が引き取り対象になっているわけではありません。対象となる車両のメーカーやブランド、種類、引き取り基準は、以下のとおりです。
■メーカー・ブランド
二輪車リサイクルシステムの参加事業者が国内で販売した車両(参加事業者の取扱車両ブランドでも、並行輸入など、参加事業者以外が販売した車両は対象外)
■車両の種類
原動機付自転車、軽二輪、小型二輪(自転車(電動アシスト自転車を含む)、ATVやバギー、サイドカーなどは対象外)
■引き取り基準(抜粋)
・ハンドル、車台、エンジン、前後輪、燃料タンクが一体となっていること
・可動、不可動かは問わない(事故車も可)
・ガソリンやオイルの漏れがある場合は事前に除去済であること
・電動バイク(リチウムイオンバッテリー搭載車)はバッテリーを搭載したままでの引き取り可。ただし、メーカー非純正やバッテリー単体の場合は対象外
お持ちのバイクが対象かどうかは、各事業者に車台番号を伝えることで確認できます。各社で車両照会ページも用意しています。詳しくは以下を参照ください。
対象車両・引取基準|公益財団法人 自動車リサイクル促進センター
システムの運用開始後に生産された対象車両には、リサイクルマークが貼付されています。運用開始前に生産された車両についてはリサイクルマークが貼付されていませんが、参加事業者が国内で販売したものであれば、こちらも引き取りの対象となります。
ただし、車体がバラバラになっている(フレーム、エンジン、ガソリンタンク、ハンドル、前後輪のうち一つでも欠けまたは別体化しているなど)場合、引取対象外となります。事故車でも自立しており、パーツが一定の形で残っていれば引き取られますが、ガソリンやオイルの漏れがある場合は事前に除去する必要があります。
電動バイク(リチウムイオンバッテリー搭載車)については、2020年4月以降、対象メーカー製であれば、バッテリーを搭載したままでの引き取りが可能です。ただし、メーカー非純正やバッテリー単体の場合は対象外となり、取り外して対応する必要があります。
バイクをリサイクルに出す手順と費用
不要になったバイクは、「二輪車リサイクルシステム」を利用することで、安心して適正に処理やリサイクルへ回せます。この仕組みを通じて資源を有効に活用でき、環境への負担も減らせます。加えて、不適切な処理や不法投棄のリスクも抑えられます。ここからは、持ち込み方法、必要書類、費用の概要について紹介します。
指定引取場所・取扱店への持ち込み方法
バイクをリサイクルする際は、基本的に「指定引取場所」に直接持ち込む必要があります。ただし、自分で運ぶのが難しい場合には次の方法を利用できます。
1つ目は「廃棄二輪車取扱店」に持ち込み、指定引取場所までの運搬を依頼する方法です。
2つ目は「廃棄二輪車取扱店」に収集を依頼し、自宅から指定引取場所まで運んでもらう方法です。
前者では運搬費用、後者では収集と運搬の費用がかかります。金額は取扱店や移動距離、車両の状態によって変わるため、事前に見積もりを確認することが大切です。
■指定引取場所(注5):参加事業者が設けた廃棄二輪車の引き取り施設で、全国に約160か所あります。引き取り後のバイクを「処理・リサイクル施設」へ引き渡します。
■廃棄二輪車取扱店(以下、「取扱店」):参加事業者が業界団体や販売店の協力を得て設けた、二輪車廃棄に関する受付を行う窓口です。全国に約7,600店あり、店頭には「廃棄二輪車取扱店」であることを示す証票やステッカーが掲示されています。ここで引き取られたバイクは、その後指定引取場所へ輸送されます。
この全国に広がるネットワークを利用すれば、どの地域からでもバイクを持ち込んで引き渡せます。手続きの流れは以下のとおりです。
- 取扱店や指定引取場所を検索する
- 受付時間や必要条件を確認する
- 車両と書類を用意して持参する
- 受付で確認を受けたあとに車両を引き渡す
施設によっては事前の連絡が必要です。特に地方や一部の事業所では受入日が限られるため、電話やメールで確認してから手続きを進めてください。
(注5)指定引取場所一覧|公益財団法人 自動車リサイクル促進センター
https://www.jarc.or.jp/motorcycle/reception/
必要な書類と事前準備
リサイクルに出す際は、車両の廃車手続きを済ませたことを証明する書類の提示が必要です。車種や排気量によって手続きを行う窓口と発行される書類の名称が異なります。
|
車種・区分 |
排気量 |
廃車手続きの窓口 |
発行される書類名 |
|
原付一種・二種 |
125cc以下 |
市区町村役場 |
廃車申告受付書 |
|
軽二輪 |
126cc~250cc |
運輸支局 |
軽自動車届出済返納証明書 |
|
小型二輪 |
251cc以上 |
運輸支局 |
自動車検査証返納証明書 |
この廃車を証明する書類に加えて、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。
廃車手続きは、自分で行う方法と、取扱店や代行業者に依頼する方法があります。自分で行う場合は、市区町村役場(原付)や運輸支局(軽二輪・小型二輪)で廃車申告を行い、廃車証明書を受け取ります。代行を利用する場合は手数料がかかりますが、手間を省ける利点があります。
注意点として、名義変更が済んでいない車両は登録名義人の承諾や委任状が必要です。書類に不備があると受理されないため、事前の確認は欠かせません。さらに、廃車手続き完了を示す書類を紛失しても、再発行の申請が可能です。
リサイクルにかかる費用と料金体系
リサイクル料金はかかりません。不要になったバイクを指定引取場所へ直接持ち込めば、費用は不要です。ただし、取扱店に収集や運搬を依頼する場合や、廃車手続きなどを代行してもらう場合には費用が発生します。金額は車両の状態や走行距離、依頼先によって変わるため、事前に見積もりで確認することが大切です。
リサイクル現場の流れと社会的意義
バイクのリサイクルは、単なる廃棄処理ではなく、資源の有効活用や環境負荷の軽減につながる重要な取り組みです。現場では安全性と環境保全を考慮した工程が徹底され、適正な処理を通じて社会全体の持続可能性に貢献しています。
バイク解体・再資源化のプロセス
リサイクルに出されたバイクは、まず、ガソリンやエンジンオイル、冷却水などの液体が抜き取られます。これらは専門の設備で適切に処理され、再利用されます。次に、バッテリーや鉛などの有害物質を含む部品が取り外され、それぞれ専門の業者に引き渡されます。
その後、車体は破砕機にかけられ、細かく砕かれます。この破砕片は、強力な磁石や比重選別機などを使って、鉄、アルミ、プラスチック、ガラスといった素材ごとに細かく選別されます。最後に、選別された素材は、素材メーカーに引き渡され、様々な製品の原料として生まれ変わります。
また、原料への再生が難しい「素材の混ざった選別残渣物」についても、その多くが熱源としてサーマルリサイクルされています。こうした工程を経ることで、高い再資源化率が実現されており、公表値では重量ベースで97〜98%の再資源化率(サーマルリサイクルを含む)が達成されています。
不法投棄防止と社会的意義
バイクの不法投棄は、土壌汚染や生態系への悪影響を引き起こす深刻な問題です。バイクは粗大ごみとして回収されないこともあり、不法投棄されやすい傾向にあります。
こうした問題を防ぐため、メーカーや輸入事業者は二輪車リサイクルシステムを構築し、引取・解体・再資源化までを責任を持って行っています。また、自治体も回収拠点の案内や適正処理の啓発活動を行い、市民への周知を強化しています。利用者が制度を理解し適切に処分することは、環境保全だけでなく、不法投棄を抑止し、社会全体での資源循環を促進する重要な役割を果たします。
バイク処分の選択肢と比較
バイクの処分にはいくつかの方法がありますが、まずは二輪車リサイクル制度の利用が推奨されます。この制度を利用すると、適正な引き取り・解体・再資源化が行われ、環境保全や不法投棄の防止につながります。そのうえで、バイクの状態や事情に応じて「買取」や「解体業者への依頼」といった方法を検討することも可能です。ここでは、それぞれの特徴と注意点を説明します。
バイク買取・リユースとリサイクルの違い
まだ走行可能で外観や機能が良好なバイクは、廃棄前に買取査定を受けるのが賢明です。買取専門店やオンライン査定を活用すれば、廃車費用どころか現金化できる可能性もあります。リユース市場では、国内需要が低下した旧型車や高走行距離車でも、海外輸出や部品取り用として一定の価値が付くことがあります。
一方、リサイクルは車両を解体して素材ごとに再資源化するため、再販や部品再利用を前提としません。つまり、買取・リユースは価値の再利用、リサイクルは資源の再利用という違いがあります。価値が残っている場合は、まず買取査定を検討し、それが難しい場合には二輪車リサイクルシステムを活用することをおすすめします。
不用品回収・解体業者の利用に関する注意点
エンジンが動かない、状態が悪いなどの理由で買い取りが難しい場合、不用品回収サービスの利用を検討する方がいるかもしれません。しかし、利用する場合は十分な注意が必要です。
不用品回収業者の中には、無料回収を謳いながら後から高額請求をする悪質業者や、不法投棄を行う無許可業者が存在します。また、適正な処理費用として高額な料金を請求されるケースも少なくありません。不用品回収サービスの利用を検討する場合は、以下の点を必ず確認してください。
- 古物商許可や産業廃棄物収集運搬許可、一般廃棄物処理業許可など必要な許可を取得している業者か
- 料金体系が明確で、追加料金の発生条件が明示されているか
- 適正な処分方法を行っているか
- 無料回収を謳う業者ではないか
トラブルを避けるためにも、上述した正規ルートでの処分を検討してください。
自分で手続きする場合のポイント
費用を最も抑えられるのは、自分で廃車手続きとリサイクル持ち込みを行う方法です。指定引取場所まで直接運べば収集・運搬費用が不要になり、リサイクルマーク付き車両なら処理費も無料になります。
節約のコツは、自走できる場合はそのまま現地に持ち込む、手続きや書類作成を自分で行うといったことです(不動車の場合はレッカー・運搬費が別途発生します)。注意点としては、以下が挙げられます。
- 事前の問い合わせ・必要書類や対象条件の確認
- 廃車証明書の再取得漏れを防ぐ
- 自賠責保険や税金の解約手続きも忘れずに行う
よくある失敗例として、「バイクが対象外車両だった」「必要書類不備で受付不可」「運搬費用が高額になった」などがあり、事前の準備と確認が重要です。
まとめ:大事にリユース、最後は信頼できる二輪車リサイクルシステムの活用を
バイク愛好家の間では、カスタムや中古購入といった文化が長く受け継がれています。国内外には活発な中古バイク市場もあるため、使わなくなったバイクがある場合は、まず信頼できる店舗や買取専門店に相談し、リユースできるかを確認するのが環境負荷の面でも望ましい方法です。
もしリユースが難しい場合は、メーカーや輸入事業者が運営する「二輪車リサイクルシステム」を利用し、愛車を資源として再活用することを検討してください。限りある資源を守るうえで、最も安心できる選択肢のひとつです。
リバー株式会社では市原事業所(千葉県)・千葉事業所(千葉県)・加須事業所(埼玉県)・那須事業所(栃木県)の4か所で指定引取場所業務を行っています。バイクの処分でお困りの際は、リバーまでご相談ください。