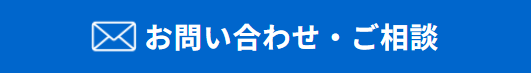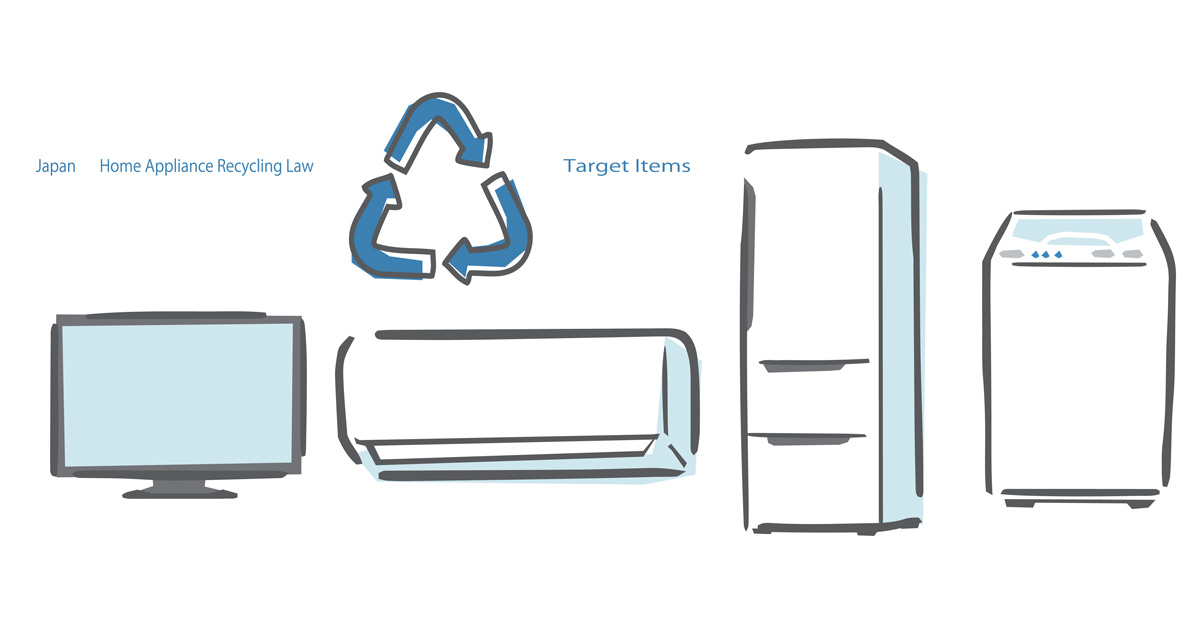海洋プラスチック問題の救世主か? 海洋生分解性プラスチックの可能性と課題
2025年10月09日

プラスチックごみによる海洋汚染が深刻化する中、解決策として期待されているのが「海洋生分解性プラスチック」です。本当にこの素材は海を救う切り札となるのでしょうか。
本記事では、技術的な可能性から普及に向けた課題、そして環境への影響まで、多角的な視点からその真価を検証します。
目次
海洋生分解性プラスチックとは?
深刻化する海洋プラスチック汚染問題への解決策として、現在、注目を集めているのが海洋生分解性プラスチックです。環境負荷の低減と持続可能な社会の実現に向けた重要な技術として期待されています。
海洋生分解性プラスチックの定義と特徴
通常のプラスチックは自然環境下では分解されず、半永久的に残り続けるため、海洋汚染の大きな原因となっています。これに対し、海洋生分解性プラスチックは、海中の微生物の働きによって水や二酸化炭素に分解されます。
重要なのは、「生分解性」と「海洋生分解性」とは異なるという点です。一般的な生分解性プラスチックは、土中の微生物やコンポスト環境下など特定の条件でしか分解されないため、海に流出した場合は分解が進まず、マイクロプラスチック化する恐れがあります。一方、海洋生分解性プラスチックは、海に生息する微生物によって、最終的には水と二酸化炭素に分解されるように設計されています。具体的には、PHBH(ポリヒドロキシブチレート-コ-ヒドロキシバレレート)という微生物の働きによって作られる生分解性プラスチックなどが該当します。海洋ごみによる生態系への悪影響やマイクロプラスチック汚染への懸念に対して、環境対応型素材としての役割が期待されています。
開発・導入の現状と政府のロードマップ
2019年のG20 大阪サミットで日本政府は、「2050年までに海洋プラスチックごみによる新たな汚染ゼロ」を目指すことを提案し、共通のグローバルなビジョンとして共有されました(大阪ブルー・オーシャン・ビジョン)。このビジョンを実現するため、官民が協力して以下の取り組みを進めています。
- 海洋生分解性の評価手法の確立
- 新しい素材や量産化技術の開発
- 国際規格の整備
また、研究開発だけでなく、「分別表示の仕組み」や「リサイクル技術の改良」、「製品の信頼性評価」など社会実装に必要な制度づくりも重視されています。こうした取り組みによって、まずは包装資材や漁具など海に流出しやすい分野からの段階的な導入が期待されます。しかし、2023年にNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)が公表した資料によれば、生分解性プラスチックの国内流通量は、全プラスチックのわずか0.02%程度にとどまっています。制度の整備やコストの高さなどが大きな壁となっており、普及にはさらなる取り組みが必要だと考えられています。
出典:海洋生分解性プラスチックの社会実装に向けた技術開発事業|NEDO
普及が進まない理由と課題
海洋生分解性プラスチックは、プラスチック問題の解決策のひとつとして期待されていますが、その普及には多くの課題が存在します。既存の社会システムや経済的な側面など、多岐にわたる障壁が立ちはだかっているのが現状です。
なぜ海洋生分解性プラスチックは普及しないのか
海洋生分解性プラスチックには大きな期待が寄せられていますが、普及は思うように進んでいません。その主な理由は次のとおりです。
- コストの高さ:石油由来のプラスチックに比べて製造コストが高く、価格競争力に乏しい。
- 性能面の課題:耐久性や耐熱性が低いため、利用できる用途が限られる。
- 分解条件の限定性:海洋環境でも確実に分解するとは限らず、素材によっては微細な破片が残る可能性がある。
これらの要因が重なり、導入効果への懐疑を招いています。結果として、コスト、性能、流通、信頼性といった複数の壁が複雑に絡み合い、海洋生分解性プラスチックの普及は容易ではありません。
既存のリサイクルとどう共存できるか?
生分解性プラスチック(海洋生分解性を含む)は、従来の石油由来プラスチックと混ざって排出されると、リサイクル工程に深刻な影響を与える可能性があります。混入すれば再生樹脂の品質が低下したり、分解途中で工程を妨げたりするためです。では、既存のリサイクルとどう共存できるのでしょうか。考えられる方向性は以下の3つです。
識別表示の徹底
生分解性プラスチックであることを明確に示す統一的な識別表示を設け、リサイクル工程に混入しないようにする
消費者への啓発活動
生分解性プラスチックの特徴や排出時の注意点などを消費者にわかりやすく周知し、適切な分別行動を促す
専用の回収・分別システムの構築
生分解性プラスチックを一般のプラスチックごみと分けて処理できるよう、専用の回収ルートや分別インフラを整備する
実際、専用回収ルートや認証ラベルの普及を目指した動きがあるものの、自治体ごとで回収方針や分別基準にばらつきがあり、全国的な整備は道半ばです。リサイクル業界からも「混入時にリサイクル全体が混乱する」などの声が上がり、ラベル表示や教育の強化が求められています。生分解性プラスチックの普及にあたり、現行のリサイクル制度との共存策構築が不可欠です。
制度・インフラの整備が追いついていない現実
制度面でも、日本国内は欧州諸国に比べて法整備やインフラが遅れているのが現状です。
欧州では堆肥化基準やEN13432(堆肥化できるプラスチック製品の条件を定めた欧州規格)などの認証制度が普及し、自治体を軸とした回収インフラも進んでいますが、国内では国レベルの堆肥化基準が未整備、地方自治体による格差も大きく、分別・回収ルートの確立が不十分です。
また、焼却処理が主流となる日本固有の事情もあり、「ごみ処理の完成形」とも言われる一方で、生分解性プラスチックの本来持つ資源循環の理念が活かしきれない状況です。
プラスチックごみ問題の現状、リサイクルの実態、政策の変化、循環型社会を目指す最新の取り組みなどについて詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。
関連記事:プラスチックごみ問題とは? 現状と循環型社会への道のり
生分解性プラスチックの環境影響
生分解性プラスチックは、環境負荷を低減する可能性を秘めている一方で、その効果は多くの条件に左右されます。つまり「生分解性」と表示されていても、必ずしも自然の海洋環境下で短時間に分解するとは限りません。
環境負荷は本当に減るのか
生分解性プラスチックが環境負荷を減らすかどうかは、その原料によって大きく異なります。トウモロコシやサトウキビなどのバイオマスを原料とする生分解性バイオマスプラスチックは、植物が成長過程でCO2を吸収しているため、焼却や分解時にCO2が排出されても、大気中のCO2濃度を増やさないという「カーボンニュートラル」の性質を持ちます。この点は、石油由来のプラスチックにはない大きなメリットです。
しかし、石油由来の原料から作られる生分解性プラスチックも存在するため、すべての生分解性プラスチックが脱炭素に貢献するわけではありません。また、分解に必要とされる特定条件下でのエネルギー消費や、製造コスト、リサイクルシステムの未確立といった課題もあります。
海洋での分解速度と条件
海洋生分解性プラスチックの最大の不確実性は、分解速度が海洋環境に強く依存することです。温暖で微生物の活動が活発な沿岸域では、比較的早く分解が進むケースがある一方、低温の外洋や深海では、分解がほとんど進まず、数年単位で残在する可能性があります。
最近の研究では、深海でもプラスチックを分解する微生物が発見されており、分解の可能性が示されています。
出典:生分解性プラスチックは深海でも分解されることを実証 ――プラスチック海洋汚染問題の解決に光明―― | 東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部
pHや塩分濃度も影響します。微生物活性が高い中性~弱酸性環境では分解が進みやすい一方、海洋の深層部や寒冷域ではほとんど分解が進まないこともあります。つまり「生分解性」と表示されていても、必ずしも自然海洋環境下で短期間に分解するとは限らないのです。
マイクロプラスチック問題を本当に解決できるのか?
海洋生分解性プラスチックがマイクロプラスチック問題を根本解決できるかについては慎重な検証が必要です。生分解性プラスチックは条件が整えば水とCO2に分解され、微細化せずに消滅することが理想です。しかし、回収インフラ未整備や消費者の誤認によるポイ捨て増加、分解条件の不適合などにより、分解する前に微小な破片(マイクロプラスチック)化して環境中に長期間残留する可能性があります。
また、分解速度が遅かったり、処理環境が適合していなかったりする場合、結果的に従来のプラスチック同様にマイクロプラスチック汚染を助長します。分別・回収・破砕方法を厳密に管理しなければ、原理的なマイクロプラスチック抑制効果も十分に発揮できません。根本的な解決には、消費者の意識向上や回収体制の強化とともに、分解性材料の品質と分解環境管理の徹底が不可欠です。
これからの展望と必要な取り組み
海洋プラスチック問題の解決に向け、海洋生分解性プラスチックは大きな可能性を秘めています。その普及と社会実装のためには、技術開発だけでなく、人々の意識改革を含む多面的な取り組みが不可欠です。
技術・表示・分別の進化
現在、従来の耐熱性や強度の課題を克服する新たな生分解性ポリマーの開発が進んでいます。産業技術総合研究所では光スイッチ機能を持つ材料の研究も行われています。例えば、光が当たっている間は分解が進まず、光が遮断されると分解が促進されるといった仕組みの検討が進められています。
分別技術では、既存のリサイクルシステムとの共存が課題となっています。生分解性プラスチックが従来のPETリサイクルに混入すると品質低下を招くため、高精度な識別・分別技術の開発が急務です。
識別表示制度については、一般社団法人日本バイオプラスチック協会による「生分解性プラ識別表示制度」が存在し、厳格な基準をクリアした製品のみが表示できる仕組みが確立されています。国際的には、ISO規格の整備が進んでいます。日本でも、国際規格 ISO 16636:2025 の規格方法を活用するための検証・推進が進められています。今後は各国の認証機関との連携を深め、グローバルスタンダードの確立を目指す必要があります。
社会をどう動かすか? 意識改革と多面的アプローチ
技術が整っても、それを活かせるか否かは社会全体の行動にかかっています。まず消費者に正しく知ってもらい、理解を深めることが大切です。学校教育や公共キャンペーンを通じて、生分解性プラスチックは「万能ではなく、適切な場面で使う素材」であることを理解してもらうことが重要です。誤った期待や乱用は、逆に環境問題を深刻化させるリスクを伴います。
同時に、企業のCSR活動やサーキュラーエコノミーへの参画も欠かせません。製造・流通・消費の各段階で、リデュースやリユースを優先しつつ、生分解性プラスチックを補完的に位置付けることが望まれます。また、廃棄の最終段階では、埋め立てによる安定的管理やCCS(Carbon Capture and Storage:二酸化炭素回収・貯留)との連携によって、地球温暖化防止と資源循環を両立させる試みも検討されています。
結局のところ、海洋生分解性プラスチックは、リサイクルや廃棄管理、消費者行動と組み合わせた多面的アプローチの中で初めて真価を発揮します。社会の仕組みと個人の意識をどう動かすかが、今後の大きな鍵となります。
海洋生分解性プラスチックの将来展望と日本の役割
世界的に海洋プラスチック問題への関心が高まるなか、海洋生分解性プラスチックは国際的な解決策の一つとして注目されています。日本でもNEDOや大学研究機関が中心となり、分解速度を制御可能にする高機能材料や、用途特化型のプラスチック開発が進められています。こうした技術が確立すれば、漁具や使い捨て包装材など、海洋流出リスクの高い分野での実装が加速するでしょう。
しかし、仮に「自然に分解されるから安心」という誤解が広がれば、ポイ捨てや不適切な廃棄を助長しかねません。これは本来の目的と逆行し、むしろ海洋ごみの拡散を増やす危険をはらんでいます。そのため、技術進歩だけでなく、倫理的・制度的な枠組みづくりは欠かせません。
日本はこれまで培った素材開発力やリサイクル技術を活かし、国際標準策定やアジア地域への技術移転などで重要な役割を果たせる立場にあります。未来の展望は明るい一方で、社会的責任と意識改革を伴わなければ真の解決には至りません。日本が率先して「技術と倫理を両輪とする持続可能なモデル」を提示できるかどうかが、今後の行方を左右するでしょう。
リバーでは、高度循環型社会の実現へ向けた取り組みを進めてまいります。プラスチックリサイクルに関してお困りのことがありましたら、ぜひご相談ください。