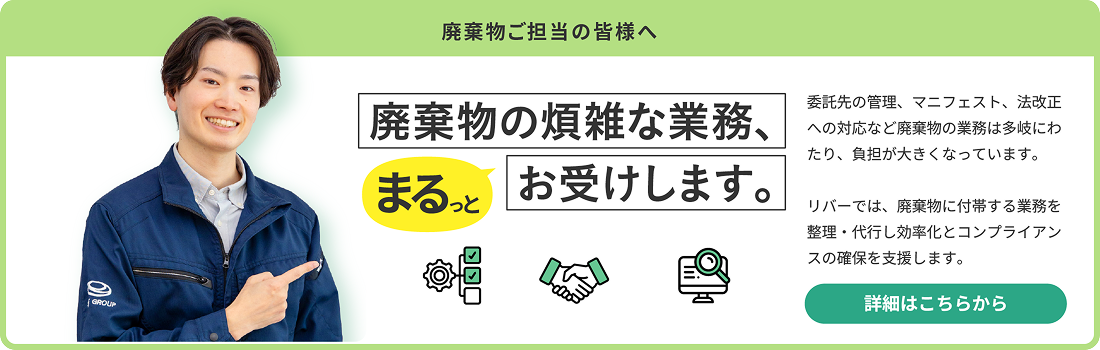廃棄物管理とは?排出事業者が知るべき廃棄物の種類や処理の流れを解説
2025年05月21日

事業活動において避けては通れない廃棄物管理。企業が排出する廃棄物を適切に処理することは、法律で定められた事業者の義務です。産業廃棄物を排出する事業の担当者であれば、廃棄物管理の基本は必ず押さえておきたいところでしょう。
この記事では、廃棄物管理とは何か、排出事業者が負うべき責任に着目して解説します。廃棄物の種類や処理の流れ、場合によっては必要となる資格についてもまとめていますので、自社で排出される廃棄物と照らし合わせながら参考にしてください。
目次
廃棄物管理とは?
廃棄物管理とは、事業活動で発生する廃棄物の種類や区分を把握し、関連法規に従って適切に処理を行うことです。廃棄物について、環境省は「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)」と定義づけています。
事業活動によって排出される廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」によって20品目が産業廃棄物として定められています。
産業廃棄物について詳しく知りたい方は、別記事「産業廃棄物とは?」をご覧ください。
事業者が遵守すべき「廃棄物処理法」
廃棄物処理法は、正式名称を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」といいます。この法律は、廃棄物の排出を減らしつつ適正な処理を行うことで、生活環境を守ることを目的に制定されました。
廃棄物を排出する事業者や、処理を行う事業者はこの法律に従って事業を進める必要があります。なお、法律違反があった場合の罰則規定も設けられています。万が一、違反した場合には懲役刑や高額な罰金が科される可能性もあるため、必ず遵守しましょう。
事業者の負うべき責任範囲
企業は、自社の事業活動で排出した産業廃棄物について排出事業者責任を負います。具体的には、産業廃棄物の「保管」「処理委託」「委託した処理の確認」の3つの段階で責任を負います。
- 保管
廃棄物は、自社での保管方法にも基準があります。これを「産業廃棄物保管基準」といい、以下のような要件を満たす必要があります。
| 保管基準 | 内容 |
| 囲い | 周囲に囲いを設けること |
| 表示 | 60cm × 60cm以上の掲示板を設けること |
| 飛散・流出防止 | 産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないようにすること |
| 保管高さ | 保管の高さを守ること(屋外の場合は一般的に5m以下) |
| 衛生管理 | ねずみ、蚊、はえなどを発生させないこと |
| 混合防止 | ほかの物と混合しないように仕切りを設けるなどの措置をとること |
| 石綿など | 石綿などの特別管理産業廃棄物は、ほかの物と区別して保管すること |
これらの基準を守らない場合は、行政指導を受ける可能性があるため注意してください。
- 処理委託
廃棄物は、都道府県知事などによる許可を得ている処理業者へ処理を委託しなければなりません。依頼時には、業者が「産業廃棄物収集運搬業許可証」「産業廃棄物処分業許可証」を持っているか確認する必要があります。
また、許可証を確認するときは、以下の点に注意しましょう
・有効期限が切れていないか
・処分できる産業廃棄物の種類に、自社の廃棄物が含まれているか
・広域での収集運搬が必要な場合は積み地・卸し地の双方で許可を得ているか
万が一、依頼先の業者がこれらの条件を満たしていない場合は、無許可業者への委託とみなされ、法律違反となる可能性があります。
- 状況確認
排出事業者は、処理を依頼したあとも、廃棄物が適切に処理されているかどうか確認する責任があります。この確認には「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」を活用します。
マニフェストとは、処理を委託した産業廃棄物が、契約内容どおりに適正処理しているかどうかを確認するための管理伝票です。産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、処理が終わるまで関係者間でマニフェストが移動します。これにより、産業廃棄物の処理状況を確認できます。
マニフェストについて詳しく知りたい方は、別記事「5分でわかるマニフェスト」で解説しています。
そもそも廃棄物とは?
廃棄物は、事業活動で発生する20種類の「産業廃棄物」と、一般家庭などから排出される「一般廃棄物」に分類されます。事業者にとっては、自社から排出される廃棄物がどの分類に該当するかを正確に把握することが、適切な廃棄物管理の第一歩となります。
産業廃棄物
産業廃棄物に指定されている20種類は、以下の表のとおりです。
| 産業廃棄物の種類 | ||
|
あらゆる事業活動に |
1 | 燃え殻 |
| 2 | 汚泥 | |
| 3 |
廃油 |
|
| 4 |
廃酸 |
|
| 5 |
廃アルカリ |
|
| 6 |
廃プラスチック類 |
|
| 7 |
ゴムくず |
|
| 8 |
金属くず |
|
| 9 |
ガラスくず・コンクリートおよび陶磁器くず |
|
| 10 |
鉱さい |
|
| 11 |
がれき類 |
|
| 12 |
ばいじん |
|
|
特定の事業活動に |
13 |
紙くず |
|
14 |
木くず |
|
|
15 |
繊維くず |
|
|
16 |
動植物性残さ |
|
|
17 |
動物系固形不要物 |
|
|
18 |
動物のふん尿 |
|
|
19 |
動物の死体 |
|
|
20 |
政令第13号廃棄物 |
|
参照:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令|e-Gov法令検索
また、このうち爆発性や毒性があり危険をおよぼすものは「特別管理産業廃棄物」に分類されます。特別管理産業廃棄物は、通常の産業廃棄物と比べて厳格な管理が求められています。
一般廃棄物
一般廃棄物は、産業廃棄物に指定されている20種類以外の廃棄物を指します。具体的には、以下の3つに分類されます。
| 事業系一般廃棄物 |
事業活動によって生じる廃棄物のうち、 |
| 家庭系一般廃棄物 | 日常生活や家庭から排出される廃棄物 |
| 特別管理一般廃棄物 |
爆発性や毒性を持った一般廃棄物 (PCBを使用した家庭用電気機器など) |
特別管理一般廃棄物は、特別管理産業廃棄物とあわせて「特別管理廃棄物」とも呼ばれます。これらは通常の廃棄物よりも、厳しい管理が求められています。
事業所内に責任者の設置が必要な場合がある
自治体によっては、事業活動で排出される産業廃棄物が適切に処理されているか責任者を設置するよう義務付けている場合があります。例えば、東京都では通常の産業廃棄物を排出する事業者へ「廃棄物管理責任者」の設置を義務付けています。
また、事業活動により、特別管理一般廃棄物や特別管理産業廃棄物を排出する事業者は「特別管理産業廃棄物管理責任者」を配置しなければなりません。これは、廃棄物処理法で定められている全国共通の義務です。
特別管理産業廃棄物管理責任者については資格が必要であり、「感染症産業廃棄物を排出する事業場」「感染症産業廃棄物以外を排出する事業場」どちらの場合も、医師など特定の職業に就いている人、もしくは大学・高専において特定の課程を修了した人が資格要件を満たしています。
しかし、必ずしもそうした人が事務所に在籍しているわけではありません。その場合は、「日本産業廃棄物処理振興センター」が開催する指定講習会に参加し、修了試験に合格すると資格が認められます。
講習は「医療関係特管責任者講習会」と「特管責任者講習会」があり、講習会終了後の資格の扱いは各都道府県・政令市により異なります。
出典:日本産業廃棄物処理振興センター「教育研修事業(講習会・研修会)」
廃棄物処理の基本的な流れ
産業廃棄物の処理は「収集・運搬」「中間処理」「最終処分」という3つの段階を経て行われます。排出事業者はこの流れを理解し、各段階で適切な対応を取る必要があります。
収集・運搬
収集・運搬とは、産業廃棄物を適切な場所へ運ぶことを指します。排出事業者が自ら収集・運搬を行う場合、特別な許可は必要ありません。ただし、依頼を受けた業者が収集・運搬を行う場合は、荷積みや荷卸しの場所それぞれの自治体にて許可を得る必要があります。
例えば、A県からB県へ産業廃棄物を運搬する場合、収集運搬業者はA県とB県両方の許可を取得していなければなりません。また、積み替え保管を行う場合は、その場所の自治体の許可も必要です。
中間処理
中間処理とは、産業廃棄物を最終処分するために、選別・破砕・脱水・焼却・中和などを行うことを指します。産業廃棄物を減量化するほか、リサイクル可能な資源にする重要な工程の一つです。主な処理方法と内容は、以下の表のとおりです。
|
方法 |
内容 |
|
選別 |
種類や目的にあわせて分別する |
|
破砕 |
潰したり砕いたりして容積を減少させる |
|
脱水 |
水分を取り除いて減量化する |
|
焼却 |
高温で燃焼して減量化する |
|
中和 |
pHを調整して安定化する |
このように、中間処理は最終処分場の負担を軽減するとともに、資源の有効活用につながる重要な工程だといえます。
最終処分
最終処分とは、埋立処分、海洋投入処分又は再生をいい、このうち埋立処分とは中間処理の終わった産業廃棄物を土に埋めることを指します。産業廃棄物の埋立処分場は「遮断型最終処分場」「安定型最終処分場」「管理型最終処分場」の3つの種類に分類されます。
| 特徴 | 対象となる主な廃棄物 | |
| 遮断型 最終処分場 |
・有害な化学物質や重金属が基準値を超えて含まれるものを処分 |
・基準値を超える有害物質を含む産業廃棄物 |
| 安定型 最終処分場 |
・有害物を含まず、雨水にさらしても変化しないものを処分 |
・廃プラスチック類 |
|
管理型 |
・安定型産業廃棄物ではないが遮断型最終処分場で処分する必要のないものを処分 |
・燃え殻 |
最終処分場の残余容量は全国的に逼迫しているのが現状です。そのため、適切な分別や再資源化の取り組みが重要となっています。
廃棄物管理のサポートならリバーへ
廃棄物管理とは、事業活動で排出される廃棄物を、法令に従い適切に処理することを意味します。排出事業者は保管・処理依頼・処理後の状況確認などについて各段階で法的責任を負うため、最終処分に至るまでのプロセスを適切な業者選定とマニフェスト管理によって実施する必要があります。
事業活動で排出される産業廃棄物の処理にお困りであれば、ぜひリバーへご相談ください。再利用できない廃棄物もまとめて処分できるため、ワンストップで対応いたします。
また当社は、廃棄物の処理・リサイクルに加え、廃棄物に関わる皆様の業務を大幅に削減するサポートを行っています。ぜひこちらもご覧ください。