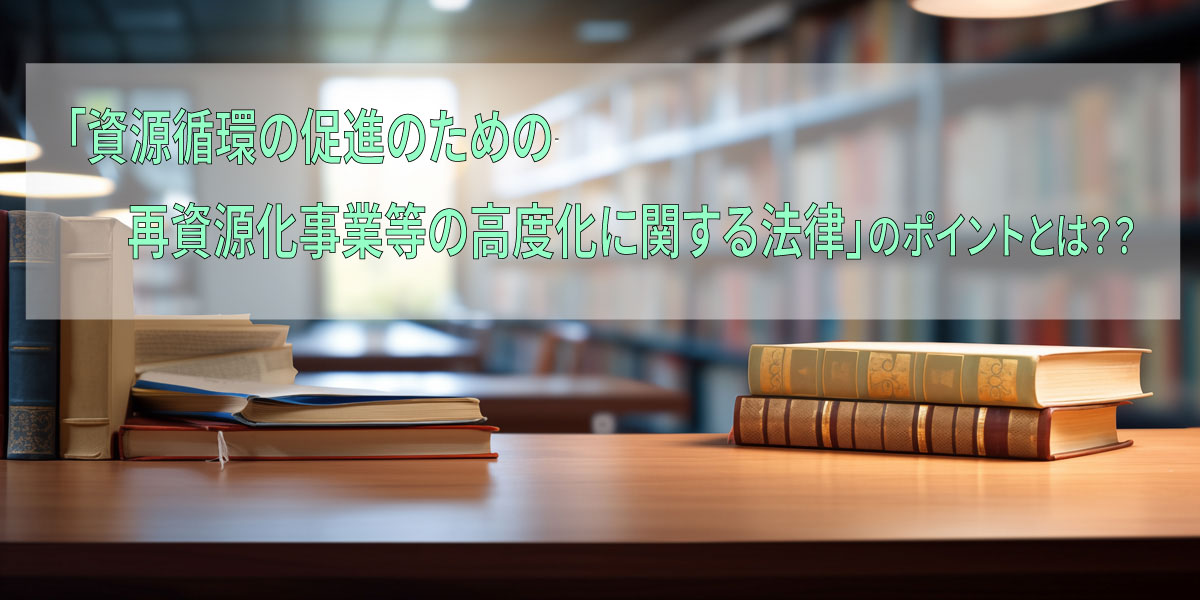委託契約書と覚書の違いとは?
2018年06月25日
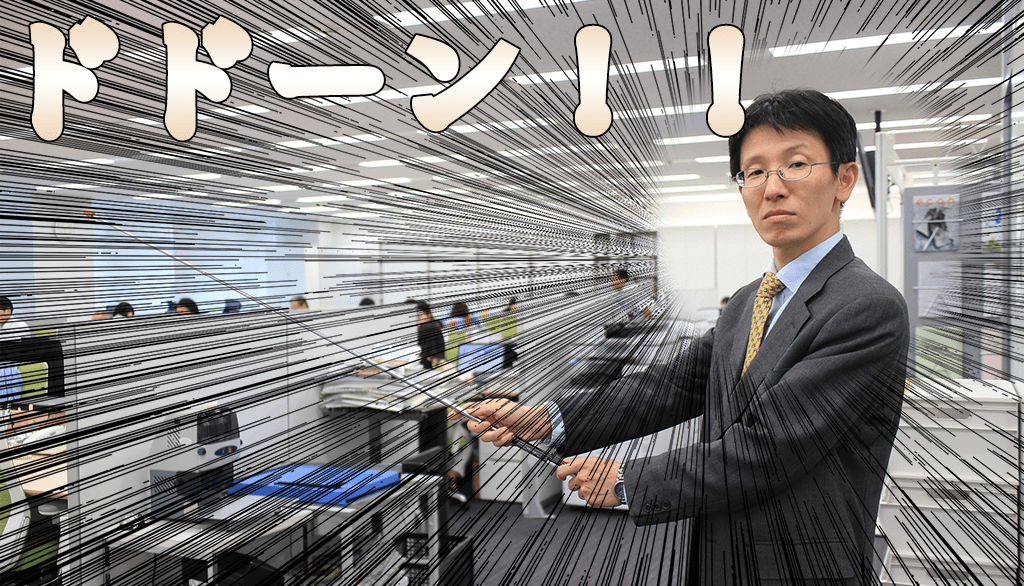
目次
『委託契約書と覚書はどう違うの?』
廃棄物処理法第12条第6項で、「(排出)事業者は産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない」と定めており、その基準として施行令第6条の2第4号で「委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には~」と記載されています。したがって法律の要請は「委託契約を書面で行う」ことで、「委託契約書」という名称は、この書面を便宜的に指しているのであって、このような名称の契約書面を作成することを求めているのではないはずです。
一般に「契約」は、当事者の意思表示が合致することによって成立するものです。例えば何か商品を購入する際に、店員さんと相談したうえで「これください」と口頭で意思表示してもよいですし、普段の買い物のように一言も発せずにレジに商品を持って行くだけでも、マウスをクリック、スマホをタップするだけでも成立します。これをあえて書面にすることにより、意思が合致したことが分かり、契約内容を明確化し将来のために証拠として残すことができるのです。廃棄物処理法では、記載内容を法定することで合意事項を明確化し、契約終了後5年間は保存することを求めています。
「契約書」「覚書」「念書」「約款」「協定書」「確認書」「合意書」・・・当事者が合意していることが分かれば、書面による契約
したがって、作成する書面の表題は、「契約書」「覚書」はおろか「念書」「約款」「協定書」「確認書」「合意書」のいずれでも、当事者が合意していることが分かれば、書面による契約ということになります。
合意を表す形式についても、当事者が記名押印をする方法だけでなく、片方から差し入れる方法や、定型のものを作成しておく、ウェブ上でマウスクリック、電子署名にすることも可能です。
契約書のタイトル、表題としては、①「産業廃棄物処理委託契約書」、②「産業廃棄物収集運搬委託契約書」、③「産業廃棄物処分委託契約書」など、いろいろなパターンがあり、使い方に迷われることがあるようです。「処理」は「処分」や「中間処理」しか指さないと勘違いされている方もいますが、「収集運搬」も含んだ広い概念ですので、使い分けが面倒な場合は①にしておけば問題にはならないでしょう。
また、単に「業務委託契約書」となっていたり、「産業廃棄物処理委託標準契約書」「産業廃棄物処理基本契約書」などの名称だったりしても、特に気にすることはありません。表題が「産業廃棄物~」だったとしても、有価物の売買や、一般廃棄物の処理についても同一の契約書に記載しても構いません。極論すると「産業廃棄物収集運搬契約書」の内容が処分委託契約だけだったとしても、契約の効力がなくなるということはありません。契約書の表題には、それほど拘泥する必要はありません。
とはいえ、会社によっては「契約書は稟議事項・覚書は部長承認」になっているかもしれません。契約書は表題で管理、ファイリングしていることもあるでしょう。しかも覚書は単体では運用せず、契約書の補足、追加のためのものであることが多いはずです。契約書はその種類、相手先の名称、コードや番号などを用いて、目的に応じて管理、運用するようにしましょう。
(リバーグループ/メジャーヴィーナス・ジャパン株式会社 シニアコンサルタント・行政書士 堀口昌澄)