資源循環や環境対策の観点で、新型コロナウイルスの影響を考える。
2020年05月12日
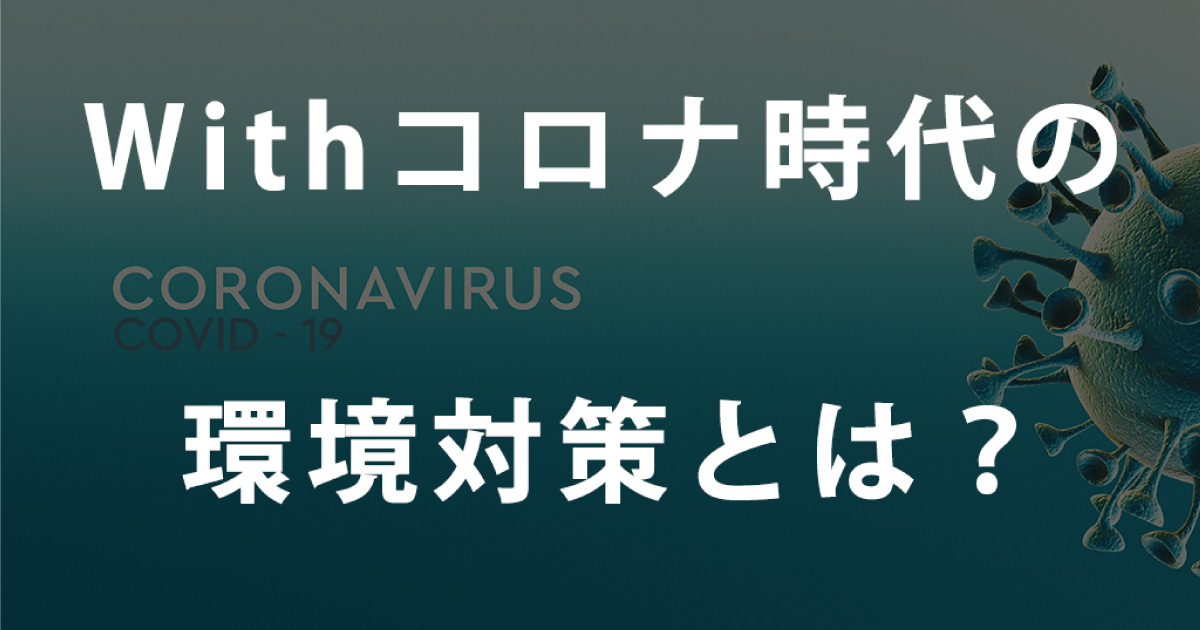
この記事のポイント
・新型コロナウイルス対策で廃棄物の発生量は比較的落ち着いているが、終息後はこれまでより処理が逼迫する可能性もある。今のうちにできる対策を取るべき。
・新型コロナウイルス対策は、結果的に大気汚染やCO2排出など、環境負荷の低減にもつながっている。
・次のパンデミックに備えて、国別に行われていた環境問題への対応も、世界統一の基準で行われる動きも出てくるだろう。
目次
コロナウイルス終息後の環境対策
新型コロナウイルスの影響が収まった後の世界では、資源循環や環境対策にどのような変化があるのか、今回はそのようなことを考えてみました。
経済の停滞が長期化するほど、経営が立ち行かなくなる業者が出てくるため、社会全体としての処理能力は低下していくものと思われます。そして新型コロナウイルスの感染が収束もしくはコントロール可能となり、急激に経済が回復するのであれば、反動需要により資源循環システムがかつてないほどオーバーフローするでしょう。処理施設で感染者が出れば、一定期間稼働を停止する可能性があり、これも安定処理のかく乱要因となるでしょう。
第二波、第三波が来れば経済は停滞、回復を繰り返すため、廃棄物の発生量の変動幅は大きくなり、システム全体へ負荷がかかります。中長期的には、中国に依存していた生産設備は東南アジア諸国への分散だけでなく国内回帰も進み、廃棄物の発生量は以前より多くなる可能性もあります。いずれにせよ、コロナ前より処理能力不足が緩和される要素は少ないと想定されます。発生量が比較的少なく小康状態にある今のうちに、保管場所の拡張や保管容器の追加、Reduce,Reuseの検討や新規の処理方法の検討をされてもよいのではないでしょうか。
コロナ対策真っただ中の現在は、経済活動の停滞により、廃棄物の発生量は減少しています。これまで上昇してきた処理費は一転して下落トレンドにあるため、コロナ対策前後では処理費が変動する可能性があります。テレワークに対応するためにも電子契約を導入する動きは活発化していますが、処理費の変動に適時対応し、処理を滞りなく進めるためには電子契約への対応は必須でしょう。社内規定の変更が必要であれば、これも今のうちから準備しておくべきです。
また、外出制限により大気汚染が抑制されているようですが、米ハーバード大学T・H・チャン公衆衛生大学院の研究者が公開した論文によると、新型コロナウイルスによる肺炎は大気汚染によって悪化しやすく、死亡率も高いということです。PM2.5の濃度が1立方メートルあたり平均わずか1マイクログラム高いだけで、死亡率が15%も高かったというのですから驚きです。それどころか、WHOによると大気汚染によって全世界で400万人以上の人が毎年継続的に亡くなっているのですから、一過性のコロナウイルス対策以上に重要で対処可能な問題のはずです。大気汚染は人災なのですから。もしかしたら、新興国の大気汚染問題も改めてクローズアップされるかもしれません。
当然ですが、大気汚染同様、CO2の排出量も減少しています。このように、新型コロナウイルス対策は結果的に経済活動を鈍化させ、環境負荷の低減にもつながっているのですが、この二つの類似点はそれだけに留まりません。
個人個人の小さな行動の積み上げによって、全体の進む方向が決まるという点で、コロナ対策も環境対策も同じような構造なのです。投票率も似ていますね。「自分ひとりくらい、やらなくても影響ないだろう」という判断は個別的には正しいのですが、その行動の総和が大変な問題を起こしているのです。
しかし違う点もあります。コロナ対策は同時代の自分たちのためですが、より破滅的であるはずの環境対策は将来世代のためであるため、他人事であり時間的猶予があるので本気度が低いのではないでしょうか。
国によって取り組み方も違います。諸外国では、コロナ対策のために休業補償と外出禁止に罰則を科しているところが多く、金銭的な支援と強制力があります。わが国では補償が薄く、外出自粛は要請のみで罰則がないため緩やかで、効果が出るまでに時間がかかります。
環境対策についても、特にEUでは動きが活発です。炭素税の導入や排出権取引は序の口で、ESGやTCFDやSBTなど企業の経営と経済に直結したスキームが提案される一方、わが国の取組みは最低限の規制の他は、普及啓発が中心です。最近注目されていたナッジなどの自主的取り組みを否定するものではありませんが、今のままでは日本は常に後手に回り、諸外国に後れを取るような気がします。社会全体が、個人の行動変容をどのように促すべきか、強制すべきか、今回のコロナ対策を機に改めて考える必要があるでしょう。
そして忘れてならないのは、同様の災厄は今後も間違いなく来るということです。鳥インフルエンザのパンデミックもいずれ必ず発生すると言われています。いまは世界が分断しつつあるように見えますが、次のパンデミックまでには、発生地域に対する早期の支援と関与、薬やワクチンの開発の国際協力体制を構築していなければなりません。それ以外の選択肢はないはずです。
さらに、地震や大規模水害は世界各地で起こり続け、復興支援とサプライチェーンの分断が継続的に問題となります。リスク回避のために、今まで以上に世界各地に生産設備が分散配備されるのではないでしょうか。もちろん、日本で首都直下型地震や東南海地震が起これば、世界経済に大打撃を及ぼすため、大きなマイルストーンになるはずです。世界はますます幅広くネットワーク化、緩やかにかつ確実に一体化し、国別に行われていた環境問題への対応も、世界統一の基準で行われるのではないでしょうか。とてもできそうにないように思えますが、人類が生き残るためにはそれ以外の選択肢はないはずです。
問題は、その選択をいつやるのか?です。早いところ「今でしょ!!」と言えるようにしたいものです。
(リバーグループ/メジャーヴィーナス・ジャパン株式会社 シニアコンサルタント・行政書士 堀口昌澄)







