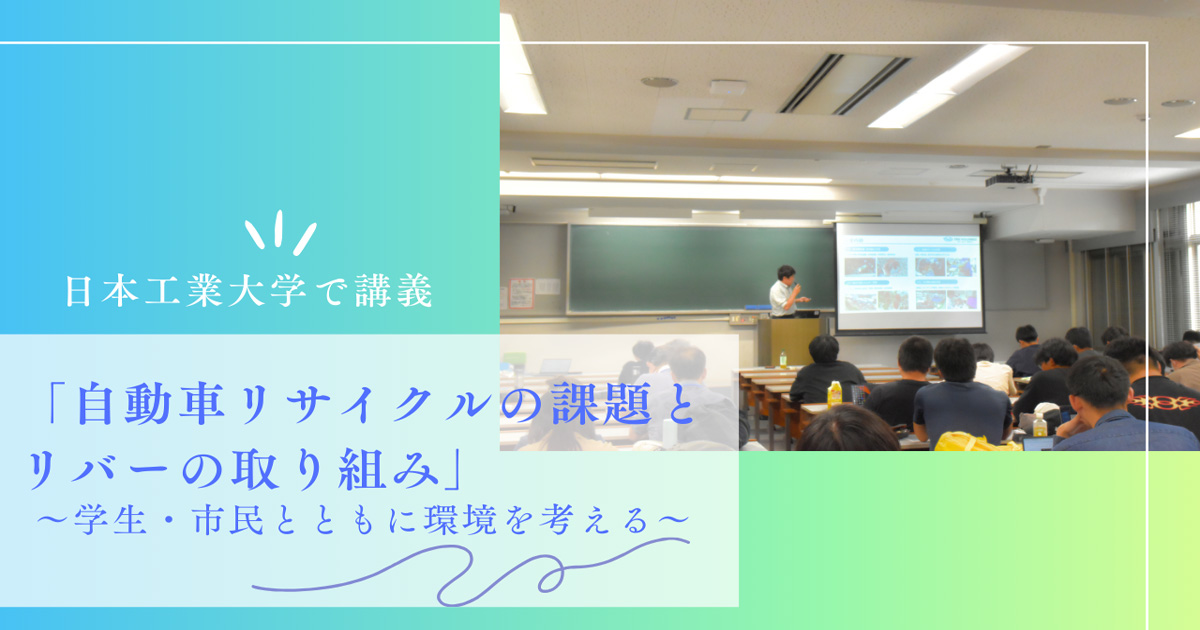IoT時代においてマニフェストの紐づけ管理に意味はあるのか|適正処理の確認のためには、より実効性のある仕組みへの進化を。
2020年08月06日

この記事のポイント
・マニフェスト制度では、中間処理業者は、2次マニフェストのE票(最終処分報告)が返却されたら、関連する1次マニフェストのE票に転記して排出事業者に返送することになっている。
・この「紐づけ管理」は、自動化されたラインで大量に処理を行う現場において、中間処理後に出てきた物のどの部分に該当するのかを判断するのは難しい。
・人手不足が続くこれからは、IoTシステムの導入を条件に、契約、マニフェスト管理を不要とするといった「紐づけ管理」のアップデートが必要。
目次
マニフェスト
産業廃棄物の行き先を管理し、不法投棄を未然防止することを目的としたマニフェスト制度では、1次マニフェストで「排出事業者~運搬業者~中間処理業者」までを、2次マニフェストで「中間処理業者~運搬業者~最終処分業者」までを管理します。
それぞれ排出事業者が1次、中間処理業者が2次マニフェストを交付しますが、中間処理業者は1次と2次の間をつなぐ役割を担います。具体的には、1次マニフェストの産廃がどの2次マニフェストに含まれるのかを把握しておきます。これを紐づけと言い、帳簿に記録しておきます。
2次マニフェストのE票(最終処分報告)が返却されたら、関連する1次マニフェストのE票に転記して排出事業者に返送します。つまり、1次マニフェストを1件ずつ個別で最終処分までトレーサビリティ管理をしているのです。
この仕組みは1992年にマニフェスト制度ができた当時はなく、2000年に追加されました。これにより、排出事業者は中間処理の終了だけでなく、最終処分まで確認することが出来るようになりました。同時に、契約書の記載事項として最終処分先も追加されています。
当時の通知(末尾参照)にもあるとおり、「最終処分までの適正な処理を確保する事業者の処理責任」を徹底させるため、「中間処理業者から最終処分の終了した旨の記載がされたマニフェストの送付を受けることにより、最終処分の終了を確認できる」ようにし、もし180日以内に「送付を受けないときは、処理の状況を把握するとともに、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じ、さらにその講じた措置等を都道府県知事に報告する」ということが目的のようです。
簡単に言うと、「中間処理から先=最終処分で問題が起こった場合に、排出事業者にも責任を取ってもらう」ための法的な根拠が欲しかったのでしょう。つまり、個別の1次マニフェストに2次マニフェストを直接結びつけ、2次以降の不法投棄についても、個別具体的な責任問題として撤去などを求められるようにしたのだと思います。それまでは、「最終処分までの適正な処理を確保する事業者の処理責任」は単なる抽象的な掛け声に終わっていたのかもしれません。
ところが紐づけ管理は、中間処理の現場の実態を知っていれば、机上の空論でしかないことがすぐにわかります。処理を手作業で行っているならともかく、破砕~自動選別、焼却、中和~脱水といった自動化されたライン・装置で、大量に処理をしているところを想像するだけでも十分でしょう。個別の物品管理は入荷の段階までで、それ以降は装置の運転管理こそが適正処理に必要な業務となります。特定の1次マニフェストが、中間処理後に出てきた物のどの部分に該当するのかなど分かるはずもありません。
したがって、紐づけは書類上は行われているようでも、現実とは関係がないため、それ自体には、意味はないのです。
このように現実論として、管理も把握もできないのですから、排出事業者に中間処理後の不適正処理の責任を個別に負わせるのは、無理があるのではないでしょうか。権限がない者に責任を負わせることはできません。
例えば、クリーニング店で有機溶剤による土壌汚染が発生した場合に、そのクリーニング店の過去の利用者に浄化費用を請求すべきでしょうか?OEM先の工場で労災があった場合、発注元企業はその責任を直接負うのでしょうか?そんなことはないでしょう、仕事を発注した者としての間接的な責任があったとしても、基本的には業務を受注した側の問題です。
とはいえ、処理業者が倒産した場合の、廃棄物の撤去や浄化のための費用は、①排出事業者、②税金の順で負担すべきとも思います。基本的には受益者である発注者が責任を負うべきだからです。しかしそれば、個々の排出事業者の廃棄物に対してではなく、集団的な連帯責任、それも(現在事実上そうであるように)無過失責任でよいと思います。委託実績数量に応じて、費用を案分すればよいのです。
現在、2次マニフェストの紐づけ管理を維持するために、契約書、マニフェスト、帳簿管理に相当なエネルギーとコストがかかっています。人手不足の時代に、国が先頭に立って効果が低い仕事を創出している場合ではないはずです。
将来的には、中間処理以降のフローについては、一定の要件を満たしたIoTシステムの導入を条件に、契約、マニフェスト管理を不要とするといった、アナログ管理からの思い切った脱却を目指すべきだと思います。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行について(本サイトはこちら>>)
八 産業廃棄物管理票制度に関する事項
産業廃棄物管理票制度は、事業者は産業廃棄物の処理を委託する際に、処理業者に産業廃棄物管理票(以下「管理票」という。)を交付し、処理終了後に処理業者からその旨を記載した管理票の写しの送付を受けることにより、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認することで、適正な処理を確保する制度であるが、これまでの制度では、事業者が産業廃棄物の中間処理を委託した場合にあっては、中間処理の終了しか確認できない仕組みになっており、最終処分までの適正な処理を確保する事業者の処理責任が徹底されていない問題があったことから、事業者が最終処分の終了した旨の記載がされた管理票の写しの送付を受けることにより、最終処分の終了を確認させることなどを目的として、次のとおり制度を強化したこと。
1.最終処分業者は、中間処理業者に送付している管理票の写しに、最終処分の終了した旨を記載することとし、中間処理業者は、最終処分の終了した旨を記載した管理票の写しを事業者へ送付すること。
2.事業者は、最終処分の終了した旨を記載した管理票の写しの送付がないときに、状況把握及び適切な措置を講ずること。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行について(本サイトはこちら>>)
第九 委託基準の強化
1.許可を受けた処理業者であって、委託の内容がその事業の範囲に含まれる者に委託することとの委託基準の遵守を担保するため、事業者は産業廃棄物の処理を委託するときは、委託契約書に許可証の写し等を添付するものとしたこと。
2.無許可業者への再委託を防止するため、事業者が産業廃棄物の処理の再委託を承諾するときは、承諾に係る書面に再委託する処理業者の許可番号等を記載することとし、その承諾に係る書面の写しを五年間保存するものとしたこと。
3.事業者は産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならないことから、産業廃棄物管理票により最終処分の終了を確認することと併せて、委託契約の段階においても最終処分の予定を把握するため、産業廃棄物の中間処理を委託するときは、委託契約書に最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力を記載するものとしたこと。
4.「最終処分の場所の所在地」は、住所、地名、施設の名称など最終処分の場所を特定する事項を記載するものであること。
第一〇 産業廃棄物管理票制度の見直し
1.事業者が産業廃棄物の中間処理を委託した場合にあっても、中間処理業者から最終処分の終了した旨の記載がされた産業廃棄物管理票(以下「管理票」という。)の写しの送付を受けることにより、最終処分の終了を確認できるものとしたこと。
2.事業者が管理票に記載すべき事項に、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地を追加するものとしたこと。また、中間処理業者については、中間処理産業廃棄物に係る管理票交付者の氏名又は名称及び当該管理票の交付番号を記載するものとしたこと。
3.最終処分業者は、最終処分が終了したときは、管理票に最終処分の場所の所在地及び最終処分終了の年月日を記載して、その写しを中間処理業者に送付するものとしたこと。
4.中間処理業者は、最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、事業者から交付された管理票に最終処分の場所の所在地及び最終処分を終了した年月日を記載するとともに、当該管理票に係るすべての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、一〇日以内に事業者にその写しを送付するものとしたこと。また、中間処理業者におけるこれらの管理票に係る義務の履行を確保するため、管理票に係る事項を帳簿の記載事項に追加したこと。
5.事業者は、交付の日から一八〇日以内に最終処分の終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けないときは、処理の状況を把握するとともに、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じ、さらにその講じた措置等を都道府県知事に報告するものとしたこと。
6.管理票に係る義務の履行を確保するため、管理票の不交付、管理票の写しの不送付、保存義務違反などを罰則の対象に追加するとともに、措置命令の対象者の要件に追加したこと。
(リバーグループ/メジャーヴィーナス・ジャパン株式会社 シニアコンサルタント・行政書士 堀口昌澄)