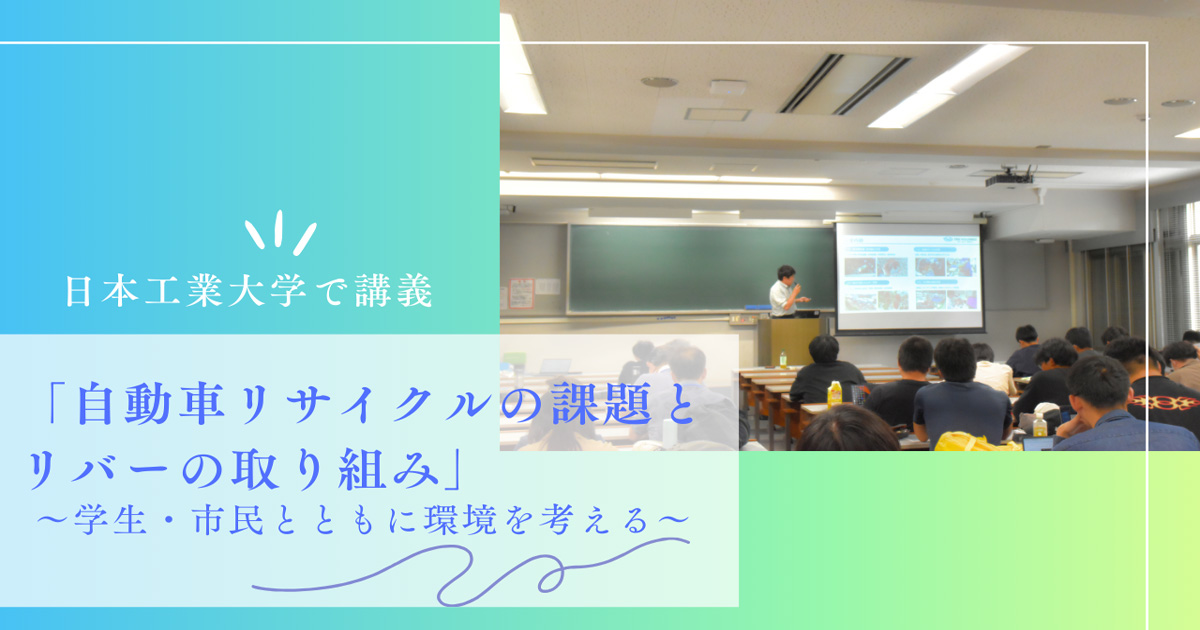一人ひとりの行動の変容を促しごみの削減に繋げる?|環境省が立ち上げたプラスチック・スマートとは?
2020年11月05日

この記事のポイント
・「プラスチック・スマート」とは、環境省が2018年10月に立ち上げたキャンペーン。
・世界的な海洋プラスチック問題の解決に向けて、個人、自治体、NGO、企業、研究機関など幅広い主体が連携共同して取り組みを進めること推し進めることを目的としている。
・サステナビリティにおいて、本当に大切なことは「一人ひとりの行動の変容を促すこと」
目次
プラスチック・スマートとは
環境省が、「プラスチック・スマート」キャンペーンと称し、海洋プラスチック問題の解決に貢献できるような活動を登録、閲覧できるサイトを運営しています。もちろん、プラスチックの問題は海洋に浮遊するプラスチックだけに留まらないのですが、消費者ウケがする分かりやすいテーマに絞って打ち出し、世論を高めていくという狙いなのでしょう。ウェブページを見ると、プラスチックに関する様々な取り組みがあり、海洋プラとは関係なくても参考になる事例が掲載されています。
事例は約1300件あり(2020年11月現在)、検索がしやすいように、カテゴリー化されています。カテゴリーには下記のようにいくつもの種類があり、親しみやすい表現の割には、なかなか網羅性が高いと思います。(下記の“・・・”以下は堀口解説)
- 究める・・・研究などをすること
- 減らす・・・マイバッグなどで使用量を減らすこと
- 広める・・・途上国支援
- 拾う・・・海岸や街の美化活動
- 使う・・・再生プラを使うこと
- 凝らす・・・容器を薄肉化するなど工夫する
- 伝える・・・地方紙などでのキャンペーン
- 替える・・・素材を他のものに代替すること
- 戻す・・・ボトルtoボトルのように元に戻すこと
- 作る・・・バイオプラなど新しいものを開発すること
- 分ける・・・プラスチックの選別
- 教える・・・学校などへの出前授業
こうして改めてみると、様々な活動が考えられるものです。キャンペーンの詳細資料で、内容の例示がされているのですが「拾う」についてICCとアダプトプログラムという聞きなれない取組みが挙げられていました。
ICCはInternational Coastal Cleanupの略で、いわゆるビーチクリーンアップ活動の国際ネットワーク組織と言うとイメージが沸きやすいと思います。日本では一般社団法人JEAN(Japan Environmental Action Network)が推進しています。
アダプトプログラムは、公益社団法人食品容器環境美化協会が支援している活動で、ウェブページによると、アダプト(adopt)=養子という意味で、「一定区画の公共の場所を養子にみたて、市民がわが子のように愛情をもって面倒をみ(=清掃美化を行い)、行政がこれを支援します。」だそうです。地域の清掃活動を、一歩も二歩も進めたコンセプトだと思います。
そしてなんと、実施自治体数が400以上、活動者数が約250万人もいるそうです。およそ40人に1人の日本人が活動していることに!!
海洋プラスチック問題は、「ポイ捨てをする人のモラルの問題」と言って、自分とは無縁の話だと思っている方は少なくないと思います。しかし、このような活動が世界中に広まっていけば、海洋へのプラスチックの流入も大幅に減るでしょうし、これまでポイ捨てをしていた方の意識向上に結び付くかもしれません。
本当に大切なことは「一人ひとりの行動の変容を促すこと」だと思えば、とても重要な活動のような気がしてきました。いや、それどころか、これこそが、唯一にして最強の解決策なのではないでしょうか。プラスチックリサイクルの推進など、海洋プラ問題にはあまり関係がないでしょうし。
皆さんも、会社でポイ捨てごみのピックアップや美化活動に参加されているかもしれませんが、地域でも同様の活動をやっていると思います。参加されてはいかがでしょうか?
(リバーグループ/メジャーヴィーナス・ジャパン株式会社 シニアコンサルタント・行政書士 堀口昌澄)