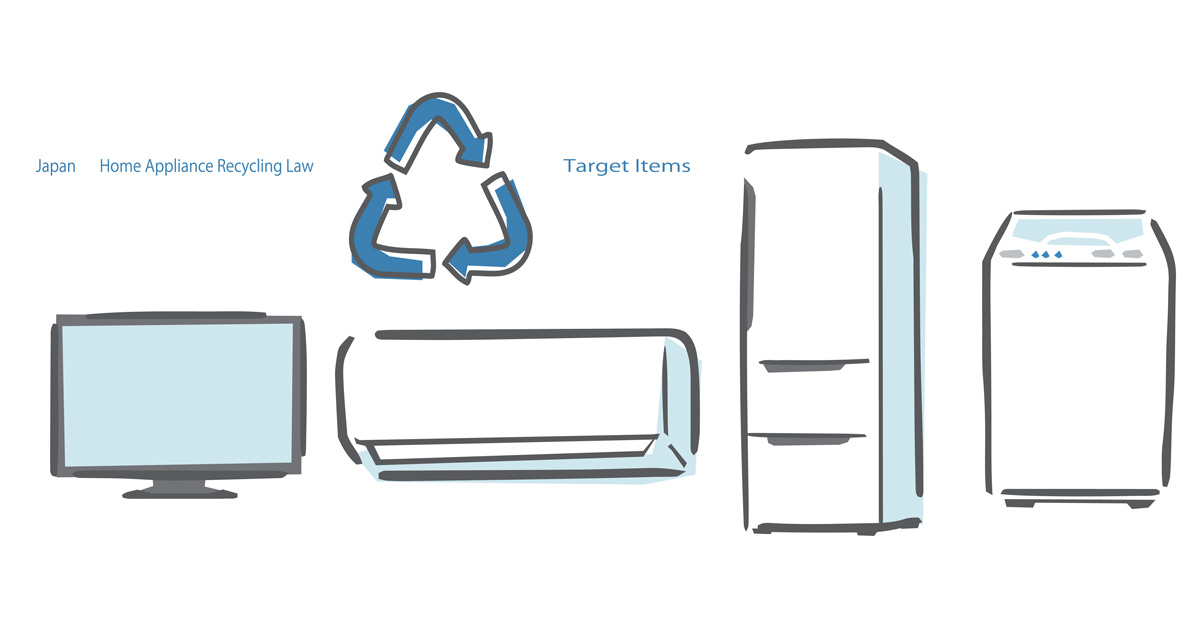公民連携による新たな資源循環の構築!
那須事業所×那須塩原市による一般廃棄物のリサイクル実証
初回荷受け篇
2025年09月30日

2025年7月にリリースでお知らせした当社那須事業所と那須塩原市による公民連携の実証事業(※1)では、地域社会における新たな資源循環モデルの構築を目指し、一般廃棄物由来の「破砕残さ物(※2)」の再資源化に取り組んでいます。そしてこの度、実証の初期段階にあたる「成分分析」を目的に、同事業所にて破砕残さ物の初回荷受けが行われました。
本記事では初回荷受けの様子をご紹介するとともに、那須塩原市 環境戦略部サーキュラーエコノミー課 課長 小野様に実証の経緯・背景をはじめ、当社への期待や今後の展望についてお話を伺いました。なお、本事業に関する取り組みについては、進捗があり次第、連載形式で情報発信をしていきます!
※1 実証の詳しい内容は、こちら(https://www.re-ver.co.jp/news/files/rv_news_20250718.pdf) をご確認ください
※2 不燃ごみ処理工程で発生する残さ物であり、従来、全量が埋立処分されてきました
目次
現場レポ! 初回荷受けの様子
9月5日、台風15号の接近に伴う雨模様の中、「破砕残さ物」の回収を目的に那須塩原クリーンセンターを訪れました。同センターは、那須塩原市から排出される一般廃棄物の処理を担う中核施設です。

当社の回収車両が到着しました。回収した破砕残さ物の重量を把握するため、事前に車体重量を計測し、クリーンセンター内の保管施設へ進んでいきます。そして、いざ破砕残さ物とご対面! 初回荷受けのため量はさほど多くありませんが、クリーンセンター職員の工夫によって、選別時に課題となる細かなダストが少ないクリーンな破砕残さ物です。

続けて、保管施設から回収車両へ運び込み。積込車両で3往復し、全量を積載しました。

積み込み完了後に再び車体重量を計測し、那須事業所へ回収した破砕残さ物を運搬。初回の受け入れ量は510㎏となりました。
初回受け入れ分を載せたコンテナ車が那須事業所へ到着! 今回受け入れた破砕残さ物は、実証用に確保したスペースで管理・保管します。
那須事業所では、今後も定期的な素材回収と選別工程への投入を進めることで、各種検証を段階的に進めていく予定です。本実証の進捗については、引き続き現場の様子を交えてご紹介してまいりますので、ぜひご注目ください
◆那須塩原市 ご担当者インタビュー
公民連携で、那須塩原市の資源循環をさらなる高みへ
初回荷受けを終え、本事業はいよいよ検証フェーズへと移行し、地域の資源循環モデル構築に向けた取り組みを着実に推進していきます。こうした動きを踏まえ、本事業を共に推進する那須塩原市 環境戦略部サーキュラーエコノミー課 課長 小野様に、今回の取り組みに至る経緯や背景ほか、当社への期待や今後の展望についてお話を伺いました。
公民連携で、“環境負荷の低減”と“地域活性化”の両方をめざす
――改めて、本実証事業に取り組まれた背景と公民連携の意図についてお聞かせください
那須塩原市では、令和6年度に「廃棄物対策課」から「サーキュラーエコノミー課」に課名を変更しました。これまでのごみの減量、リサイクルの推進に加え、他分野との連携を進め、地域経済の活性化にどのようにつなげていくかが重要な課題であると考えています。
そうした中、那須塩原クリーンセンターでは、不燃系廃棄物由来の金属類の再資源化および最終処分場への埋立量の低減が課題の一つでありました。市の保有するリソースだけでは解決が難しいこの課題に対し、民間事業者の知見や技術を活用することで解決を図れないかと考え、今回の「令和7年度地域の資源循環促進支援事業」に応募申請をいたしました。
地域の課題に、技術と知見で応えるリバー
――今回、なぜリバー㈱にお声がけいただいたのでしょうか?
リバー那須事業所には、以前から小型家電や製品プラスチックの処理といった業務を委託していました。那須事業所の工場見学をさせていただいた折に、本市の金属類再資源化の課題を相談したところ、連携の可能性があるとのことで、協議を重ねて実施可能な事業スキームを醸成いたしました。リバーの再資源化に対する高い技術と豊富な知見を活用して、本市の課題解決を図っていきたいと考えています。
共に手を携え、資源循環の輪を広げたい
――本事業に期待する効果について教えてください
金属資源の再資源化による地域経済の活性化と、最終処分場への埋立量の低減による環境負担の軽減を目標としています。加えて、実証の上、本事業の効果、継続性を確立し、事業結果の他自治体への共有を図ることで、資源循環の輪を広げることができればと考えています。これまで市のみで行っていた一般廃棄物の処理に、民間事業者のスキルを上手く連携させていくことを期待しています。
公民連携で循環の輪を、サーキュラーエコノミーの概念を広げていく
――今後の展望や方向性をお聞かせください。
今回の事業は金属類の再資源化にフォーカスしていますが、プラスチックや紙資源等、本市が資源循環に注力しなければならない資源物は多数あります。それらについても民間事業者と連携しながら、効果的な手段を検討していきたいと考えています。
また、本市は生乳産出額が全国2位の自治体ですが、例えば乳牛の飼料を再資源化由来のものにする、生乳の加工過程で発生するホエイを再利用する等、サーキュラーエコノミーという概念を一般廃棄物行政以外にも適用させ、本実証事業を契機として、行政が抱える様々な課題を公民連携の力で解決していきたいと考えています。
本実証事業について
「不燃ごみにおける金属類の高度リサイクル事業」
那須塩原市では「第 2 期那須塩原市一般廃棄物処理基本計画」に基づき、ごみの減量化、再資源化を推進している。そうした中、同市の廃棄物処理を担う「那須塩原クリーンセンター」では、主に不燃ごみ・不燃系粗大ごみの処理工程で排出される「破砕残さ物」について、未利用金属等の再資源化ができないまま埋立処分しているという課題があった。
こうした課題に対し、当社は那須事業所の「高度選別技術」を活用した、公民連携による「破砕残さ物」の再資源化に関する実証事業を提案。本事業は環境省「令和7年度地域の資源循環促進支援事業循環型ビジネスモデル実証事業」に採択された。
同事業を通じ、これまで埋立処分としていた残さ物から未利用金属等を抽出、再資源化することで環境負荷の低減はもとより、埋立処理に掛かる処分費の削減など、環境面、財政面の双方から持続可能な資源循環スキームを構築。そして今後は、同様の課題に悩む近隣自治体に対して本循環スキームの水平展開も進めていく。